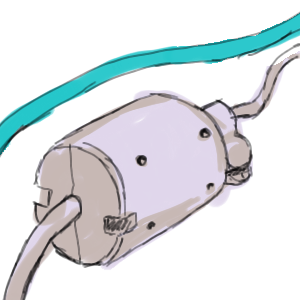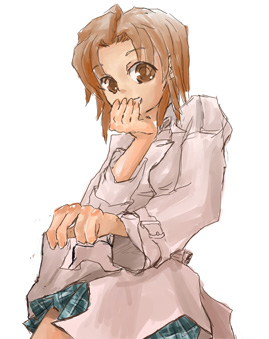|
|
��2006ǯ10��28��(Sat)��
���Ƥ��ޤ������äƤ��ޤ�
|
�Ф����μ������ȯ�����������Ǹ�ޤǸ��Ƥ��ޤä���
�˲��Ϻߤꤹ����
�ƥ���ɤ��ɤ���ˡ��������ͽ�ۤȤ��Ȥ��ڤäƤ��ޤ��ե졼���ο����ϰ����Ǥ����ʤˤ�ꥯ����ƥ������������Ƥʤ���
100�ʾ�λ����ɤ���Τˡ��ޤ�˰���Ƥʤ������������롣
��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/
�������̡�Ʒ����ʬ�˱��Ԥ��������������Ǥ�������꤯�����ޤ���
��������Ǻ�������ܤ���ˤ����ޤ����뤰���з빽����äݤ��ʤ��ʤ����ʤ��ȡ��ۤ�ޤ����ʡ�
| Replay
 | | |
|
��2006ǯ10��28��(Sat)��
������
|
Replay
 | ������������顼�����äƲ�������������㤤�ޤ�����
�ޤ������䡣
�Τ�Ʊ��������γ��餿��ƽƤߤ롣
�Ƴ����Ǥ��� | | |
|
��2006ǯ10��27��(Fri)��
�Ȥꤢ�������ɤäƤߤ�
|
Replay
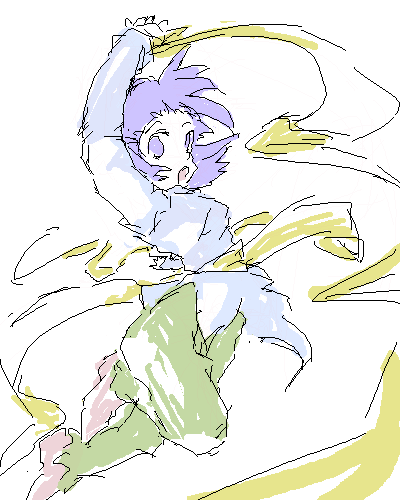 | ̵�̤�����ä�
���Ȥϴط��ߤ�ޤ���TO LOVE��κ�ɱ�μ�괬���ʥݥ˥Ƥ����ˤ��ʤ�Ȥʤ��ĥܤǤ���
�������괬���ߤ����ʤ�̵�����ʤ��� | | |
|
��2006ǯ10��27��(Fri)��
�Ȥꤢ�����Ԥ��ޤ����ä�
|
Replay
 | �������Ȥߤ����ʤ�ͽ�ۤȰ�ä��Τǥӥå���Ǥ���
�Ȥ���������ûҤǤ���ʤ����Ȥ�����
��ʬ��ͽ��
����ûҢ������ǥ��
���ᡡ�������ȥ��å���
�Ȥ������¤ä���ǯ�����ä��Τ�...
Ƥ�å����������äڤ����Ϳ���Ф��������ɤ��ä��Ǥ�
˷�������襤�Ƴ����Ƥ⤤���Ȼפ���Ǥ�����Ƥ���ʤ��Ȥ����Ƿ�Ʈ�������Υꥹ����ͤ�����Ե��������ɤ��Τ��⤷��ޤ���
�ɡ����Υ����Ĥ��Ƥ����Τϥ���������ˤϾ���˨���ޤ���
���ݤȤ���ڷ�����å�路����äƤ�������
���ȵ��Ť�����Ǥ����¤������ν��ͤäơ����������������Ǥ����
����Ҳ�����餫��
��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/
˨���������Ȥ��Υե���ϻ�����������
�����
��ʬ���������Ȼ�ή��ή����Ƥ餯��������Τǡ��ܿ������ϵդ�ή����ʤ����ߤ����ʤ��Ȼפ��������κ���
��Ĺ�äƼ�ʬ��Ĺ��Ф��ʤ��ʤä������꤫��ߤޤ��Ǥ���͡�
�Ǥޤ���˨�����μ��������Ȼפ���Ǥ���...�äơ�����������ä��ʡ�
| | |
|
2006ǯ10��26��(Thu)��
|
 | | ����ȴ���ȹ����������Ƥ��ޤ��ޤ��� | | |
|
��2006ǯ10��22��(Sun)��
���������
|
 | �������Υ����������ä��Ǥ��ͤ���
��������ҤΥ����ȻѤ��ɤ��ä�������Ѥ��夳�ʤ����äˡ�
���ˤ��Ƥ⡢��äѤ�����֥ɥ�ޤϤ�����
��æ�����ڥ���ä��Ĥ�ʪ����Dz��Ѥ��줿�ɥ�ޥ���ץ�å����������餤�������餷���Ǥ���������֥ɥ�ޤϤ�äѤꥵ���ڥǤ��ʤ�������
��
��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/��/
��ϻ�ƴ��ߡ����ԡ�
��Ϸ�ͤμ��Ȥ����Ĥ��������ˤ�ϩ�������롣
���������Τ����ޤ�褦�˾ФäƤ�����
�ֱ�ͺ���Ƥ�����Τ��ʡ����ͤ��ƿʹ֤餷���η��Ҥ������ä�����
���������Ǥʤ�ȩ�ޤ��ߤ��Ŀ����ˤ��ä���
��ʢ���鲫�Ф��Ͼ�����������������Ф��Ƥ��롣�ҡ���������·�ä�Ͼ������ü�ϡ��ϥ��ȥꥰ���Υȥ���פ碌�롣Ǯ�����ʤ�����������¡�������˰��������줽���ʶ����ʱԤ����ä���
�����¡�������ü�ˤ��֤������ֹ����줬ũ�äƤ�����
���ͤ��ͤȤ��ư۷��ˤʤä��ԡ�����°���ä���
�֤����������֤äפ���ʡ���������Ⱦ�ϻ����Ĥ����������볦���٤�����
�֤����á�����ʤ˺���Ǥ��Τ����������Υ������켫�����褩��
����°�ϡ�Ϸ�ͤμ�����̤���Ȥ��ƥ���Ǥ��٤����Τ褦��Ƨ�ߤˤ��ä���
�֤���Ȥ�ͦ�������������������Ĥ餬����ʸ����ͤ�ʤ���Dz��Ƥ����Τ����������Τ�ʤ�ʬ������ʤ�����������
�������ơ�������ۤ��Ƹ��ʤ��Τ����Ȥˡ��֤ͤ�褦�˸���³���롣
���ΤäƤ뤾�����������νпȤ��äƸ�������ͤ����������ʥ��ͤ��������ˤ��äơ�������°���������ޤ줿�����͵��α�ͺ�����ޤ��ʤ�Ƥ褩��
�֤����ޤ����������줿��οʹ֤��äƤ��Ȥ����ͤ�����������¿���ͤ����Ԥ��ͺ�ȸ��ä��餷�������������ϻ�ơۤϷ�ɤΤȤ�������������̣�Ǥ���������
�����ΤȤ��ä��ä���
���̤äȡ����椫�����꤬ƹ���ꡢ���Ф�����Ϥ����
�������Τ褦�˺٤�������������Τ�ʤ��Ӥ��ä���
�֤����ʤ������
�����դ�ߤ�ơ����μ�������ȸ��Ĥ����°��
�����νִ֡����μ̵꤬¤��˹����ޤä���
���ߤ�����ݤ��ޤ��褦����������������°�ϡ��������ʤ����ʤ뤫�Τ褦��ɽ�����餻����
�֤�����...�ʤ���
���ͤ������ޤ졢�����餶����°�ι���Ŵ�����Ǥ����Ȥ��Ȥ��ƽäγѤΤ褦�˻Ȥ����Ȥ⤢��ۤɤǡ��ְ�äƤ�ͤ���Ϥ��ޤ����ʪ�ǤϤʤ���
�����ι��������ʹ֤κ٤��Ӥˤ�äơ��ޤ�Ǿ��ޤ��ޤ뤫�Τ褦�˻ؤ��Ϥ������ޤ�줿�Τ���
�������Ӥϡ��ޤ줿����������ष����褦���Ϥ�����
�������ޤ�������������
�֤�...�������㤢������������
���ޤ줿���Ф������������Ϫ�Ф��Ƥ��������Ф�����ˤϡ����ȶڤ����Τ褦�˻������Ƥ��Ӥ��դ��Ƥ�����
�֤ơ��Ƥᤨ���������������������β�����
�������Ϥ���꤬�����ݤ��ơ�Ͼ���ι�����°�ι����ͤ��ɤ�����
������ǸƵۤ������ߤ����
��³���Ƽ�ϡ�����¡�ؤ��ͤ��ɤ�����
��������櫓�Ǥ�ʤ��Τˡ����Τ˰������ǻɤ��Ӥ��Ƥ�����
�����ΰ��ǡ���°�ϡ���¸�ߤȤ��ơ�������䤨����
��ϻ�ƴ��ߡ�������
�ʡ���
������ϡ��������ܤ��Ƥ�����Ω�äƤ�����ǯ����
����ۤɻ����Ϥ��ξ�ǯʼ�Τ��ä���
�֤�����...�ڤäڤá������줵��˰³ڻव�����Ѥʤζ��碌������ơ�������δ��㤤��������͡��ġ��ˡ�
�������ˤ�줿�Ϥ��ι�ū�����褷�Ƥ��롣
����ǯ�ϡ�����æ���ǡ��ΤФ������ȱ������ä���
����ȱ���ä�����ȱ�ǡ����ܤ��ä���
������Ρ�Ʊ�����Ʒ�˾��������ɤ餰��
�ֱ�ͺ°��������ȱ������...ͦ�Ԥ�����
���Ҥɤ������Ӥ줿���ǡ�����ϿҤͤ���
������Ϥ��Ƥ��뤬���ޤ�ǵ��Τʤ��ֻ��Τ褦����������
��ͦ��...�äơ��������������ڤΤ��Ȥ������䡣�㤦���ɡ�
�������ꤲ�ΤƤơ�����Ԥ���°�λ��Τ�٤���
�ֶ�ȱ�α�ͺ°�Ϥ���ͦ�Ԥ����Ȼפä�����
�֤䡢�Τ��������ϥ��줬�����ʤ������...�Ƥ��������ꤳ���ġ���
����ǯ�ϡ�����ؤ�������
�־���˻����ư����ä��ʡ����礤Ĺ���ʤꤽ����������줷����ä�������ɡ����졢�Τ����εؤ��ä�������
���ͤ���°����ˤλϤᡢ�������켫����⤷����°��������ˡ������Ĥ���°��¸�ߤ����������ơ�
�֤���...�⤦�ɤ��Ǥ⤤�������ݤ��ʤ�����
�������ˤɤ��Ǥ�褵�����ˡ��ܤ������롣
�֤������ä��㤨��Ƚ�����衣
���ޤ������ʥꥪ���Ȥ���ͦ�Ԥˤ��줫����������ƥ����ĤȤ�ꤢ��������ɡ��Ǹ�ˤ����Ǥ��ˤʤäƻ�̤�����ɤ���
�������顢���줬�����Ƥ����ʤ��ȥ���ʤ���Ȥ֤Ĥ֤ĸ����ʤ��顢�����դ���롣��ǯ�ζ�����ϡ���¡���ͤ��ɤ����Ϥ��Υʥ��դν����ä��Ƥ�����
��...�����Ѥ�����
�֤��졢�ȥ���������
����ǯ�Ϥ���ˤ��������������������夫�鲼�ޤǹ������ȸ��Ĥ��
�֤ʤ�����ʤ���������ǥ��դǥϡ��ɥܥ���ɤäƥ�ġ����ե������˷��ѴݽФ��Υȥ����ʤ�ƥ����ǥ������ۥ��ۤ���ͤ����Ȥ�����á����ޤ��äƤ����ɡ�����Ϲ���������
���ˤ�ޤ�ȾФ������äƤ������������줷���Ҥͤ뤬�����������̵ȿ�����ä��ΤǤ����ܤꤷ����
�֤����������ܡ����Υ��å������������Ȥ��������礤���������ä���ä�������ɤ���ʼ�Σ���
���ȡ���ǯ�������Ӥ��Ȥ�ǡ��������ʤ��Ȥ�פ��Ф������Τ褦�˽Ҳ����롣
�֤ˤ��Ƥ⡢�����ʼ�ΤȤ���������������뤿�������¸�ߤ��륭���äƤΤ�ʤ��������ʤ��������Ĥ����ϡ����������˱����Ʋ��������Ȥ��Ƥ������Ĥ�ʤ�������������Թ����äġ��Ρ�������ʷڡ��Ȼ�˴���٥�ȤȤ���˴���ե����ȤȤ�¤��Ȥ������ޤȤ�ʿʹ֤��㤢�Ǥ��͡����
���ʤˤ���ʰ�ä��ͻҤǡ��������������
�����������������ž���ä���
��©�Ѥ��βˤ�ʤ��䡹������³���뾯ǯ��
��ʼ�Σ��Ȥ�����������Ϥ⤦�⤦̵��̣�˻����줿�껦���줿�껦���줿��Ȥ���Ũ�����Ǥ�ñ�˥ܥ������λĵ�����ɽ������٤�����Ũ�˻����줿��Ȥ������������ä����ä��������Ȥ�����äˤʤä���Ȥ��֤��աפȤ����äƻ�����Ȥ������Ǥ������줬��������Ǥ����ߤ����ʤ���
���ޤ���������ǡ�������Ǥ⤿�襤��ʤ�Ĺ�ä�ʿ���Ǥ������δ֤˥Х�Х�ɥ�ɥ�����ꤹ�������̵�̤ʤ��Ȥ��Ƥʤ��ǰ��äǤ���з⤷�Ƥ�㤢��ʤ��˻����Τˤʤ��ä�Ÿ�������ۤɺߤ�櫓���������Υϥ��λ��֤�Ԥ�����˲�ã�ϻ�ˤޤ����Ȥ����⤦�ͤ���Ƭ����������ʤ��졣���Ф���ĵԤ��Ȥ��ꥢ��ͤ��Ȥ������ʤ��㤪���ͤǤ�¿����Ƴڤ���ޤ��Ȥ�����
����ʤ�͡��äġ��Ρ�
������ʤա��ˡ��ɤ��Ǥ��ɤ��������ä������ǥ��ե����ȤǤ��ä��껦���Ƥ��������ߤ����ʹͤ����������Х���������Ĥ���äơ����ȤΤ�����äݤɥ�Ф�����衣
���������ʤ�Ƥ衢��ï���ʤʤ�����¿������ɤ��Хȥ�ޥפȤ�������̡��ڤꤿ������ɤ������Ǥʤ��Τ�̾�����դ������������ǡ�Į�ͤȤ�����ʼ�ΤȤ����������Τ褦�˻��ǤƤ������äȤʤä��衣���äƤ���������
�������ĤˤȤäƤ����οʹ֤äƤΤϿͤȤ��Ƥ���ǤäƤʤ��äƤ��Ȥ���͡�����
���ޡ���¿ʬ����ʤĤ��Ǹ��ä���ʤ����������ɤ����Ǥ⡢����ʤĤ��Ǥʤ��äƻ���������äݤɥꥢ��˥�Х��Ȼפ�ʤ�������
������ϡ��ܤ�ݤ����Ƥ����ʹ���Ƥ�����
�����äƤ뤳�ȤϤ���ʤ������ʤ��ȤʤΤ�������������ˤȤäƤ��줬�ʤˤ������Ω�ĤΤ��Ȥ����ȡ���������ʤ��ȤϤʤ��ä���
���ʤˤ������ǤĤ��ȤǤ���äƼ�ʬ�����������褿�Τ������ȥ������äƤ�������ϡ���������ȴ�����ͻҤǡ�
�ֲ���������������
�֤��䡢�����ϵ�������������դΰ�ĤǤ���äƥ䥱�ˤʤäƤ�եꤷ�Ƽ¤Ϥ����Ǥ�ʤ�����������ϻ�Ƥν�ʤ���ڥ���åסۤȱ��������ʬ������äơ�Ÿ���ʤ�����ɤ������줽�������ζ�̣�ʤ����顢�ɤ����ʤ������ط��ʤ����̤Ǥ⤷�Ƥߤ褦���ȡ�
���Ȥ����������Υ��٥�ȥ��줢��ޤ깥������ʤ������ʡ��Ⱦ�ǯ���줤����
�֤�����°����äƤ��ߤ����ˡ������ˤ���ͦ�����ä���°����Υ��С��ʥ辰���������������켫����ä���°��ȯ��Ψ�����ͤ˹⤤���顢�����ܤ������Ƥ��������ˤʤäƤ��ä�̱���Ⱦ������ޤ��礦�ߤ�������Ĵ������Ƥ����ǡ�����¹Ԥ����������ᤤ�����⤬ͦ������¤���Ƥ�����
�����Ρ���������Ȥ��⤽�ΰ�����ä��櫓����
�����������饹�Ȥ�����ǵ��Ƥ���Ʋ������������ɤ�����������֤��Ƥߤ��Ȥ��Ƥ⤳�Τ�������ã�������٤˥������Ǥ��ˤʤ�äơ��Τ��ɤ����Ƥ�Ǽ�������ʤ��Ƥ��
����Ĥλӳ��ˤ��ơ���ǯ�Ϥ����ܤ䤯��
���ͤ�̿����˳ݤ����ǯ����ɤ�ʤ�����褽�����ѤȤ��������Ѥ��ä���������Τ褦��ȯ��������
������ɽ��Ϥ����äƿ������ä������Ť����ܤꤹ�餿�����Ƥ��롣
�������Ȥ�����ʡ������ϻ������������ˡ����������褿�Ȥ����Τ�����
������ϡ������ԻĤʾ�ǯ���ä��դ��礦���Ȥˤ����餷����
����ǯ��Ŭ������������
�֤��������ԿԤ��ä����ɡ�����ϥ����ʤˤ�Ǻ��Ǥ�Τ����ΤäƤ롣�����������ͤȽ��ƽв�ä����ǡ��������̤줿�����äƻ��⡢�軲��ΤĤ��Ǥ�������Ƥ��Τޤ������褦�Ȥ������Ȥ⡢���ι�β���������ɥֽ����������̤��Ǥ���ʵ�ʬ�ϼ��������Ȥ⡢�ʤΤ�ͦ������������꤬���Ԥ��Ƥ��Ʋ��⤫�⤬����ˤʤä����Ȥ⡣���������Ϥ��μ����褬�Ǥ٤Ф����Ⱦ����ϻפäƤ뤳�Ȥ⡣
��������ˤ�������줬�ɤ���������С����Ѥ�ꤹ�뤫���
������ϡ����ޤ�˾�ǯ�θ��դ����������Τǡ����Ф����
�֤����Фä���
�־Ф������ʤ顢�ʤ���������ʤ���������ȤƤ�����ʤ������⤷�����ˤ������Ȥ����顢���ΰ٤ˤ����ˤ������Ƥοʹ֤������Τ������䤬�������ƾФäƤ���֤ˤ⡢�����οͤȤ�餬���Ӥ껦����Ƥ��뤳�Ȥ�������
����ǯ�ϡ��Ҥɤ�ʰ�������ͻҤǡ֤��Τʡפ��줤����
�ָ��ä����������줸�㥢�����Ǥ��ޤ�����衣
��������ԿԤʻब��������̵��̣�˻������ʼ�Σ��⡢���ޤ��礦�����ǻ�̱�̿�ˤ����Ĥ⡢������뤿����������ޤ�Ƥ����褦��¸�ߤ���ä��餤�������ͤΥ����˺Ǹ�ޤ������Ĥ륭���������������ʬ��������٤Ǥ�ᴤ�ͦ��ã���������
�������顢˸�������褿����°�ˤ�ͦ�Ԥˤ⻦�����Ϥ��ʤ���
������Ϥ����������ԿԤʻ�������뤿��ˤ�äƤ�������������...���ͤ�ʥꥪ�֥쥤��������
����Ũ�˾Ф���ǯ��
����°�λ����ä������Ĥ����°�����ޤ�Ϥ���롣
������ϩ�Ϥ˽��ޤ���°����á�������ǯ�ϾФä��ޤޤ��ä���
�֤����顢����ϲ��ˤ⤤��ͤ��������ؤ�ñ�˻��̤����褿��������
��������ʪ��ͦ������������������
�������������Ŀ��ˤ����ξ夫�龯ǯ�˶�����ݤ��Ƥ�����
����ǯ�ϡ��Ƥ�Ťͤ��ޤ���������ޤ�����°�ο�¡�ˤ��Ф���ʤޤ����äƤ����ˤ�ɤ�����
�֤ޤ�������Ȥ��ƤϤ��������ʹ֤Фä��꽸��ƥϡ����Ȥ��Ĥ��ꤿ��������ɡ��ޤ�������ϲ������Ƥ��롣��������͡��Ȥʡ�
������ϩ���ǡ���������°��������ǯ���Ϥ���롣
���ޤ�Ťʤ�褦�ˤʤäƤ��뤿�ᡢ¾����°����Ͼ�ǯ�������ʤ���
����ǯ�Ϥ��λ�Ѥ�ǰư�ϲ�ϩ��Ÿ�����Ƥ�����
�����̵�������ϤDZ黻����Ƥ��뤬�Τ���ˡ�ȤޤǸƤФ�봰����ѡ�
��ȯư���롣
�֤������������դ�������̿�äƥ�Ĥϳ������ݤǤ衣�㤨����°�˻�����뱿̿�ˤ����ĤäƤΤϡ����α�̿������Ȥ��Ƥ��ɤɤ����̤ξ�����°�˻�����ƻ��Ǥ��ޤä��ꤹ�����衣
��Ʊ���Ȥ����Ǽ��Ԥ���ʹ֤äƤ������������̿�äƤΤϤ���ε�˷Ϥʤ���ʡ����äȡ�
��ú����ɹ�����������褦�ˡ����γ�Ҥ����Ф���
������ȯˤ���������Ӥ��Ȥ�����°����ä������ȸ��λѤ����ᤷ��������
����°��ʹ֤��ᤷ������������������Ѥϡ�
�֤ޤ����ԿԤ��ä���ʡ��饹��ľ���dzФ������衣����ϻ�������ξڤ����ꡣ�Х��������줬����С��ۤȤ�ɤΥ��ʥꥪ����Ǥ��ޤ��äġ��ˡ�
���ܵ����ܤ�ʤ��顢��ǯ�ϽѤ�Ÿ��������
����θ�������������Ǥ�����
�������Ȥ��ä��Τ����ڤ�©���Ǥ��ƤΤӤ���
������ơ���롣
�֤��㤢�ʡ������������ä����ɡ�����δꤤ�ϥ������ꥢ��������Ǥ�������ӤƤ�äƤ��Ȥ���������°���Τ�˰�����Τʤ顢����Ǥ�������ͤ�����
���櫓�狼��͡��������ˤĤ����äƺƤ��浪���Ȥ������פ�����äݤɥޥ�����̵�̤˻�̤ʡ����ȡ��ڥ���åסۤ����ڡ�������ʤ��ơ�ͦ�Ԥ��Ϥ��Ƥ����Ƥ��졣����ʤ��ȥ٥��ȥ���ɤˤʤ�͡������ʤˡ������դ˼ΤƤƤ����н�������
�֤���̵�������ʡ������
�����������ǵ������Ƥ�줿��������Ϥɤ�����쵤̣�ˤ������ä���
����ǯ��̵�ٵ��ˡ��Ϥˤ������
�֤ޡ����ԿԤ���äƤ���Ǥ͡�
�֤��줫��ɤ�����Ĥ�������
�֤ɤ�...�äơ����Υ��ʥꥪ������ˤ���������ɡ�����ϻ�ƤΡڥϥ�ޡ��ۤ��ä����ʡ�����Υ�ġ�
�֤�������
��ϻ�Ƥä�����輡�����������äơھڡۤ�å����륤�٥�Ȥ��������ɤ������⤦���ۤǤ����ȡ�������������Ʈ�����ƥ��Ѥ˶Ťꤹ��������Ũ�μ�ͳ�٤�̵���ʤä��ߤ����ʤ������ʤ�¤�äȤ��ʤ��顢ϻ�ͤα�ͺ�ȥХȥ���Ȥ��������ޤ����ˤ���������äƤΡ�����ʹ����ޤ������Dz��θ�����ʤ��襤��ϻ���֤����ä��οȤˤ�ʤ�äġ��Ρ��ɤ�ʥޥ��ץ쥤�Ǥ�����
���ɤ����ͥ������������ά�ѥ�����ޤä��襤�ʤ�ƶ��ˤǤ����ʤ��äġ��Ρ�
�����������οʹ֤ˤ�����������ǽ�θ��դ�ܤ䤭³���뾯ǯ��
�������˼�ʬ�ζ��Ԥ����줤�Ƥ��ʤ��ΤǤ��롣
���䤬������ϡ���Ф��ʤ����������
�֤ʤ顽����
��ϻ�Ƥ��äϤ����ǽ���롣
��ͦ������ͦ�Ԥ��������֤ˤ��Ϣ��������Ʒ�����Ѥ�ž�ܤ��Ƥ��������ˤϡ������̵�������ʥꥪ�ΰ�ʸ������Ȥⵯ��ʤ��ä��ΤǤ��ä���
��
��ͦ�Ԥϡڥ���åסۤ������줿���ޤ�����ޤ�������
�ʡ���������
| | |
|
��2006ǯ10��21��(Sat)��
ϻ�ƴ���
|
Replay
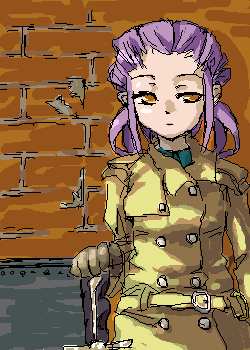 | ���������д�����ߤ겼���륨�ݥ�åȡ��ƾ������롢�����������ۡ�
�������Ƥ�֤餻���뤿��Σķ����������ο������Υ������ޡ���µ�٥�ȡ�
������ʲ����Ǥ����衢ť߿�ϤǤ��Ϲ�������ꤷ¤��줿�٤��Ϲ������Ȥ�̾���դ���������
�������鲿�ޤǡ֤��������פǤϤ������ʤ�����������¿����ʼ��ã�Ϥ������˻פ����ȤϤʤ��������;͵����Φ����������ʪ��Ȭ�䤬����䤨��������̵���ʤäƤ�����
����������������˲Ȥ����¤�ϻ�Ĥ����ΰ�Ĥơ��������Ϥ��λ���˺ߤ�Ϥ����ʤ����ԻĤ˻פ������Ǥ�������
��ϻ�ơ�����Ф���Ǥ����ƤФ줿��ͺã����Ǥ⡢����ϰ�ݰۺ̤����äƤ�����
�����Ĥ��Ϥ�������åפ���ķ��ʤ���⤢�����ʤ��Τ����ˤꤷ��ơ�������ܤ��Ĥ��Ƥ�����
�����Ƥ���Ȥ����櫓�ǤϤʤ�����������ͺ�ϱ�ͺ��̾��Ϣ�ͤ������ǿ�̲�����ɬ�פ������ߤ���å���Ƥ�����
��̴�⸫�뤳�ȤϤʤ���
�������顢�ܤ��Ĥ����Ȥ����ǡ������פ��Ф����Ȥ����Ǥ��ʤ��Τ��ä���
��̴�ˤ�����Τ��ۤ��Ф�
����ū��³�����ޤ˷��䡣
���̤ζ����������ߡ��������ޤäƤ�����
������ϡ��ޤ��ܤ��Ĥ����ޤޤ��ä���
���������켫���衢�Ȥä�����άŪ��̣��ä����������ϩ���ǡ������ۤ���ư���ʤ���
�����Ĥ��ɤ�����Ȥ�ʤ�ʹ�����Ƥ��롣
��
�����������ʼ�Τ���ϩ�Ϥ��鸽��롣
�֡����͡��ʤ����ʤ��ΤǤ��á�������äƤ���������
�����νִ֤ˤϻ�ҷ�����ä˽���������졢��ū���ˤ��롣
����ʪ���α���äϡ����Τޤ�����˽������������Ȥ�����
�����������ˤ��μ��νִ֤ˤϡ��˲��ۤ���Ѥ��Ȥ߹������Ƭ�����ͤ��ɤ��äƤ��롣
�������ͻ�����Ƭ������ä������Ȥ���¨�¤˽�����Ϥ�뤬�������ĥ��줿˸���η볦��������˻ߤ��롣��äϼ�ä�ǭ�λ�ȤʤäƲ̤Ƥ���
�����Ͱ��Ȥξ��⤬���ؤ��Ȥߤʤ���ޤ�ϩ�Ϥ��鸽��롣
����ͤ������ˤ�줿ʼ�Τ�ʹ������
��©�����ä��������Ť��Բ�ǽ���ä���
����Ĺ�餷����ʪ�����Υʥ��դ����ȴ����̵¤���ʼ�Τζ����ͤ��ɤ���
���⤦��ͤ��������Ф��ƥʥ��դǺ�ä���
������������ä���Ĺ�ϡ�ʼ�Τ��ܳ�����Ȥ��Ƥ��������ȷ��Ǩ�줿���ˤĤ�����
���������뻰�͡�
�����Τ�����Ĺ����������ؤȿ����������
��Ϸ�ͤ��ä���
�֤ޤ�Ƨ���ڤ꤬�Ĥ��ޤ�����
��...����Ȥ⡢�⤦��°�Ȥ����ʤ��Ĥ��Ǥ�����
����°�Ȳ��������ͤ��������Ϥ��ΰ٤˱�ͺ�ˤʤꡢ�����Ƥ�����Ū��̤�����
���������顢�⤦���ʤ��Ĥ��Ǥ�������
��������ϻ�ƤȸƤФ줿��ͺã�����ϡ�������������°������̤Ƥ��Ƥ����Ԥ��٤˿ͤ�ΤƤ���ã�Ǥ��롣
����Ƥ���Ť���٤����ͤ�©�Ҥ�Ʊ��̴�����ä�ͧ�ͤ�
�������ͤ��������Ǥܤ���������ˡ��ͤ�ΤƱ�ͺ�Ȥʤä��ԡ�
����ͺ����ˤϡ�����̤������ִ֤˼���μ��ķ�����Ф����Ԥ⤤����
����°�⽽�ΰʾ夤�������Ǥ����������ι�˲����Ѥ�����Τ��Τ�ʤ����������繶�����������Ǥ��ʤ������ʤ���С���ʬã�ϴ֤�ʤ�����䤷�ˤ���뤳�ȤǤ��礦��
��...�볦�ε����⤢�ȿ�ʬ�⤢��С��˲�����뤳�ȤǤ��礦�������ʤ�Ф��Ȥϰ���Ū�ʵԻ������桹�˽���뤳�Ȥȸ�����...�������äȲ�������ͧ�����ȤΤʤ��褦�˽��֤�ܤ�������
�֤���Ǥ�...��äƤϤ���ʤ��Ȥ����ΤǤ���...��
�������Ԥä�Ϸ�ͤϼ�ä���
�������ʤ��顢�꿮���Ф���
�֤��������椬�����������ʡ��ष��ͦ�Ԥ��٤ء���
���볦���餹��Ĥ��ʤΤ����������ʤϺƤӿط��ǡ��濴�ؤ�����Ф�����
��
������ϡ���
�� | | |
|
��2006ǯ10��20��(Fri)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
���Τ��˸��������ͤ���ȿͤȤδ֤������롢�������٤���֤���
���ɤ�����ѤʤΤ����ɤ�ư���д��������Ǥ���Τ����ɤ��ʤ���ɤ����ޤ줺�˺Ѥ�Τ���
���ФȤ��Ƥηи����������ˤ�����������Ǥ�����
���ͤ��������;�Ϥ�ʤ���ϩ�Τ褦�������ε������ѥ���Τ褦��ʣ���ʥѡ��Ĥ��Ȥ���������ܤ�����褦�ʹ����Фä�������Ƨ�߾��ʤ��٤�ƻ���Ϥä��������̤ƤΤʤ����ʤ������Τ褦�˶�夬��³����������
������餬�����⤴�Ȥ��λ���������Ū�ͤ������ʵ�ư�Х���Ф������Τ餺�����ҥ奦����Ϳ���Ƥ���롣
���ͷ������ι��⤬���ꥮ��ǥҥ奦���β����Ƥ��ä���
�����٤⻦�����Ȼפä����������٤ˡ��ϥХ�����������ҥ奦����Ƴ���Ƥ��줿��
�֡�����������ư��³��������֤Ĥ������������ꡢƨ���ʤ���Ĥ��Ǥ˹��⤷��������Ȥư��а�ˤʤ餺�����¿�а���ݤ�³�����������Ϸ��Ѥ��ǿͤʤ�С�Ũ����������ܤ�����Ȥ����ͣ�졢�����οͿ���¿���ɤȸ������¤�������̵�������̤˹ͤ���Ф���������Ǥ����ʤ���������Ũ��ʣ�����Ȥ������Ȥϡ�ʣ���Ǥ��뤬�Τ˷�֡����䤬���ޤ��ȸ������ȤǤ⤢�롣��ޯ��ߤ����̤��������ξƤ��Ф�������ũ�Τ褦�ʶϤ��ʸ�����������ͣ�졢������ͣ���դ����뤳�Ȥ��Ǥ����ʤΤ�������������ѤĤ�������֤������졣�ᤶ�Ȥ�����Ĥ��������˳������
���ޤ��̵�������������ä������ϥХ��������������˼�ʬ��ͭ���Ǥ���褦�˴����뤫���ԻĤ���
���ͤ����⤬�����٤�ҥ奦����¦��Ϋ��Ƥ�����
�����Ĥ�����ƨ���ڤ줺�˻¤���Τ������ȳο����ʤ��顢����Ǥ�ҥ奦����ƨ��³�������ԻĤȶ��ݤϤʤ������ݤ���С����νִֻ�̤Τ������ʤȻפä����ʤ�ȤϤʤ��ˡ�����ľ�äƤ�����
����꤬�ڤ��ʤ롢�������˹��⤬Ϋ��ʤ��ʤäƤ�����
����˻�Ѥ�������ऻ���ǡ��ͷ������ι���ϰ�⤿��Ȥ�����ʤ��Τ���
�����Τ�̵���ʻ������ɤ����������Ȥ���ž��Ǥ�����
�����Τ������������ڤä������̤οͷ���������ݤ줿��
��Ũ����Ϯ����Ƥ���Τ�����˼��褦�˲�롣
���ޤ��Ǥ��Ƥ⤤�ʤ��Ȥ����Τˡ��䤬����֤����ɤ���ȯ������Τ����ɤ�롣
�����ˤɤ���ư���Ф����Τ��������������������Τ�ä������鸫���Ƥ��롣
��������夰�������ȩ��ʤ���
�֤äȡ����⤷�ʤ���...��
��;͵�����ޤ�Ƥ����Τǡ��Ĥ��Ǥ˹����ä��Ƥ�����
���ǥ��������ڤ�̣�Ϥޤ���äƤ��ʤ��ä������ߴ��������Ӥ���á���٤����Ȥ���ǰ�������¤��������Ͽ���Ū�����ʤ��ä������ʤ�Ȥ���ʴ����Ǥ��롣
���襤����ǡ�����ʷ�������;͵�����뤳�Ȥ˾����ä���
�������ͤοͷ��˰Ϥޤ�Ƥ���Ȥ����Τˡ�ʪ���������ʾ��ˤ���ߤ���������夤�Ƥ�����
���ʤ�ۤɡ��Τ��˰��а���ä��Ȥ���������ۤɶ����ä���
�����⤬�ä������ȡ�Ũ�Ϥ��ä��ʤ��ݤ�Ƥ��ä���Ũ�����ʤ��ʤ��٤�ƨ���䤹���ʤ�Τ�����ȿ����������֤⾯�ʤ��ʤ롣
�֤äơ�������а�ˤʤä���ɤ������...��
�ֹ��פ���Τ��ʡ�����Ǥ⡢�⤷���а�ˤʤä����
�֤ʤä��顩��
��ƨ�������ʡ�
��...���ͤǡ�
�������鲿�ޤ����������ʤ����ȷ��Ѥ��Τ�̥ҥ奦���Ǥ����פä��Τ��ä���
�� | | |
|
��2006ǯ10��20��(Fri)��
���ޤ�ˤ��礭�ʡ��Ϥ��ɡ������ΰ�
|
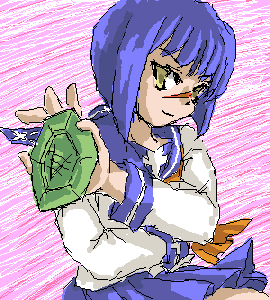 | �轵�ϸ��꤬¿���ʤ���
ǯ����ȴ���������ü�ޤ�ʤ����ߤ�����
���Τ���������ϣ��Ϥ�����ʰ�̣�ǥϥ�ϥ餷�ޤ�����
�������顼�ˤʤä����������ӡʤ�����ʰ�̣�ǡˤǤ�������
���ȡ�������������罸�Ȥ��� | | |
|
��2006ǯ10��19��(Thu)��
�Ĥܤߤ����Ĥ��֤Ҥ餯�褦��
|
Replay
 | ���˥�ݥ����ǰ���ͥ���ʵ��ȸ����Ф������
�֤��碌����
�ʤ櫓�ǡ��ºݥȥ졼�ʡ����֤��碌�פȸ����С������Ƥ��Υݥ�������ȤФ����Ũ�ι���路�ޤ���ޤ�
�Ȥ��˥��ȥ��Ϥ��Ȥ��뤴�Ȥˡ֤��路��10���ܥ�ȡ��פȤ��֤褱���ԥ����奦���פȤ��֤��路�ƥܥ�ƥå����פȤ����Ÿ��вС������蘆�줿�������ä��碌�ԥ����奦���פȤ��褯��ޤ��ԥ����奦�Ϥ���ʥ��Х��Ȥ�̿�������פ���ʤȤ��פ��櫓�ǡ�
���������Ρ֤��碌���ס��Ҥ��礦������Ŭ�ä�̿��Ǥ⤢��ޤ���
�ޤ������魯�����ߥ�Ҵ�Ū��¬�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����ͷ⡦ˤ�⡦����ϸ����˵ڤФ��ϥ�ɥ�����ʥӥ����Ȥʤɡ��ѡ��ȥʡ��˹�ư�䥿���ߥ�Ǥ����ȸ����٤ϡ��ʹ֤ɤ����Ǥ����ˤ˸����ޤ���
�ޤ����ݥ���餹��С��ۤ�ȿ�ͤΤߤ�ư�����Ȥ�����뤿�ᡢ��ʬ�ǹͤ��Ʋ��������ư��Τ���ʤ�ȸ�������������ޤ���
����ˡ��ȥ졼�ʡ��ʻش����ˤΡ֤��碌�פȸ���̿��ˤ����մ���θ�ǽ�⤢��ޤ������곰�ι�����ܤ����ˡ��������֤ˤʤä��ݥ��������֤餻���ꡢ������Ф���̵�ռ��˶�ĥ���Ƥ��ޤ����֤��֤Dz�����������̤�����櫓�Ǥ���
�Ĥޤꡢ�֤��碌�פˤϤ��魯��ư�����褦��������¥�����Ѥ�����ΤǤ���
�ʾ夫�顢���ȥ��Ρ֤��碌���פϤ�����̵�����äƤ�櫓�ǤϤʤ�����ѤȤ��Ƹ���Ū��̿��ȸ����뤳�ȤǤ��礦�����֤�
| | |
|
��2006ǯ10��19��(Thu)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
�������ˡڿͷ��ۤΰ��Τ����ꡢ��꤫�֤롣
���Ҥɤ�̵¤����ä���
�����ɤ����롣��Ǽ����ߤ��Ф����Τ����������ߤ���ȤϤɤ�����Ф����������䡢���⤽�Ⲷ�˼����ߤ����Τ������⤷���줬���ե�����Ȥ��ä��顩��
����������
���ϤäȤʤäơ��ҥ奦���ϲ����������
���Х����ȡ��Ϥ������Ǥġ��Хͤ��Ƥ����褦�ʿ�ư����������
�֤������碌��...��
�ָ������������餤��ï���äƽ���롣����ϰ�ͤǤ������뤫�ɤ�������
�ݥ����ߤ�ޤ������ĤޤǤ⳰��������������Ȼפ��ʡ�
�֤ݤ���������
�ּ�����뤾��Υ��ơ���Υ�����
�������̤���ä������ޤ���ϤϤɤ��ƤⲶ�οͷ��Ǥ��롣
��ƨ�����ä�...�����ޤ��Ƥ⡽�������
���ڤ����Ǥ����ͷ�����ʬ�������Ϥ��ʥ��ڡ��������ä���
���¤äƤ���ˤϤʤ�����֤˳������褦�ˡ��������ͤù��ࡣ
�������Ϥޤ줽���ˤʤä������Ȥä��˾��Τ�ʢ�˴�������Ǥ�����ʤ���
����ž��̣�ǡ�ȴ���Ф������Τޤ�ž����ʤ��顢�Τ��������ष����ƨ���ơ������դ��Ƥ��Ƥ��ʤ����Ȥ˵��Ť��Ƥ��鿶���֤ä���
�֤ʡ��𤱤ͤ���
�֤��䡢����Ǥ��������Τ������ǿͤˤ�Ȥ��Ƥ��ڤФʤ����Τ�����ζ��ݤ��ܤ����ˡ��Τ�ư�������Ȥ������ʤ������ΰ��̿ͤ���
���������ȥϥХ������³���롣
�֤��������Ȥ��Ƥϰ�ή�οʹ֤����ʤ��ФȤ����廊�Ф�����
�֤ȡ��ФȤ��ơ���
���ɤ��Ǥ⤤�����ɡ��ͷ������Τܾۤ�ˤ���ϥХ���������ϤȤƤ����Ƥ�ʹ�����Ƥ��롣�ޤ�ǡ����Ǥ��٤��äƤ���Ƥ��뤫�Τ褦����
���������ͷ��Ϥȸ����ȡ�����⤤�Ƥ���ϥХ�����Ȥ���Ȥ����ȷ����äƤ��롣
���ƻ���¸�ߤ����ɤ��ʤ��ä��褦���ʡ�®���Ϥ���ʤ�������ͤϥ�����¤���
�����������ĤĤ⡢�ͷ����ꤲ���������ܤǶ��ߡ������ߤ�롣
������ľ���ơ��ڤ����뤦��
�ָ����ܤ�������������ɤ�������ɳ�ޤǹ�����...�����⤳����ĤǤ���ʡ�
�����ʤ��������ꤲ�ΤƤ롣
���Ĥ�Ǥ���Τϡ����ä������Ǥä����������������ǥ������Τ�����˺�줫���Ƥ��뤬������к�Ϲ����ϥ�ޡ��Dzù��Ǥ��ʤ��ۤɤ˹Ť���
�֤Ƥ����ʤ�ǥϥХ�����Υ��ԡ������ʤ���Ǥ�����
�ֿʹ֤�ǧ����ʤ��ä��Τ����������٤ʤ��Ȥ���
�����⤬ݵƫ�����ʤä��Τ��������˹��٤�夲�Ƥ�����
�ְ�ư���ʤ���Ǥ�������
�ְ�ư�Ǥ��ʤ��Τ����ʡ�
��ò©���줿��
���ϥХ�����ϡ��ޤ�Ǥ������ɤ����뤫�Τ褦�ˡ�����˼�����Ӥ碌�롣
���Ҥ���Τ����ä���
������������ϥХ��������Υ����ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ���Τ���
�֤���������ɽ���㤤��Ǥ��͡�
���ϥХ�����ϡ��褦�䤯��ä��Τ��Ȥ���ɽ��Ǥ��������������
���������褿�Ȥ����Τ���Υƥ�ݡ��ȤȤ�������ˡ����������
�֤��ɡ�����ʤ��ä�����äƤ������ɤ��ä��Τˡ�����ʤ��Ȥ������ʤ顢���˸��ӿ��٤���Ȥ���
�֤����̥��Ū���ä����ʡ���ǰ�������濴���Τ��ϲ��ؤ����뤳�Ȥ��Τä��ΤϤĤ����ä������������
���ɤ�ɤ�Ⱦ�˾夬�äƤ�����
��ɸŪ���Ѥ�ä�����ȸ��äơ����Ǥ������ǤϤʤ�������
�����Ť��С��ͷ������ι��⤬�ߤ�Ǥ�����
�����⤬�Ϥ��ʤ��ȸ�ä��Τ�������
���Ȥʤ�С���������������Τϡ���
�֤Ǥϻ�Ƴ��Ϥ�褦���ҥ奦����
�֤ϡ��Ϥ���
�֤Ȥꤢ���������ν��Ĥ��濴�����ӹ����
�֤��������á�������
�� | | |
|
��2006ǯ10��18��(Wed)��
�����Υ����ȥ��Ǻ��
|
Replay
 �ҥ奦�����ΤĤ��ǽޤ�����������Υ֥롼�ʤ⤷����RPG�Υ֥롼Ū�����ˤߤ������� �ҥ奦�����ΤĤ��ǽޤ�����������Υ֥롼�ʤ⤷����RPG�Υ֥롼Ū�����ˤߤ�������
�֥롼�ϼ���Υ��顼����ͤ��Ǥ��ʡ�
�ɽ�
�֥Хå�����!1934�����ԡ�Alice In Jails ������ �ɸ�
�֥��Τ�ι��10��the Beautiful World ������ �ð�
��ϵ�ȹ������3�ӡ��� �ຽ
��A����ˡ�إ�ץ쥤�֥å�~��������ˡ����~��¼͵��/����ե��������ƥ�
�֥ɥ��CD�����������ϣ�� 2�ס��·� ����
�ֽ�������ʪ�� 8�� ��¼ �ȥ�ҥ�
�Хå����ΤϰƤ���岼���ξ���ä��Τǡ������Ȥ��Ƥ��ޤ���
�Хå����Τξ岼���äơ�Ʊ����˵��������Ȥ�����ʬ���Ƥȸ�����§Ū����ˡ���Ѥ����뤫�顢�崬�����ɤ���Ȥ��Τ���䤬�Ǥ�����
����ϣ��Υɥ��CD�ϥݥ��ȥ����ɤ��տȤν���Ǥ������������͵��Ҥ�����ɤ��ʤ����������ڤ�......ʢ�����ʤ�...
�ޤ�ơ��֤Ȥ��ءפȡ֥ޥ긫�ơפκǿ�����ڤ��ɤߡ�
�Ȥ��ؤϥ����Ϣ�ܤ��뤽�����ɤ������Ǥ���
�Ҥ��餷�Ϸ���ɤޤʤ��ä��ʤ�...�Ȥä����꤬���Ĥ���ʤ������β������ɤ�Ф����Τ�������
����κǽ��ä����ɤ�Ǥߤ褦���ʡ�
����ȸ����к���ν������ΤϤ褫�ä��������ƥ٥����ä��������ȥ뤫�餷�ơ֥ɥ饴�����ȡף����������줬������
��塼���������ʤ꾮�Խ��Ф��Ƥޤ����ͤ���
�������⤹�ä���ǥե���������...���줵��餫��
8�����ɤ��ä��Ǥ������ޥ��ڡ��������ʤ���ä��Τ����Ȼ�ǰ��
| | |
|
��2006ǯ10��16��(Mon)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
����ȱ�����ܡ��ջ֤϶��������������������������Ȥ��Ȥ�ʤäƤʤ������ʡ��������̣��Ʒ��
�֤äơ�������������äѤ����ޤ��衢�ϥХ�����
�֥������Ȥ�����ʣ�������ͷ��������ԡ���������ȿ�����ơ������ԤλѤ����魯��¤��ˤʤäƤ��롣̵����������궯����
��ʣ���ʤΤˤá�����
�ֶ�ν��ơ����ޤ����褦�������°�������ˤ������������ޤ�Ƥ��롣�Ȥϸ�������������°���Τ�ʤ��ä���...�ޤ���ñ����������ٶ����ʤäƤ�ȹͤ���Ф�����
��...�Ĥޤꡢ�ɤ����äƤ���Ԥ�궯���ʤ�ä���ˡ�ʤ�Ǥ��͡�
���ܤ����ˤ����줿���ʡߤ��äѤ��ˤϡ����ͤ����Ȥ����㳰������ͤ��äƤ��롣����ư��ϰ��ͤ˵���Ū�ǡ��ʹ֤餷����̵����
���濴���褿�Ȥ����Ǻ�ư���륷���ƥ�ʤΤ���������������360�����Ƥ������˲����錄��
�֤���������ϡ�����
��ή�Ф���¤�ʤߤ������ʡ�
���⤫����˹���ݤ��ơ����Τޤ�ŷ��ؤȾ夬�äƤ����ϥХ�����
��16�Τ���16�����γ��ɤ˳�Ǽ����Ƥ����ߤ������ʡ�
�֤ߤ�������...�äơ����硢�ϥХ������ͤ������뤤�ä��衪��
�ֲ���������
�ֲ������äơ�
�������������ޤޥϥХ����ҤͤƤ��롣
�ֽ����Ƥ��������衪�������Τޤޤ��ȡ��ɤ��ʤ��Ǥ����ääơ�¿ʬ��������㤦��Ǥ��礦���ɤá������Ƥ��������衪����
�������������ˤ��ĤĤ⡢�ҥ奦����ɬ����ʤ�����
������褯�������ˤ���褦��̿����ꤵ��Ƥ����Ȥ��Ƥ⡢�����ǺѤ�Ȥϻפ��ʤ����Ȥ������ġ��ʤ��̤ȸ��äƤ������Ȥ�����
�ּ����äƤ��ɤ�������֤ǽ���뤾���椫�餹��С������ζ��������ܤˤʤ�����0�˿�����ݤ�³����褦�ʤ�Τ�����ʡ�
�֤Ҥɤá�������֤ǽ���äƤ�Ĥޤ�ʤ��Ƥ��ɤ��Ǥ����顢�����Ƥ����������
�����ä�����Ȥ�����ϥХ�����ˡ��ץ饤�ɤ�ʤ����ꤹ�롣
����Ȥ����Ʈ�˴ؤ��Ƥ��糰���ʤΤ����Ĥޤ�̰��Ϥ�ĥ��ɬ�פ�ʤ���
�֤ޤ������������������ʤ����̤˹���̤��ʡ�
�����ʡ��Ȥ����ĤĥϥХ�������⤫�־�ξ�����ơ�Ω���夬�롣
�������ơ���˾�ä��ޤޡ�����ʢ���פä�����������γ���벻��
�֤�������Ϸ�����ܤ��ǤĤȤϡ�ͧ�ͤ�����ˤ��֤���ʡ��ѡ��漫���襤���������Ƥ�����ȻװԤ����ȸ����ˡ�
�֤�...��
�ֺ����ιϩ������ƴ��äη������餤�ϳФ��Ƥ����������ʤˤ��������������ˡ��ޤ��������dzڤ���ι��ǻ�̤ۤɶ�ϫ����Τ�춽����������ޤ�����θ��Ԥ��֡��Ȥ������ʤɡ��¤α�ͺ�ȤƳ��̰ڤ�¿�����ȤΤ����ʡ��������Τʤ���
�֤���������...�Ƥ����ʤ�ǥϥХ�����ι����ä��ΤäƤ��Ǥ�������
���������ˡ��ϥХ�������פ����Ʋ��ˤ��餷����Ĺ����οϤ��Ť������������äƤ��롣�ˤ䤫�ʥ����֤�������ȤΤ��������Ϥ��ʤ�������������������Ƥ��롣���Ⱦ�������С���Ȥ���������̤�������������
�������ơ������ХϥХ�����ϡ������Ƚ����⤰�餤�ޤǤ����äƤ��벶��ʣ����������Ƥ��ޤ��˰㤤�ʤ���
�֤������ɤ����롣�����ǻ�̻פ��ƶ�����������������Ȥ⡢��
�֤䡢���ޤ��衪���廊�Ф�����Ǥ��礦������
��Ⱦ�Х䥱�ˤʤäơ��ҥ奦���϶�����Τ��ä���
��
��
| | |
|
��2006ǯ10��15��(Sun)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
������Ȥ����Τ�����ϼ��ΤΤʤ��ͳʤ�ؤ���������Ǥ��ʪ�ˤȤ�Ĥ������Ĥ��γʤ���ͤ���ʪ�Τ��Ф��Ƥξ�ħ�����ʹ�Ū����������ӿ��ȸƤ֡�
���������ˤ�����������ɤ�С�����������������ӿ��������ǥ������Τ褦����Ȥϲ��δط���̵������ɤäƤ�����Ϥ�����������������դ���̤��뤿�ᡢ�桹�����ӿ��Ȥ����ƾΤ���ˤ��롣
��;�̤��������Ȥ��������Τ���Ĥ��Ȥ��Ų��Ѳ����뤤�ϵ��Ͳ��ȸ��������ˤ��οͳʤ������ʤξ���̾�Τθ����ˡ�������դ����
�֤��䤢�Ρ���ʤ��ȸ����Ƥ���ޤ������Ȥ������椫�鱳�Ǥ��礦��
���褯�狼�ä��ʡ��ȥϥХ�����ϰ��Ӥ�⤻���ˤ��������Τ��ä���
�֤�����ˡ�ؤϡ�����п����ӿ���¤���֤���
�ֿ���������
�֤������Τ�ʤ���������������ΤäƤ��롣��������ӿ��Ȥ����Τ���ͤ��������ǽ���㤤�����դ�Ф����ƤλҶ����٤���
�������������Τ褦���¹Ԥ������äν�����볦���Ĵ�δ������ݻ��ʤ�Ʒ����Ϥޤ��Բ�ǽ����ñ�̤ǻ���Ф�ʪ�ʤ����ӿ��ʤ�⤷�����������뤫�⤷����ȤƤ�졻��;ǯ���٤���¸�ߤ��Ƥ��ʤ���������ϤǤϤʤ���
���Τ��ˡ��ϥХ�����θ������Ȥ��������Τʤ�ġ��ʤϤ������ʤ��ۤɶ��Ϥ��Ϥ���ä�����ȸ������Ȥˤʤ롣��ǽ��������ľ�����̤ꤸ��ʤ����Ȥ�פä�����
�������¤����ˤϣġ��ʤϿ���ǯ������ǡȯ�������餷����
���������ɤä����Ρ��������������ˤʤä��餷�������ġ����ܿͤΤ��ä��餫��Ȥ������ʤ椨�������ä�����δ�������Ȥ��Ƥ��ϰ̤��Ω���Ƥ��������ĤΤޤˤ����롼���Ϥ����̵�ռ��ȸƤ�Ǥ�����...
�֥롼���θ��ϡ����Ĥ䱽�äˤ�ä����ȯ��������Τ��Ȥ���äƤ���Τ��������Τ��ˡ�����������θ��Ϥ��鸫��С�¸�ߤγ�Ω�Ϥ���Τ˿ͳʤΰ����������Ǥ����ꤦ�롣������ˡ�ؤ⡢�������ä��͡���̵�ռ��Ǥθ����ǰ�Ȥ��Ƥ���褦�������ʤ����ְ㤤�ǤϤʤ���
�֤��䡢����˹ͤ��Ƥ뤳���ɤޤʤ��Ǥ��������äƸ����������ä�������äƤޤ����ɲ�����������
�֥ҥ奦���Ȥ���̾�Τ��ҥ奦�������ȥ�֥ꥯ�������������θĿͤ��Ƥ�������������˸����С���˽��ߡ�������Ѥ����äΤĤʤ����夿�������λФ˥����٥���Ȥ��������������ȱ���ܤξ�ǯ�Ȥ�ʤ�С��������ˤ����ʳ���¸�ߤϵ�ʤ����Ȥ�������
�֤���㡢�����餢�äƤߤ������Ǥ����ɡ�
���ϥХ�����˾�ǯ�ȸ�����ȡ����Ȥ��ԻĤʵ�ʬ�ˤʤ롣
�������ܤϥҥ奦������äȾ�ǯ�ʤΤ��������Τ������Ƥ������Բ��˻פ�ʤ����ष���̱Ǥ椤��
���ޤ������������ʤȥϥХ�����Ͼ������줤����
�֤����Ʊ�ͤˡ���¿���οʹ֤����������������ȸ�����ǰ����������¸�ߤؤȲ������֡������������Ȥ���
�֤��䡢Ʊ�ͤäƤ����Ƥ⡣���ˤ������Ƥ狼��ͤ���Ǥ�����
���ϥХ�����ϡ���ʬ�μ���ˤ�����������Ƥ����Τ�����������������ͤˤ��������ʤ���������ľ10ʬ��1�������ɤ��Ĥ��ʤ���
���ҥ奦���Ƚ��ƽв�ä��Ȥ����餺�äȤ������ä���
���ʤ��������������
���������������äƤ���ǤϤʤ��ä���
���ä������ʤ�Ǥ��ʤ�����
�֤����ȡ��Ĥޤꥳ������ˡ�ؤȡ���ã����˻��äƤ륤����ߤ����ʤΤ���蘆�äơ���������ӿ��ȤϤҤ�̣�㤦�ġ��ʤ������줿���äƤ���...���ʤ���
����ɲ�������顣
���ϥХ�����ϡ���ʬ�ο�¬��ʹ���ʤ��������˸���ü��ʤ��Ƥ�����
�ֽ���ʹ���ư�˷�֤��ʡ�
�֤���˫��Ƥޤ����͡�
���ܤ䤯�����ҥ奦���Ȥ��Ƥϡ֣ġ��ʤ�����Ū��¤��줿�� �ȸ������¤����Ǥ⤦ʢ�����äѤ����ä���
�֡�����ˡ�ء��Ǥ��������줬���ߤȤ��Ƥ���äƤ��Ȥϡ��ǽ餫������߷��ۤˣġ��ʤ����ä��Ƥ��ȤǤ���͡�
�ֶä���������
�֤������ष��祤�������äƸ�����...��
�����������鴶���Ƥ����֣ġ��ʤäơ��볦����Ĵ��饨��١�������顢����ȯ����������ˤ��Ƥϡ��䤿�餤�������������Ƥ��ʤ��� �ȸ�������⤽��ʤ�Ǽ���ιԤ����ȤǤϤ��롣
�֤Ȥ��������դˤʤ�Ǻ��ޤǤ����������˹ͤ��ʤ��ä��Τ��Ȥ��פä��㤤�ޤ��ͤ���
�����ޤ���˿����֤�ޤǤ�ʤ����ġ��ʤ�¸��̵�������������Ω���ʤ���ʬ��¿�����ä����ʤ顢�ġ��ʤ�ǽ餫������߷פȤ��ƺߤä��ȹͤ���Τ����̤ʤΤ���
�֤���Ϥ������֤��⤤���֤ˤ��뤫�����������ȯ��������������Ρ���ȯŪ�ʻ�ʪ���������οʹ֤����㤤�����Τ�����⡢���Ƥ��̤ꤳ��������Ķ�������Τ褦�����տ�Ū�˵����Ĥˤ�ä���ƿ������褿�Τ�������
���ȡ��ϥХ������ܤ��Ĥ�����
�������Ʋ��������줤�����Ȼפ��ȡ�����äƤ���Ĺ��ϥХ�����Υ��ƤҤȤ�Ǥ��⤫�Ӿ夬�롣
���ä��ҥ奦����;��ˡ��ϥХ�������⤫����ξ�˹��ݤ���
��Ĺ�ä�����ʡ�����뤾��
�֤����� �ȸ����ĤĤ�¤Ϥ��ä����顢���ʤ����դ�ˤ������ȷ��ʴ������դ�Ż�äƤ���Τ���
�ֲ����ϥХ�����äĤ��Ƥ��줿��Τ��ȤФä����
�֤ϡ�����Ϥ��Թ������ʡ�
��ɡ�ǾФ��ϥХ�����
�������������Ȥ餷���ä���
����ˡ�ؤ��Ĥ��������������Ѽ����Ƥ�����
�����䡢��ȸ������ϳ����������ȸ������⤽��ϡ��俧�θ�����
�֤դڥ���С��֥�åɡ� ���ܤ���ѤǤϤ��뤬�������ͦ��Ϣ�椬ʹ�������Ϸ�������ͤ�ʡ�
��ͦ����ï�Ǥ��������졩���äƤ�������ʤ��äѤ��褿��������
| | |
|
��2006ǯ10��14��(Sat)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
����夬����¤���ФƤ����Τ�...
�֤��
���Ȥξ滰�ܤϤ��뤫�Ȥ���Ĺ���Ȥ�����ǯ���ä���
�֤äƥϥХ����������
���ɤϡ���©���Ǥ���
��Ω���ʤ��顢������������ܤΤ褦�ʽ�ʪ���ɤ�Ǥ����ϥХ�����ϸ�����夲����
�ֿͤ�ʤꤿ��©�Ǥ��Ȥϡ������֤���ʡ�
�֤��䡢�����ǥ�����Ȥ��ȹ����Ƥ���������ˤ������������̤�Ȥ��ʤ���30ʬ�⤷�ʤ��ǺƳ��ġ��Τ⡢�ʤ�...��
�������ޤǸ��äơ��դȤ��뤳�Ȥ˵��Ť���
�֥����ǥ�����...���������������Ǿ�������ƥ������ƥफ������ʤ顢��
�֤��䤽���ꡢ�ϥХ��������ˤϤɤ���äơ����Τ������Dz��ˤϹߤ���ʤ��ä�...��
�֤������ʡ�
�ּ������ä���������
���̤˾ä��ƤϤ��ʤ���
���ޤ�����������Τ褦�ˤ��������ϥХ�����
��;��ˤ������Τ褦�˸����Τǡ��ҥ奦���ϼ�ʬ�ιͤ��������ְ�äƤ���Τ����¤ˤʤä���
�֤������Ρ�������ϥХ�����äƼ��������ŷ�դΤ���äȾ夰�餤�ޤǤ���...��
�֤���������������ε�����Ƥ���Τ����ҥ奦���������ϲ��μ������Ф�������˴��㤤�����Ƥ���褦�����⤦���ٻפ��Ф�����ʡ�
�ִ��㤤�� ��ʹ���Ƥ⡢�ϥХ�����Ϥ���ʾ�������Ƥ��줽���ˤʤ���
���������Ƽ�����Ѥ��롣
�֣ġ��ʤ��������ǥ�����˾��ƤäƸ��ä���Ǥ����ɤɤ��������ȤǤ��礦������ˤ�����������ɤʤ�ʤ����...��
������夬�ä���¤�ľ��2���ۤɤαߤ��ä���
�����줬ɨ�夰�餤�ˤޤǾ夬�äƤ��Ƥ��ơ����ξ�˥ϥХ������롣
����ۤɤ�����夬�������餷�ơ������ؤˤ������Ȥˤʤ�Τ�����������ϰ��β��Ƥ����Τ�������
�֥����ǥ�����˾��ơ������������ӿ��������ˤ������ä��Τ�����
�֤���ʹ����������������Ǥ�����...���������ʹ�����ʤ��ʤäơ�
�֤ޤ����������������ʡ����褽ǰư�ϲ�ϩ�ȸ�����ĤϤ���Ⱦ�¤�����ˤʤ�ۤɡ��礬����ʡ������Ū�ˤȸ�����̣�Ǥ��������Ѥ�Ԥ����Ȥ�����롣�߷ޤ��Ȥ���������뤬�������̤����Τޤ�ʣ������ȿ�Ǥ����Ȥ������ǤϿ�����ץ������˶ᤤ��������ñ��˽�ʪŪ�ȸ��äƤ⤤��...��
���ޤ������ȺѤޤ��ơ������ʤ����������롣
���ɤ��ĥå���Ф����Τ�Ǻ�ߤĤĤ⡢�ҥ奦���Ϥ����������֤��������ϲ����� �ȸ���������Ф�������ʤΤ��ȵ��Ť���
�֤ϡ��ϥХ�������ä��ԤäƤá�
��̵������ϩ�����ʣ��¿�ͤ����������줿�������Ѥ��뤳�ȤǽѼ��ΰ��̤�ޤ뤳�ȤϽ���뤬��������δ�������ξ����ڤӲ����ݻ��Ȥʤ�ȡ��ɤ����Ƥ����˽�Ϥˤ������Ǥ��������Ѥ�����ʬ��ɬ�פˤʤäƤ��롣�ºݡ����λ����Ф��Ѥ���������������ˡ�ؤˤ��Ƥ⡢�濴���ο��Ԥ�����Ф��Ȥ�Ʊ����ʸ�η����֤��ʤΤ�������
�֤������������ԤäƤ���äơ�����������ȸ����Ƥ��������ʤ��äƸ������������Τꤿ���Τϻ��ȤߤȤ�����ʤ��ơ�����������������ˡ�ؤäƤΤ��ɤ�������Τ��äƻ���...��
����ʬ����������äƤ뤳�Ȥ˵��Ť����Τϡ����줫��3�ø���ä�����
| | |
|
��2006ǯ10��13��(Fri)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
�֤ʤ��������
�������ϡ�������ޤ줿�����������������ä���
�����䡢��ΰ쳬�ؤǤ��뤳�Ȥϲ�äƤ���Τ�����
�ֶ��äݤ�...�����������ޤ뤴��...��
������١����������Ф�ȡ������ˤ����äԤ������֤��Ȥ��äƤ�����
������ʤ����줹��ʤ���
��������ɤ������ä�ξ�����鿭�Ӥơ��ߤ�ʤ���褦�˱��ؤ�³���Ƥ��롣
�����ޤ�ˤ���������ܱߡ�
�����줬�����Ф��Τ����ɤ��˳Ȥ��äƤ�����
�������դ�Ĥ���
�����ޤ�ˤ�����Ƥ��ι����������������Τ���
����Ȥ����ĺ����֤���餷�Ƥ���ҥ奦���ˤȤäơ����ΡȲ���ʤ��ɹ����϶������礭����������
�֤�櫓�狼��ͤ��������դȤʤ�ȿ�ʬ�Τ��ФλŻ���������...���Ȥ��Ƥ⤳������������ʤ顢�Ф��Τ�ʤ��Ϥ��ͤ��Τˡ�
���ʤΤˡ����ˤ�������������ޤ줿���������ܤ����ˤ��롣
�ֲ��������Ĥ�...��������������...�����äƤ䤬���
�����θ������Τϡ�����Ŷ����ޤ줿ȯ�����뾲�Ĥ��ä���
�����դ�����Ĺ�����٤���������ȯ���������ġ�����ȡ��ɤ��ˤǤ�Ȥ��Ƥ������̤ξ��ĤȤǾ��̤���ʬ���Ƥ��롣
����Ψ�Ȥ��Ƥ���Υѥͥ����������Ū�˾��ʤ���
���ѥͥ�ϡ��ɤ�������Τ褦�˽IJ�̵�Ԥ˾��̤����äƤ���褦���ä���
�����Υ饤���������������⤵�ϣ����Ϥ������������
�֤�ä����ͤ�...����ۤɤξ��ʤ顢�サ���֤ʤ걿ư���ߤʤ�...���ͤϤʤ���äƤ�����߷פ��
�إߡ��ʤ餳����Ĥ������ǽ��ߤ����ʤ����ɤͤ����ɤä������ξ����ΤäƤ�Τϡ��ߡ��ȥ�����������������١�������...�����ˤ㤢�Ȥޤ�ʤ����
��ʹ���ĤĤ⡢�ҥ奦���Ϥɤ�ɤ���濴�ؤ��⤤�Ƥ������ۤ����������Ե�̣����Ф����Τϻ��¤������ФȤ��Ƥι�������˾��ä��Τ���
�����ܡ�Ϳ����줿�ѥ���Υѡ��Ĥ��Ȥ�Ω�Ƥ�������п�����������Ǥ����Ĥ��ɤ�ʥѥ�����Ȥ߾夲���Τ��ˤ϶�̣���Ԥ��ʤ���
�֤����Ĥ���...�ϥХ��������ˡ�˻��Ƥ�ʡ�
�������㤦����ʪ���줫�餳���Ф�褦��ø�������������ब��Ѥ���Ѥ���ݤ˸������֤����ˤ��ä�����ä���
�ְ���Ū�ˡ��ɤ����γ��ؤΥץ졼�Ȥβ��ʤ�������ʡ��������Υ��ͤ���ȡ���۳��β�������ε������뤱�ɡ��ʤ����ġ���...�ġ��ʡ���
��...����������衣����ˤ��äȤ����ɡ����ξ��ĤϺ��ʥ��
�֤�����͡����ɤ���
���ɤΤߤ������γ��ؤ���Ƥ���ҥ奦���ϥ��줬�����ʤ��ʤäƤ��롣
���ǥ������ˤ��������ޤǴ����Ƥ����Ϥε��ۡ�������в��Ǥ�¤��ȸ����ο�������Фᤤ�����ۤ�̵���ʤäƤ�����
�֤Ȥ����ǡ�����äƲ�������ʤ������
�ؤʤ�Τ��ä����
�֤��ä���ʹ������������ɤʡ��äƤ����ɤ����������餤��Ⱦʬ�����ɡ��������ä��Τ��������ʤ����������
���ġ��ʤ���Τɤ��ˤǤ�¸�ߤ��롣�����顢�������Ʋ��ä��Ƥ���֤ˤ⡢����ͶƳ����ν������¹Ԥ��ƹԤäƤ���Ȧ�Ǥ��ä���
������Ǥ�������ˤϡ���ɴ�����٤ʤ�Ʊ���˲��äƤΤ����¹Խ���ǽ�Ϥ����롣����ʾ��������������ҥ奦����ͤ˷ڸ���á��;͵�Ͻ���ʬ�ˤ���Ϥ��ʤΤ���
�����������Ŭ�������Ȥ����Ǥ��ʤ��ȸ������Ȥϡ���ۤ�¾��˻�����ʤä��ȸ������ȤǤ��롣�ҥ奦�����פ鷺�Ҥͤ�Τ�̵���Ϥʤ���
�ؤ��䡢���Υ������⤬�͡��Ф����Ƥ�Τ����ޤä�������ä����ͤ���
�������ˤ��ɤ������������Ǥ��롣
���ȿ��ꤹ���Τ�ʤ��Τˡ��ɤ��������С��ꥢ��������פ碌�롣
������ʤ��Ĥ�Σġ��ʤΥϥåԡ��ܥ�����
�������������������ɤ������ʤ���
����Ϥ꾯�����ͻҤ��ä������ҥ奦���Ϥ�����ⵤ�˳ݤ��뤳�Ȥ����ä���
���Ф����Ƥ�äơ������Ф����Ȥ�����
�ؤ���ȡ������Ĥ�����֤��ä��Τ�ޤ���������衣�������ή���Ʊ��路�Ƥ�ͥ���
�֤ʤ���äƥ�������������ʤ�
�ؤ���ޤ������ä��ϵ��ˤ��ʤ��Ƥ����衣���ץ��쥹�ߤ����ʥ������������굤��Ĥ��ʡ������ˤϡ��ޤۡ�...���...�륬���ǥ�����......��
�֤ϡ��������ġ��ʡ��Ǥ���������������
�������ʤ������ɤ�ɤ�ȱ���Ϥ���롣
�������ԵȤʸ��դ�ʹ�����������ơ��ҥ奦���ϲ��٤���������̾����Ƥ����
��...�奦�������ʤ龡�Ƥ롣�äƤ������ơ������ʤ����̡��狼�ä���...��
�֤äƤ����äääá����������ʤꥯ�ꥢ���ˤʤä��Ȼפä������㥯���㶲������ȯ�����Ƥ뤷����
��...�ơ�......����...��
�֣ġ���...����
��ȿ�����ʤ���
���⤦���������ǡ֣ġ��ʡ��� �Ƥ�Ǥߤ�������ŷ��Ⱦ��˵�����ȿ�����롣
������ȿ�����ޤ��ɤ��ˤ⿴�٤���
�����露��ȡ����α���ˤޤ��ż䤬�����Ƥ��롣
�����Ϥ��Ƥ�̤Ƥ������ʤ�����ʹ��֤��Ȥ����Τˡ��ޤ�ǥ������åȤ˲������ޤ줿���Τ褦�˵���˻פ��롣
���Ȥ��������������꤬�ˤ����Τ餺�ǥ����������Ϥ����äƤ����Τ���
���ġ��ʤ�����̵�ռ��˻פ��Ф����Ȥ��ơ��Ĥ����ä�ʹ��������ʸ��դޤǤĤ��Ǥ˻פ��Ф��Ƥ��ޤä���
���ֿ�
���������������濴�ξ������꤫�鲿��������夬�ä��褿��
| | |
|
��2006ǯ10��09��(Mon)��
�����λ�
|
Replay
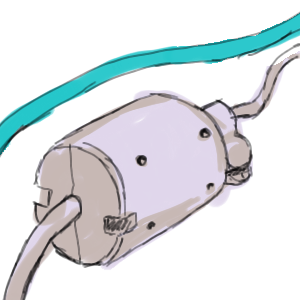 | �ʤ�̵��϶�äƥѥ�������ŵ������֥�ˤĤ��Ƥ뤳��˻��Ƥޤ��͡�
�����λ�
ɽ�椬���ꥮ�ꤹ�����
�����Ϥ���ä���̯�Ǥ�����
�����ɤ��ä�ʬ���äˡ�
����ή�Υ����ǥ��Ϥ����äȻפ��ޤ���������Ǽ����ߤ�륷����Ͼ��������������褦�ʡ����ι��ޤ�������̵������Ǽ��������줿�����Ǥ���
�⤦��������ή����äƤ���ޤǤ�ή�줬���ࡼ���ǡ������Ϥ�������ɤ��ä����⡣
�ڤ줿�뤬�طʤ˰��٤�ФƤʤ�����ޥ��ʥ��Ǥ�����
���ꥰ��ư�����ޤ䡢�Ի�������������ä��Ǥ���
�Ǽ��Ĥ˥���Х����罸���Ƥ����ݸ��ι��𤬤��ä��ꤷ���Τ����ʤ����ä��� | | |
|
��2006ǯ10��08��(Sun)��
���Ĥभ�Ф������ˤ������ް�γ
| |
| |
|
��2006ǯ10��06��(Fri)��
��������dz���Ƥ���
|
 | �������ʤ���ˤ����äƤ���Τϥѡ��饤�Ȥȥ���ʿ��ե����ˤǤ���
�����Υ饤�Ȥ���̿�ˤ��դ��Ƥʤ���ǡ���갷���˿��Ť��פ��ޤ��äƤ���ʥͥ�ï���������
�������Ǯ�ˤ�뿧������Ҥɤ����ˤ��㤤ľ���ޤ���
������ϡʱ�����Ǥ���TakeBack's�ˤ����ơ˰������ͤƤ��ޤ���
�������ϸ�������ê�ˤ�������α������ã������ʤ���������������������Ѥ��ޤ����ѡ��ƥ������å�����ä���⤷�ޤ���
�������ʤߤ��ΡˤǤ������饸�����Ͻ������ޤ��������ߤϣͣĤǤ����ʤ����⤦�Ť������ΤϤ�äѤ�饸�����Ǥ�������ϩ������ʤɤΥ���ݤ������դ����ʤ����⤳����Ѥ��ޤ���
�������åȤ�10ʬ���٤ΰ�ʪ���Ѥ������ڡ����̲���Ĥ��Ф��ƥ����åȰ�Ļ��Ѥ�dz��ΰ����Ѥ����ޤ�����������ϥ����åȤ����ä��ܥå�������Ĥ⻰�Ĥ������Ƥ��ޤ�����
���ޤ��������åȤȤ����ۤϺǽ�ο��ä�̵���Ǥ��뤿�ᡢ�������äƤƤ����˲����Ф�褦�ˤ���Ƭ�Ф��Ȥ�����Ȥޤ������������������ƳΤ���Ƥ⤤���ΤǤ������и��Ԥϼ����ơ��פ��ѿ����Ǹ��ˤ�Ƥ��ޤ�����
�����ʤ����ɮ�ǥ����åȤλ��֤�櫓�Ǥ��ʡ�
�����̲����������ǹ����������̲�����õ�ä����ȡ��ʤ���Х�뤷�ޤ���
�����̲��������̤˥ĥ�����֤��Ƥޤ�������ϡ�����ޤꤷ�ʤ��ä��ʤ���
���£ǣͤ����Υ��Ĥ�Ŭ�����֤��Ƥ��ä��ãĤ�Ȥ��ޤ���ê���ǥ�������ޤäƤ���֤䤫�ʷ�������ȥǥ����ʣ£ǣͤˤʤ�ޤ�����
��������ڤӥɥ�ޤΥ���ȥ����ϻȤ�ʤ�����̵��Ǥ��礦��
���Ҥ�������ΤäƤ�����硢���ͥ������ˤʤäƷ�˽��椷�Ƥ���ޤ���
����ƻ��ʤ��������ˡ�Ω�ƴ��ĺ��ʤɤξ����������ͤޤ�����ƻ��ʤɤϡ��ޤ�ͽ���ȿͤȤ��襤�Ǥ���
�����ʤɤϤ���ޤ�Ȥ��ޤ��ꥢ��ƥ������ɵ᤻�����褯���ʤ�Ȣ����ʪ�Τ䡢�����餢��������ʺ��ʤɤ��Ѥ��ƹ��ߤ˲Ͷ��ζ��֤���夲��Τ�����Ū�ʤ褦�Ǥ���
���ޤꤿ���ߴ��ǥ���Ȥ�ͤ����ޤ���������ʴ����Ǥ��͡�
���繩�Ż��⤷�ޤ������嵭���ͤ���ͳ����¤�ä��Ȥ��Ƥ�Ȣ�Ȥ����Ȥ����ʤȤ�����Ǥ���
���ޤ����ޤꤿ���ߴ������ʤɤ�ڤꤿ��⤷�ޤ���
�����λŻ����äƤ���ȡ����祴�ߤ����λ��˸����Ƥ��ޤ���
����ƻ��ʤ����ˡ��ᥤ����ô�����Ƥ��ޤ�����ƻ��ϡ��ޤ����Ӥ˱����ơ���ʪ�ˤ��뤫��ʪ��Ȥ�����༡��Ǥ��礦�������Τ�������ͤޤ��Ф��뤳�Ȥʤ��Ż��Ǥ�������ƻ��δ��������ѤǤ���
��������äƤ⤢�ޤ긫���ʤ���ʬ�Ǥ⤢��ޤ���
�����λŻ����äƤ���ȡ��ꥵ�����륷��åפ��ʰʲ�Ʊʸ��
���ᥤ���Ϥޤ����ɡ����δ����Ȥ���
�����ˤ˥ᥤ�����������ꤷ�ޤ���
����������ʤ��ꤵ�ˡ����ġ���Ф��ͤޤ�����ʬ�����ܤ�ʬ����Ф���Ȥ����Τϡ��츫����Ū�ʵ��⤷�ޤ�����ȿ�̡�ɽ���˴ؤ�����Ƥ��ͤ������餦����˻���ζ���������ޤ�Ȥ�����Τˤʤ�ޤ������礻���ͤǹͤ��뤳�Ȥˤϸ³�������ΤǤ�����ͤ�����ͤ��褤�ȸ����Τ⤢�ä��ǤϤʤ�����
��
���ȸ����櫓�ǡ��ס���TakeBack's�ͥ��Ǥ����� | | |
|
��2006ǯ10��05��(Thu)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
���������ʤ�ʤ��顢�����٥�����������������ä��路����
���Ϥ��ᡢ�����٥������ʬ�������ä��Ƥ��뤳�Ȥ˶ä��Ƥ����Τ�����ľ��ʹ���Ƥ��뤳�ȤϤʤ��ä���
�����ä��Ȥ��ˤϡ��椬���Τ褦���ᤷ��Ǥ��줿�����ˡ��ۤäƤ������Ȥ˿������ʤ������Ƥ����Τ�����
�ֶä��Ϥ���������
��Ⲥ�������������������ࡣ��ϡ�
��...�ޤ����Τ���ʤˤ������Ƥ�ȤϻפäƤ������ʡ�����������̣�Ǥϰ¿�����������ʤ��Ȥ��ä����äƤʡ�
����Ф��ʤ��饹�����ɤ��ۤ����ɤ�ɤ�ȳ��ʤ�ߤ�Ƥ�����
�֤����ʤ������錄��...�ʤ�Ƽդ�С�
���ҥ奦���ˤϼդ�ʤ��ⶵ���Ƥ����ʤ��顢��ʬ�⤳���ͤ���
����ϷҤ��äƤ��ʤ��Ȥϸ�������Ϥꡢ��ʬ�ȥҥ奦���ϻ���ʤΤ��ʤȶ����פäƤ��ޤ���
������ۤä��ޤޤ��ä������䡢
�֡����ҤȤĤ�������ߤ������Ȥ������
��...������
�֤��㤵��äƸ��äƤ����
�����դΰ�̣���狼�餺�����٥�������ۤ�����
�������ۤä����ȡ��դ�褷��©��ۤ���������˸����äƸƤӤ�������
�֤��㤵���
��������त���Ф�����ϡ������ˤϤޤ��ޤ�������������
��...���������ä��Ȥ��������ˤ����Ƥ���㤨�ʤ�����ȵ��Ť��ơ������������ǰ���ä���
���ʤˤ�������Ȥ�ʤ���ϡ��ݤĤ�ݤĤ�ȡ����������ä���
�����Τޤޥ����٥���˿����֤뤳�Ȥ�ʤ������ʤäƤ�����
�֤��㤵��
���������ۤ��ˡ����Ҥ�Ҥ�ȿ��ä���
�֤Ϥɤ����Х�©�Ҥ��Х������Ф�������������Ӥ줿��������ʤ顢�����Τ�������ʤ������ΥХ��Τ����������äƤ�����Ȥä���Ƥ���
���̤˥ҥ奦���Τ�������...��
�֤����䡢�����ĤΤ�������
�����椬���֡�
�֤�����������ȷ뺧����ʤ�������Ǥ������ˡ�����Ū�˥ե�䤬�äơ����Ĥ��餽��ʤˤ����ϰΤ��ʤä�������ޤä��������ΥХ�©�Ҥ�...�����á�ʢ��Ω�ä��ޤ��Ф餢�ʡ�
�����֤��դ��ʤ��顢�ɤ�ɤ�ߤ�Ƥ�����
���ġ��ʤ˲������줫��ơ����뤻�����֤��Ƥ�����
������ʤȤ����ϥҥ奦���ˤ褯���Ƥ�����
�֥ҥ奦��...��
���ġ��ʤ˴��С��ҥ奦���ϥ���١���������եȤ��̤äƤ�äȲ��γ��ؤ�������餷����̵���Ȥϸ���������������餺�����̵�㤵�ø��˥ϥ�ϥ餵�����롣
����ʬ���ˤϡ���ʬ��ä�����ۤ���ͤӤ���Ƥ��Τˡ�
���ʤ�ȤϤʤ��ˡ��������������
���������ʤ⽪���˶ᤤ��������ҥ奦��Ω���ν��ߵサ�褬�����Ƥ�����
�����εサ�衢���䳬�ʤν����ˤ�ͤ������Ƚ��ޤäƤ�����
���ʤˤ�顢���Ƥ����ͻҤ��ä���
�� | | |
|
��2006ǯ10��04��(Wed)��
ŷ��ؤΥ⡼���륷�եȣ���
|
����θ����ʤ���ƶ�������ơ��ҥ奦���Ͼ��������ȿ̤�������
������١��������̤��ͳ���ζ�ƶ�ϡ������ˤ����ޤ�뤳�Ȥ�ʤ��뤳�Ȥ�ʤ�������ľ���ع����̤����ޤޤ��ä���������Ȥʤ�ȸ����̵�����ä�����
������3�����٤��������ǹ������줿�ͳ��졣�ڤ곫������������顢����ϸ����ʤ��Ϥ��Υ���եȤ��ɤ������롣ξ�����ɤ˥Υ�������ι¤��ͤʤ�Τ����ä��������餯������١������˻��֤��դ��Ƥ��ꡢ���줬�¤Υ��������ȳ��߹礦���ȤǾ��ߤ�����ȤߤʤΤ����������Ƹ����������Τι�¤�ϲ�롣
�֤Ƥ�����������١������ϡ���
�ز��˹ߤ������衢���Ϥ����줷�͡������ɤΤߤ����졼�����̯�˶ʤ��äƤ뤷�������夲���ʤ����ɥ͡��ҥ奦���äƤФɤ���äƹߤ��Ĥ�ꥵ��
�����굤�ʤ��ܡ����ȸƤФʤ��ʤäƤ�ʤ����Ȼפ��ʤ��顣
�֤ޤ����ʤ�Ȥ��ʤ������
����Τ���ơ�5�Ⲽ���롣
�������ơ����˴������Х���ʤǡ����ȥǥ������ȤĤ������դ�����
�ؤʤˤ���Ĥ���������
�֤�ꤤ���ġ��ʡ�
������Ĥ��äơ�����ܤ�ʤ�롣
�֤��礤���Ĥ��뤫����ˤ���ޤäȤ���
�ؤ��硢�ޤ���...����
�����档��Ƶۤ�������Ф���
���������դ������ɤ��ޤǤ⿼������ξ��ķ�����
���ϼ��á���
�֤�٤á�
��Ƨ�ڤ���֤������ä���
��������¦���ɤ�ĥ���դ��Ĥ����ä��Τˡ�����ϤޤäƤ��ޤ���
����δ��Ф��Ȥ����롣
�֤�������ɤ��졼����
�����Ƥƥҥ奦���ϡ������ޤ�ʤ������Τޤޥǥ��������ɤؤȿ��겼��������
�������奤����������������������
����®�Ǿ�ؤ��ФäƤ����ɤˡ��ǥ�����뤬���ܤޤ��ͤ��ɤ��롣
������������դ����ǥ������οϤϡ����Ƥ�Ӥ��̤���������Ĥ��椨�ˤɤ��ޤǤ��ڤ줿��
���ڤ줿�ޤޡ�����Ƥ��������Ϥˤ���®��ɤ�ɤ�ä�äƤ�����
�����ޤ�ˤ��ڤ줹���뤿��ˡ����̤�����Ƥ���Τ��Ѥ��ʤ��Τ���
�إҥ奦������
�֤嵐���äƤ롪���ǥ�����롽��������...�������ڤ��ʡ�����
���������������������������������������������������
���ִ֡������ߤĤ���ξ��ˡ��Ӥ��������ۤɤξ⤬�ä�ä���
������Ƥ���Ȥ����Τ˿��������夲��줿���Τ褦�ʡ��ޤ�ǵ�ͤ����夲��줿���Τ褦�ʴ��С�����������˽��롣
�֤��ʤ���������������
���롼���ΥХ���ʤ��ʤ���С����Υ���Ƥ������⤷��ʤ���
���ҥ奦���ϥ��ꥮ��ǥǥ�������ľ������
���ǥ��������ڤ�̣�ϡ��ɤ�ɤ��ߤ��ʤäƤ�����
���ڤꤿ���Ȼפ����ڤ졢�ڤꤿ���ʤ���Фʤˤ��ڤ�ʤ��ϡ�
���ҥ奦������Ⱦ⤬�����Ƥ�����ǡ��⤦����ʾ��ڤ��ʤ�ɬ��˴�ä���
�إ���̵��衣�ʤ˹ͤ��Ƥ�Τ����ܡ�����
�֤����ܡ�������ä���
����ʬ�Фä������������Ҥ�äȤ����顽�����ꤨ�ʤ��������䤷�Ƥ����Τ��⤷��ʤ���
�����Ť��С��ҥ奦�����ɤ����������ǥ����������ˤ֤鲼���äƤ�����
���ɤ˥�С������äơ������ˤ����ߤĤ��Ƥ����Ǥ����Ȥ��ä������������ä���
�ֻ�̤��Ȼפä���
�إ��ۡ��ᤤ�äѤ����ۤá���ä�¾�ˤ��褦�����ä��å��硪��
�֤��䡢�Ǥ⤳�줬���֤���Ū����ô�����ʤ��äƸ�������
������ô���٤ȸ������䤬ʹ�����������ҥ奦���Ϥ���������������ˤ�������������ξ���Фä������Ϥ����礦�ɡ��ɤ����γ��ؤ���餷����Τ����ä����Ĥ����������Ϥ��Ƥ��ʤ����ﳲ�����ʤ��Ȥ������Ȥϡ����ʤ����
�ֿ�ʬ���ޤǹߤ���ޤä��ߤ������ʤ���
�ؤޤä������������ݳ�ꤷ��å�...�äơ�������...��
���ȡ��ġ��ʤ��ۤꤳ���ä���
�֤ɤ���������
�ؤ����ʤ�Ǥ�ʤ���
���ȤƤ⡢�ʤ�Ǥ�ʤ��ʤ������ʡ����綠�����������ä���
���������ȡ��ɤ����ǽŤ�����ư���������Ϥ���롣
�֤Ȥ⤫����������ޤǤ����ʤ��Ȥʡ��ġ��ʡ���Ȥ����⤦���������ڤä��㤦���ɥ���٥�ʡ�
�ؤ��䡢�����...�����ʤ��Ÿ��������Ƥ롣�����뤫�顢���Ȥ���������ʡ� | | |
|
��2006ǯ10��04��(Wed)��
���Ȥ˰��ޤ�Ƴ��������
|
 | ͷ�������ϣЎ�����
���������ͤ�������������������
�ɤ�������٤��ɮ�ǻͶ�Ȭ�줷�Ƥޤ���
��ʬ�ξ�硢����ϡʺǽ�Ū�ʻž夬��Ρˣ��ܡ����ɤ�ϣ��ܤ��礭���ˤ��Ƥ���Τ������ɤ���Ǥ��������ܤˤ����Ȥ���ɮ�����ְ�äƤ�ߤ����Ǥ���
�Ȥ��櫓�ǡ�����������ľ���ƽƤߤޤ�����
���Ȼ����褦�ʹ��ޤʤΤϥ略�ȤǤ��� | | |
|
��2006ǯ10��04��(Wed)��
ŷ�Ϥ�����ʸ�����
|
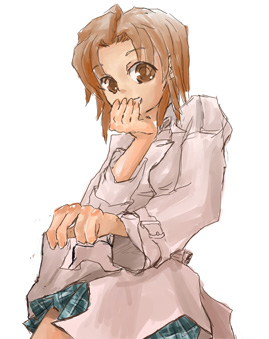 | ��������äȻ��Ƥ������ʡ�
����ʬ�������ĤΤ褦�ʵ������ޤ����� | | |
|
��2006ǯ10��03��(Tue)��
�ˤˤϼ�ʬ������������
|
 | ����ͭ������������餺���ʤ���
�ܤ�ȱ�˥ݥ���Ȥ��������ȿ�¬���뤱�ɡ��ɤä�������ʤ���
�ºݤ�������ʪ�äݤ��ȥ�����Ƥޤ��������γ��ϥ�ǥ������Ǥ���
�äơ��Ĥ��������������ʤ�����;�פ���ħ���ʤ��ʤ��ʤ����� | | |
|
��2006ǯ10��02��(Mon)��
�ӳ��ѻդ�ͦ�Գ�����
|
�������Ŵ���ˤ⤿�줫���ꡢ�з�夲�ƥѥ��ݤ��ࡣ
���롼�餬�и����ʤ��Τǡ������ʤ����ĥޤ���Ȥ˰����������ε���Ǥ��ä���
�ֶر�ѥ��ݤʤ������äƵۤ��Ф褫��������
�ְ������Ƶ���Ȥ����Τ����ʤ�ʤ������ѥ��ݤ�����äƤ������äƤ��鵤ʬ���Фʤ�������
�֤䡼�ͤ������äơ��ߤ�ʤ��ݤ�ɤ��Ȥ���ͤ����٥����ǥ��Х���äƥ��å�������å������Ȥ�����������Ȼפäȡ������פȤ��
�������ơ��Ϥ��äѤ˾Ф��롼�顣
���������ä��Τǡ������β���Фʤ���
�֤�����
������
�֤ʤ�͡����졩��
���褿�ʤ顢�������Ƥ����Ф���������
�֤䤢�衣�����ˤ��äƤ��줿�äȤ衩��
���롼�餬Ŵ���ˤ�����Ĥ����������餳����δ�������Ƥ��롣
�����ä���Ω�������ή��Ƥ��뤫�Τ褦�ʺ٤�ȱ����ͤӤ����ȥҥ奢�ꥣ��ɽ����������������ϥ��������å��ȸ��ä�������������������
����ʬ�λ����˵��Ť��Ƥ����롼��β��餬������������Ф����
��˫��Ƥ�ʤˤ�Ǥʤ��Ȥ��
�ֲ�����äƤʤ�����������
����Ʃ�����줿���Ѥ��������ǡ���夲�롣
���롼�餬���������Фäƥѥ��ݤ�å���������դ�����
���Ȥ������롣
�֤ʤ�ͤ��졣�Ȥ桼�����ʤ�̣����
�֥���ߤ����Ƕ�ŤäƤ����
�֤���������äѤꤳ���λ�̱�ä��ѤȤ��
��Ĵ��˴��С��롼��Ϸ�������ޤ�Ǥ��롣������Ǹ����Ȥ��������������������塢�����ˤ��Υ������Ρ��ȤؤȽ��ۡ����Ĥޤ�ƨ���Ф��Ƥ����Τ���������
�ֹ�˵��뵤�Ϥʤ��Τ���������ͱͽ��ʤ��ʤ뤾��
������Ϸ���Ȥη�ˡ�˵ڤ֤ޤǤι�ʤ��������
���Ⱥ������ˤ����꤫�ͤʤ���Ƥ��ä������Ȥϸ��������ʤäƤ����Х��ĥޤȤ��ƤϤ��꤬�����ä���
�֤䤢�衣���ä��㤳���Ǥ�뤳�Ȥ�����äȡ�
��ť���ο������������Ȥξ��ֻȤ��ˤ��줿����������ʪ�ξ����٤���ưŻ����ͺ��ݤ�����櫓����
�֤��
���롼�餬���ѥ��ݤĥޤθ����ᤷ����
��������������˳Ȥ��롢����ߤ�̣��
�֤��Υϥ������������硼�����Ƨ������äȤ����Ť�ȤϤʤˤ��ȤäȤ衣���ٸ��Ĥ����餮��դ���碌�Ƥ�뤱���
�֤ޤ���ޤäƤ������������ʡ�
�����⤽�⡢�������ڤ�����̤��κ���٤����ʹ֡��פ���˰Ż��ط��ԡˤξ�������뤳�Ȥ��ݸ�ѻ��դ��μ���ͱͽ�����ˤޤǸ������Ƥ���Τ�����ʬ�˺��ߤ��֤��Ƥ���Ϥ��Ǥ��롣
����ˡ����Ȥ����ڤ�٤ϡ����ηڤ��ʹ֤���������Ǥ���̿Ū�Ǥ��롣���������ι٤��Ǥ��Τ��Ϥ�С����ζȳ��������Ƥ������Ȥ��Բ�ǽ��������
�����Ȥ�����٤��줿�Ȥ��Ƥ����
���٤������̤�ϤʤΤ������ȸ���������Ư���Τ��������ȸ����ۤ��ä���
�����Ȥ����Τˡ�����϶�ĥ����ʤ��Τۤۤ����Υ������Ρ��Ȥ������Ƥ��롣
����äȤ⡢�ᥤ�ȥ�Ȥ���Υ�줿���ϩ�ϤˤϿͰ�ͤ��䤷�ʤ���
�����Ƥʤˤ�פäƤ���Τ����������Τ������ۤʤΤ�����ʪ�ʤΤ�����
�����äѤ�狼��ʤ���
������ᤤ����������ȥե������Ȥ���¾�����������羧���Ƥ�����
�֤��줫�餦���Ϥɤ��ʤ�äȤ��͡���
��ͱͽ���������顢����ˤɤä��ԤäƤ����
����ͤ���ͤ���������ȸ������Ȥǥ롼������ݤ�Ǥ���줿�櫓���������ĥޤ�������ǡ���������ä�������Ȧ��ʤ���Ф���ʾ�����ݤ⤴���Ǥ��롣
���ҥ奢�ꥣ�ǤϤʤ��������γ������˹Ԥäƥᥤ�ɤ�Ϣ��Ƶ���ͤФʤ�ʤ��Τ�����
�����ʤߤˡ�ͦ�Գ��ϥ륤�������äƵ��ä����ӳ��Ѥη�����㤤��ä����ȤˤʤäƤ��롣
����ɥᥤ�ؤμ���ϥ륤����Ω���ؤ����Τ���
���Ż��ԤλŶȤ˽��褿���ᡢ�����ʪ�����������ޤ�뤳�ȤϤʤ��ʤä�������ä����Ȥȸ����Ф�����������٤Ͽ�²���ط��������������ޤ�뤳�ȤȤʤä������Υ�����������褹��ˤϡ���ΰŻ��Ԥ�����������̵����������
��Ω���ؤ����륤������⤬�����Ȥ��Ƥ⡢�ޤ��ޤ�����äǤ��롣
�֤������㤢�����ˤ��äȤ��Ƥ�褫��͡�
���Ҥ�ᤤ���ȤФ���ˤϤ��㤰�롼�顦�롼�ס�
��...��
���ޤä����������Τ������ͤϤɤ��ޤ������㮤äƤ����Τ���������
�ʽ�����
| | |
|
��2006ǯ10��01��(Sun)��
����������
|
�������Фäơ����ݸ��������������
�����Τ��ȡ������Ȱ�����������������Τǡ�Ƭ���ˤ���
�������Ϥޤ����Ӥ����ߤ��Ƥ�����������ݵ��ʤ�Τ���
�����ճ����ε����뤲�ʥ��ȡ���Ƭ�˶�����
�������ˤϡ���˱����γ���į��äѤʤ��ξ���������
�������ơ������ޤä������ǽ�ϥХȥ�ʤ�Ƥ��ä��Τ��DZ�ñ���Ф��ޤ��äƤ�������������ʣ��ݣ������ˤˡ����ӥ����ൡ��ï�Ȥ��Τ�ʤ����Ȥ�����Ƥ�������̩Ʀ�ʣ��ݣġ��ˡˡ��Ҥ����������������Ǿ����Ԥ������Ƥ�������ѥ�ʣ��ݣ����ˡˡ������ƥե���������Ĺ��ǭ��
�����������������������С��Ǥ��롣
����︷�������ȸ������Ȥǡ������ס��˽��ޤä��Τ��������ޤä��������äˤ��뤳�Ȥ�ʤ��ä���
�֥���ѥ��
�֤ʤ������
���������ܥ�˾�Ⱦ������ϡ�̵����ʪ������ʹ���֤�����
�������ȤǤ������Τȳ�줿ʢ�ڤϰ쿴����˴����Τؤȸ������ޤޤ��ä�����
�֤��δ����ΤϤɤ��ε�ƻ�����餫�äѤ�äƤ�����
�֤դ�ޤäƤ��롣�ɤ���Ĥ��ƤϺ����������
�������ˤʤäƤ��ʤ��ˤ⤫����餺�ϺƤӾ�����Τ������ͤ��Ф�����¤�ޤ�����¢�����٤Υ��ڡ�������ΤǼ���ʤ��Ȥ��ξ�ʤ���
�������ξ��μ����դ�������¦���碌�롢�Ƴ��Ǹ����Ȥ����Υ��ˤη����ä���
��������Τ������Żߤ����ơ����Ф餯���Ƥ�����ؤ��ᤷ�ơ��ޤ������Τؤ��ͤ��Ф��ȸ����٤��٤ⷫ���֤��Ƥ��롣
�֤ʤˤƤ���������
�֤դ�ޤäƤ����
��ξ���ʿ����˸����ơ����Ǹ�������
�֤���Ϥ��Ȥ���
�ֽФ���Τ�����
����ǽ�Ϥ�Ļ�ȥ��ߥ�˥����������������ν��� �Ǥ��롣��Ʈ�Ȥ�פ碌�뤬�ä���Ȥ����γʤȹ��ʤ��餷������ʿʹ֤Ȥ���ȿ�ФΥ��إ��ǽ�ϡ����Ȥϡ������θ��դ�����
��������Ʈ�Ȥ��ϡ�����������������
�ֺ�����ˤϡס�
�֤�������
�������餯̵���������Ȼפ��ʤ���⡢��˱�ϰ�ʬ���֤��٤줿���Ȥ������
���������Υɥ�����������
������äȸ�������ʹ�����ơ��������Ĥ�����
���ɤ�����Ƥ��ޤä��餷����
�����졣���ޤ�䤷�ʤ������
����˱���Ƥ��᤹�ȡ��⤬��ä���ȳ������ڲ����������������
�����餷�ޤ����Ȱ���������Τ�������������Τ�����ѥ�������ä���
����ǯ�������߾ϤDz�ä�����
��ʹ���Ƥʤ��Τ�����������
���������˥������Ĥζ��ն�ˤϡ֣ʡפ�ʸ���Хå����֤鲼���äƤ������֣ʡפ���˱�����ǯ�����߾ϤǤ��롣���ʤߤ˰�ǯ���֣ơפǻ�ǯ�ϡ֣ӡס�
�֤��������С��ʤ�ǣʤʤΤ���������ѥ���
�֤���ʤ櫓���뤫����ǯ�ϥ��ڥ���ǰ�ǯ�ϥե���ԥ�
�֥����ʥӥ��Ȥ���
�ֹ�̾�Ǥ���ʤ��ʡ�
���ʤɤ�̡�ͤƤ���ȡ�
�֣�...����˥���j u n i o r �ڷ��۸��ڡ�ǯ���Ρ���ǯ����ˤ�������ǯ���Ρ�̾�۸��ڡ�©�ҡ�ǯ������ǯ����ˤ�������ǯ��...��
����餬ñ��Ģ���ɤߤդ��ä��ޤޤ��줤����
����äȤ⡢ñ��Ģ���ɤ�Ǥ���Ȥ����櫓�ǤϤʤ�����������
�֣�...�ե�å���ޥ�f r e s h m a n����̾�ۿ��������鿴�ԡ���...���˥���s e n i o r���ڷ��� ��Ǥ�����ڤΡ��Ǿ��Ρ���̾��ǯĹ�ԡ����ڡ������...��
���ޤ�Ǽ�����ɤ߾夲��褦�ˡ�ñ��ȸ�����ɤ߾夲�Ƥ�����
�֤դФ���ñ��Ģ�ե����������Ф��Ƥ�֤ˤ�����������
�֥ե�����f e t i s h i s m����̾��ʪ�����ҡ��ե��ƥ������ࡦ��ʪ�����䤬ñ��Ģ�ե����Ȥ��������̤�οʹ֤ʤ顢��ñ��ϼ����Τ���˳Ф��Ƥ���櫓�ǤϤʤ����Ȥˤʤ�Τ�����Ϥʤ���
��������Ĭ�����������ˤ����
����������ñ��Ģ�Ĥ�ޤޤǤɤ�����Ǥ��롣
���ä�����á�
�ֹ�魯���ʤ�����ۤɤ�ʤ����������ʡ�
����Ϥΰ��������ʤ�Ǥ����ڲ���꾷�����롣
�����¤ζ��������λ����Υơ��֥���濴�ˡ��ڲ����ư��������
�����礦�����郎����ä��Τ������Ԥ����夲����
�֤䡣ï���������ꡩ�����Ȥ����餦������������ǯ�����Υ��åȥۡ����������ä��ꤷ�ơ���
�֤դ��ۤ�Ǿ̣���ȥ����ƥ��
�֤ʡ��ȥ����ƥ�äƤʤˤ������������ˤ���ȳ�餫�ʻͤ��ͳѤ����ä������Τ褦�˰��Ф�Ȥ�����������̣����
�֤������ä��٤��ä��������ɤ�ɤ��ä�ȴ���Ʋ����Ф���Ƥ�������������������ۤ졣�ޤä���������ʤ�Фä��꤫���������ϡ�
�֤֡֡֡����������ʡססס�
������©��Ĥ��Ʊ�˱��
��������
�֤���...�Ǥϡ��椬�����٤����⤷��ʤ�����ã�衣����������Ҳ𤷤褦��
���ڤ��ä���������̵���˳Ȥ��롣
�����⡢���λ��Ф�����ڲ��δ����
�֤��������äƤ뤸��ɡ�����褳�ζ����ե�������
��̯�ʤ���̾���դ���ʡ���Ĥ�λͤ����ޤȤ������ȥ����ƥ�ʤ����������
����Ĺ�������ա�̾�ۡ�
�֤ʤ������������
��second ���뤤�� kept woman �äơ������������顩
...�桹���������Ϻ�ǯ�٤���������ͽ��ʤΤǡ���ǯ���Τߤǹ�������Ƥ��롣�㤤�ޤ�������
��All right����
�֤��碌��ʡ���
�����ƴְ�äƤ��롣
�֤դࡢ�Τ��ˤ���Ͻ��פ��ʡ��Ǥ���Ĺ�μ�ʬ�����˿Ҥͤ褦��
�ڲ�����������������Ϻ�ǯ�٤��������뤳�Ȥ���ޤäƤ��롣����Ǥ��������뤫������
���������Ф˹������ڲ����ˤ����
���ڲ��ϡ����¤��ܤ˸��������Ƥ����ɤ�������줷���ͻҤ��ä���
��ɢ���ڤϡ�����...��ʬ�β��ͤǤ��������οͤ����ʤ���С���ʬ�ϰ���������Ƥ��������Ȥ��ɤ�����ڤ������������äƤ��Ȥ��Ƥ⡢���ΤȤ��������Ƥ���ɤ��ä��ȡ����äȲ���³���Ƥ�����...����ʸ�����¤���ɢ���ڤ�ʧ�äƤ��줿��
�������顢��������ڤ���̤Τ������ʤ���
�����ڤ������������������ʤ���
����Ƥ���ʤ�ơ��������ʤ�Ǥ��礦����...��ľ�˸����С����ε��������������������������Ȥ��Ƥ��ޤ������줬�ְ�äƤ�Ȥ�פ��ʤ���
�������ͳ�Ǥ����Τʤ�...��
�������ϡ֤थ�פ�ӹ�ä���
�����˼�����Ƥơ�
�ַ��Ϥʤˤ����㤤���Ƥ���ʡ�
�֤ϡ��Ϥ�����
�ּ�ʬ����������ջ֤Ϥ��뤫��ʹ�����������������ʷ��������Ф�����
�������ȡ��ڲ������롣
���ڲ��Ϥ��Ф餯���ۤ������ȡ��サ�����������Τ褦��Ʋ����Ω��ľ������
�֤���ޤ���
�֤褦���������ڡ��Ǥϳ��ν�������������åס�
��������Ψ�褷�Ƽ��á���ȡ��ͿͤФ���ζϤ�����꤬�����³������
�����˾Ȥ�ʤ��顢�ڲ��ϼ�ʬ�������������
�֤褦��������ͳ�Ϥɤ����졢���ޤ����
�֤��꤬�Ȥ��������ޤ������������ޤ������ɡ����졢�������Ǥʤ�...�������ڤ��������ڤȰ��ˤ����ʤ顢���μ�ʬ���¤����������Ϥ���ʡ�����ʵ��⤹���Ǥ���
�֤�����������ϡ�
���ʤˤ��Ǥ��롣
�����˥ӥå��ꤷ���Τ�����Ȥ���줿�Τ����ե���Ĺ�������äѤʤ����������Υɥ�����ФƤ��ä���
�ʰ�������
| | |
|
��2006ǯ10��01��(Sun)��
�ӳ��ѻդ�ͦ�Գ�����
|
�֤ʤ�Ǥ����ʤ�Ρ���
�����ˤȤ����Τ˼����ٶ��Τ���ȡ֤ʤߤϤ���פ�ƨ������Ǥ��Ƥ����ҥ奢�ꥣ�ϡ��褦�䤯�ä����������ĥޤˤ��������Τ��ä���
�ֳ������˹Ԥä��Τˡ��ᥤ�ɤ���äƤ���ʤ�ơ�
�ֲ����Τ뤫��
�֤��������䥭�äƥ��饳������ʤ��ΤǤ�������
�֤���ʤ櫓�ʤ��Ȥ衣�����䥭�ˤ��Τ���������Ȥ��ޤäȤ�äȤ��
���������Ρ��Ȼ�̱��ʹ��������ܤ������ʲ��ä깭���ʤ��顢�����䥭�Ƥ���Ŵ�Ĥˤ�����Ĥ��Ƥ���ᥤ�ȥ롼�顣
�����ʤߤˡ��롼��Ϥޤ��ᥤ��������Ƥ�����
�֤����ǤϤ��Υ��饳�ϲ��˻Ȥ��ΤǤ�������
�ֲ��ˤ�Ĥ���ʤ��äȡ��դġ���ź����Τ������ΰ��ʤäȤ衣
�ޤ��������Ҥ��ˤ��Ƥ�褫���ɡ�
�֤����Ҥ�...��
�����ä�����˹Ԥä��Τ����顢���Ԥ������Ƥ������ȸ������Ȥˤʤꡢ�����ä��Τ����ȥ��饳���ä���
�����ϥ��ĥޤ������饳�ϥ롼�餬��ä���ΤǤ��롣
������ϻɿ��Ѥ������㤦ͽ����ä��Τ�������ä��ΤϤ����Ƥ��Ѥ����Ǥ��롣�֤����Ƥ��ѡפȽ줿�����ͻ����Ȥ��ˡ��롼��ȥᥤ���۾�ˡ֤����Ƥ��פ˶�̣�������ᡢ�����ʤä��Τ��ä���
�����ĥޤˤȤäƤϲ��ҤȤĤȤ����������ʤ���
�������Ƥ��Ѥ������ɿ��ѤȤ��̤�����Ƥ��뤳�Ȥ�ޤ�ơ�
�֥롼�餵��äơ���η���οͤʤΤ��ʡ��ۤ��������Ȥ��⤽�������ɡ����饳�äƤ��ä���������翩���äƤ�������
�֤餷���ʡ��вԤ�����Ƥ���餷����
������ť���ȸ������Ȥ��������������롣���饳���翩�Ȥ����Τ��и�����������˿��٤��Ƥ���ΤϳΤ�������ˡ���Τ���η�������Τ�ΤǤ��롣
�����������˵ڤ�ǻפ鷺��äƤ��ޤä��Τ�������
�֤ʤ��ܿͤβ��DZ����äȤ�äȤ��
���롼�餬���������Ƥ�����
����ˤ������̤������뤯��Ȳ�ž�����Ƥ��롣
�֤����ꡢ��Ȥ���˰����ϺѤ���Τ�����
�֤�...�ޤ��äȡ�
�������̤�����������ơ��ȿ̤�����롼�顣
�֤��äƤ���������̣�������
�֤����狼��ʤ��������
����Ȥ������ϲ���ˤ��롣���Τˤϲ���˷��ķ���Ω�ƾ����Ǥ��롣
�����餫�ˤʤߤϤ�����Ť����η���Ω�ƾ����ϡ��͡����祴�ߤȤ����פ��ʤ��ȶ��⳰�ˤҤ��ᤤ�Ƥ��ꡢ�ҥ奢�ꥣ۩���֥��߲��߰�������פǤ��ä���
����ȤϤ��η���Ω�ƾ����ˡ��Ȥ��ƽ��߹���Ǥ����ͤǤ��롣
�֤ޤ���������...�ɤ������Τ��ä���ï�����⤦����̣�ʤ�����������
���ᥤ�ͤȤ��ƽ��ޤ碌�Ƥ�������Ǥ⡢���餫���ä���
���Ȥꤴ�����ΤϤ�������ï��ʹ���ƤϤ��ʤ��ä���
���롼��ȥҥ奢�ꥣ�ϤȤ����ȡ����ĤΤޤˤ��µ�齡��Ȥ�����Ƥ��롣
�֤������á��롼�餵��äơ��錄�����ǯ���ʤ�Ǥ�������
�֤ߤ����Ȥͤ�����̳���齪��äơ��������ۤ����äȤ��
�ּ�ʬ�ǽ��ۤȸ�����...��
�֤����������äƤ��Ȥϡ��錄���ȥᥤ�����ȤΤ��礦�ɿ����������ꤸ��ʤ�������Ǥ���ʤ����ͤ�����ʤ�ơ�ȿ§���嵐��
�֤ӡ����ͤäȡ���
�֤����衼������ʤ���ͤӤƤơ��ץ��ݡ��������ɤ����������ʪ�Υᥤ�ɤ�����Ȼפä���Ρ�
���ᥤ�ɤˤϼ㤯���齢ϫ����Ԥ�¿���Τ������פϿ��ͤ餷����ȴ���������μҲ�ͤ˸�����ȸ������Ȥ�������
���Τ��ˡ��롼��ϸ����ܤ�����20��ȸ��äƤ��̤�褦��ʷ�ϵ�����äƤ��롣
���ޤ��������˸����ܤ����ʤΤϤ��줳�������Ȥ���ʤΤ�����
�֤��������襤���ʤ���
��������˥ᥤ������ޤ������ޤ�����ҥ奢�ꥣ��
��ǯ�����ΤäƤ������٤���ü�˱�θ�Τʤ���ΤˤʤäƤ��Ƥ��롣
�֤���...������������ʤ���Ƥ�����ʤ��������ʤ�������������
�ȸ��ä������Ĥ�����
�������Ĥ��줿�ޤޤΥ롼�顣�����˺��ä��ͻҤǥ��ĥޤơ�
�֤ʤ�͡����ο������������Ĥ����衼�ʤϤ��㤮�äפ�ϡ�
�֤��Τޤޤ�����
�֤���...�ᥤ������褦�ʰ����ʤ�͡�
���ȵ줤���Τ�����㡽���ᥤ�������롼��Ϥ���äȤ��ơ��Ǥޤä���
����������ǡ��ᥤ��ŷ��夲���ޤ�ʡ�ξФߤ����Ƥ�����
���Ĥ��ƥ롼���ŷ��뤬�����פ˲�Τ褦�����ɤ�����äƤ���������ä��ΤǺ��𤷤��ͻҤ��ä���
��...�ɤ������äȡ���
�ֵ��ˤ���ʡ����饳�Τ����Ҥ��Ȥ���̤�Τ������˷ڤ���ŷ���Ƥ��������
���ᥤ�λ�������ˤϤ��äȳڱ�Ǥ⸫���Ƥ��뤳�Ȥ�������
�֤ʡ��ʤ�͡�
���������ͻҤǸ夸���ꤹ��롼����ä��� | | |
|
��2006ǯ10��01��(Sun)��
�ӳ��ѻդ�ͦ�Գ�����
|
�֤դࡢ�������Ƥ��������ʡ���ٽ�����
�֤�������Ǥ����äȤ衩��
�ֲ�������
�����ĥޤ��Ҥͤ뤬���롼��Ϥ����̤ˤȼ����Ȥ��ʤ��ͻҤ��֤�����������ʬ���ά����ΤϤ������ʤ��������Ȥ��褯���ʤ����Ȥ��줤�Ƥ��롣
�֥롼����ˤδ����Ϥ�äȤ��������������Х��ʤ�Ƽºݤɤ��Ǥ⤤���Τ��衣���ä����ȿͤ���äƤ���Τ�����͡���ޤ�������夲��Ф�����
�������ʻ��ۤ�Τ��ޤ��륤�����ä���
�֤��Ρ���ɤɤ��������ȤʤΤǤ��礦��...��
�������ƶ�λ�ʧ���Ϥɤ��ʤ�ΤǤ��礦����
������ʴ�Ƥ�ʤ��Ȼפä�į��Ƥ����顢�ޤ���Ƨ�ޤ줿��
�֤դࡢ�Ǥ��ߤ�Ŧ����������ޤ��礦���ȿͤϤ��β��ߤǥᥤ�ɤ�ʱ�����ƥ���������塢������ɽ�ؤˤޤDZ���ǡ�����������Ĥޤ�����ȥ��塼�Ȥνи�������Τ���������ΤǤ������θ塢������ι���������Ƚ�������Ʊ�����롼����ˤ�������Ϫ���������ƥ�����λ�˴���Ǹ��Ƚ���������Ȥ��������辰�Ǥ���
������Ϥޤ������߲���ȼԤβ�����֡��������ͽ�ꡢ�����ͤ����ι�ư�ȿ��������Ѥ�����̯�ʻ����������ȥ�å����ä��ΤǤ��礦�����ޤ������ϵ����Ȥ��ƥХ�Ƥ���櫓�ʤΤǰ�̣��ʤ����䰦���ޤ��礦��
�֤��䤱����Ū�ˤ�����ü�ޤä��餤����衼�ʡ�
�֤Ȥ⤫������������Ƴ���Ф���������ϰ�ĤǤ����Ǥϥ롼�����������Ȥϲ��Ǥ��礦����
���륤���ϲ�����ڤ���褦��ɽ��ǡ��롼����䤤��������
���롼��϶�����ͻҤ�ʤ��ä��������ä���Ȥ��Ȥ��Ƥ���©��Ĥ�����
���ä�ʹ���ʤ�������줿���Ȥ����櫓�ǤϤʤ���������
�������������ᤷ�����餤����Ǥ������顢����
�֤狼�äȤ�äȤ�...���ä��ϥϥ��줿�Ȥ͡�
���٤��줿���¤ˤɤ����褦��ʤ��������롼�顣
�����������˥륤���϶��������餷���Τ��ä���
�֤��������С����ʤ��˥��ȥ�Ȥξ����������ʪ�ˤĤ��Ƽ��䤵����ĺ�������ΤǤ�����
| | |
|
��2006ǯ09��30��(Sat)��
��ǭ
|
�������
��GA-�ݽѲʥ����ȥǥ����饹�� ����Ť����Ȥ�
�˥�λͥ��ޤǤϡ�����ȡض���ASTRO�٤������㤪���ȻפäƤ���Ǥ��������Ť��Ƥ�����äƤޤ�������äۤ���
�ɤä��Ǹ������Ȥ��볨���ʡ��Ȼפä��顢�ɥ�ޥ��Ǹ������Ȥ������ä����ʡ�
���ޤ����भ��饭���å�
���ǽ饭����åȤ��ȻפäƤ����������˥�Υ���������� | | |
|
��2006ǯ09��29��(Fri)��
����������
|
����˱������̡�3ǯ15���饹602̾����ͭ����ǽ�Ϥ���餬´�ȤޤǤ�����������뤳�ȡ�
�����줬�����λ�̿�Ǥ��ꡢ�������ο�����Ū���ä���
�������ơ������λ�̿��ȿȯ���������ǽ�Ϥ�´�Ȱʸ�⼫���˾�ब�ޤޤ˹ԻȤ������ȴꤦ��Ρ�
�����줬������Ũ�Ǥ��ä���
����˱����̤���ͭ����ǽ�Ϥκ����ϡ�¾������ˡ§���Τ�ΤǤ��롣
��ǽ�Ϥ�ԻȤ���Ȥ������Ȥϡ�����������ʤ顢�������������Ѥ¶��֤˾������������˿����ʥ롼����ɲä��Ƥ��뤳�Ȥ�¾�ʤ�ʤ���
�����ơ����������Ф�����������ˡ§��Ϳ�ϡ����θ��������ˤȤä��ǤǤ��롣
�����ΤҤȤĤǤ������˺�����С����ߤ�ʪ��ˡ§����Ȥ��뤢��Ȥ����뺬��§���Ѱ̤��뤿��Ǥ��롣
���ǰ���ʪ��ˡ§������֡�
������ϸ����������������̣���Ƥ�����
���������ߡ��������¾�������ǡ� �������ȤϺ����äƤ��ʤ���
����˱��Ȥ������˻�����˱Į����������������������¸�ߤ���ǯ�������ǤοʹԤ��ߤ�Ƥ���Τ������ޤ�����Ϥɤ��Ǥ⤤����
������ϡ�´�Ȥ�����Ǥ��ֲ��� �Ȥ������¡�
�������顢���������Ƥ�ǽ�Ϥ������ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ������¡�
�������ơ�
�֤��褤�衢�ɤ�����ܹ���夲���äƤ��ä���
����äƤϤ����������ơ���˱���ڲ��Ͽ���Ĥ�����
�����夬�����Ĥδ֤ˤ���ޤ���Ƥ�����
��ƫ������ä��ˤ������Ҽ���ڲ����٤˺¤롣
�ֻ�ǯ������ǽ�Ϥ�ä����ʤ�ƴ�ñ�˸������ʡ����ä���������줿Ķǽ�Ϥ������������������������Ƥ����������ʤ�Ƹ����ơ��ʤ�Ǥɤ����ɤ����ä��ۤ��ɤ��������Ȼפ������ޤ��Ƥ䡢�������ʤ����������Ǥ֤���Ȥ���ʤ��ɡ���������դ�ˤ��������롣����ʤ����顢ͽ¬���Τ����ꤹ���ۤ��äƤ��Ƥ⤪�������ʤ���������
������˽ФƤ������ʼ��ǰư�ϤǷ����Ƥ����롣
������ڻ��μ�ʤΤ��������夬�����ˤϡ���������ˤ䤿���٤����Ĥ�����̣����ī�ޤǤ��Ĥ����Ĥ�塢���Ƥ��ϼ�����ޤǻĤ���ǿͤ�������Ǥ��� ��Ǥ��ꡢ����ʼ�ʤ��ڻ��˻�������Ƥ�ï����ߤϤ��ʤ��Τ���������Ϥ褯���μ����äƵ��äƤ���Τ��ä���
���ޤ�������ʤ��Ȥ�Τ��ޤ�����⤿�ޤ��Ǥ��Τ�����
�֤��㤢����ǯ���ΤۤȤ�ɤ�...����
����˱�Ϥ�ä���ȼ�ä���
�ֻ�Ʊ�Ԥ���������Ū��¿�������̤ζ�����������˼�ʬ��ǽ�Ϥ���������뤳�Ȥ�λ�����Ƥ����
���������ڤˡ���
��ǽ���������Ϥ���äƤ�Τϡ�����������������
��ǯ���ޤǤϻ��ͤ��ä������줾��γ�ǯ�˰�ͤ��Ĥ��������
�����ο�ã�ϼ�ʬ��γ�ǯ������������ǽ�Ϥ�Ĥ�����������´�Ȥ��Ƥ��ä�����ǯ���������֡������������Ȥ���
��...���ͤ���Ȥ��ˤޤȤ�Ƥ��ʤ��ä��ΤǤ�������
�����ε���Ϥ�äȤ���ä���
����äȤ���ä������ºݱ�˱�Ϥ��ΰƤ������˻������������Ȥ⤢�ä���
�������������Ϥ����Ѳ������Τ���
�����夬���ڲ��ˡ֤��Ȥ��Фʡפȸ�꤫������
�֡������γ������뤨��ۤä�ǽ�Ϥ���äƤ��ۤ������Ȥ�������������ĤϤ���ǽ�Ϥ�դ����˻Ȥäƶ��٤������������ä����٤��Ƥ��������֤ò��줿�麤�뤫��ǽ�������ˤϻ����ʥ辰����
��������ޤ������ˤ϶��Ϥ�櫓��������������´�Ȥޤ������Ϥޤä��ߤ����ȸ������������ʡ������Ĥˤ���������Ǥ�¿���Ԥ������辰����
�֤���...��
�ֲ������������������ۤ�ޤ�ƶ��äƤ��ȤʤΤ���
��Ǽ�������ä��ͻҤ��ڲ���
�����ʤߤˡ����夬��˽Ф���ǽ�Ϥ����ʪ�ϼºߤ��롣
��������...��
�������פ��Ф�����ǯ������������Ω���夲���Ȥ��������
�֤���������ĥ��������줿������������⡢�衹��⡢���������μ�ĥ��������줿�����֤Ĥ餯�ʤ�ΤϤ����ļ��Ȥ��äƤΤˤʡ����ꥮ��ޤǡ������Ĥ������ϰϤȻ��ꤷ�������ޤǡ�����������������ͱͽ��Ϳ������
�������ơ������褿��
�ָ³�����äƤ��������������ꤷ�������Ϥ⤦��������
������Ũ��ư���Ф�����
�֤ʤ��ư���Ф������äơ��ȡ��ǽ�����������Τ������Ĥ���������
�����夬�����롣
�ֻ������褿�顢����ϰ��Ƥˤ����Ĥ���ɤ�������٤������Τ���ˡ��˲�ߤ�����ǽ�Ϥ������������äƤ��ۤ�Ǥ����Ĥ��Ƥ�櫓�������Ϥ�¿�����¿������������
����äȤ⡢����Ǥ���ϩ���������Ƥ��ޤä��Τ�����
���ż䤬Ĺ��³������
����˱���ۤä��ޤޤ��ä���
���ä��٤����Ȥ��ä��������������Ƥ�����
���䤬���ڲ�����������
�֤���...��Ʊ���ʤ��ͤʤ�Ƥɤ���ä��Τ��Ǥ�����
����Ϥꤽ�������������Ĥ����⿴�ǤΤ��줯��
��������̵����Ũ�мԤ����Τʰջ֤��辰���ʤ���
�����ꥮ��ޤǸ����Υե�ơ��Ǹ�˽Ф�ȴ����ǽ����ï�⤬�ͤ��롣
����˱���ۤäƤ�����
���������ΤϹ�����ä���
�֤ޤ����ͤ����ʡ�����ʹ���������Ǥ�פä��櫓����ï���äƹͤ��롣
�Ǥ�ʡ���ǯ�Ϥ����������ΤäƤ�����
���Ԥơ����塣�ڲ��ˤ����äϡ���
����˱�Ϲ���θ����Ȥ��뤳�Ȥ��Żߤ��褦�Ȥ�����
������������Ͽͤΰ����Фߤ�������ǡ�
�֤��䡢��˱������̤ʤ�ï���äƲ��Ȧ���ʡ�
���Ȥ����ڲ���ɽ�𤬡����Ѥ�����
���������ʤ��������������ɽ����ä���
�֤��㤢...ɢ���ڤϡ�
�ֹ��塪����
�����֡��ν��ĤΤ������ߤ����
�����νִ֤פ�ä��褦�ˡ�����ϸ��ä���
��ɢ��̿�ʤ顢�����Ĥʤ�ï��Ũ���ʤ�ư�ȯ�Dz�롣�����������Ȥ���
�������������Ӥ���̤˻��äƤ�����
�������˼�ʬ�η���������ƫ�����դ���
�֤�ä����ͤ���
�����Ҥ츫�褬�����⤫�٤ơ����������Ԥ�ϳ�餹��
��������ʪ�����ˡ���˱���ܵ����ޤ����줯��
��...����ʤ��Ȥޤ��ä��Ĥ��Ϥʤ��ä���
�֤��á���ǰ���ä��ʡ������ä����������ä���
���ʤ��⡢������Ф���
����˱������������ˤ⤻���������⤫�����Ҥ��ˤ�³������
�ȡ�
���������Ĥ����
�����Ҥ��ޤ�Ǽ̿���ʤ������Τ褦�ˡ�ʿ��Ū�ˤͤ���Ƥ����٤������Τ褦�ˤʤäơ��ä���롣
��DZ�졢
���٤��ʤꡢ
���ä��롣
��������ǽ�ϤǤϤʤ���
�ֱ�˱����...�����Ƥ���������
����֡�ï���������ʤ��ä���
������ۤɤˡ��ڲ���������ʷ�ϵ��Ϥ������Ѥ�äƤ�����
��ɢ���ڤϡ�Ũ��ï���Τ뤳�Ȥ�����ơ�
�����顢���ä������������ͳ�Ǥá��������줿�ΤǤ���������
�������������ȡ������줫�ͤʤ���
���ڲ��Ϥޤ�����ǽ�Ϥ����椷����Ƥ��ʤ���
���оݤ˻��դ������������ǡ��������Ƥ��ޤ����ˡ�
�������顢��˱����ľ����������
���Τ�ʤ��ʡ�������ʹ�����˻���������ʡ�
�֤�...��
����ʤ����ܶ��ʸ��������Ȥϻפä������ڲ��Ϥ�������������ᤷ����
�������ڲ�����������ۤ�����ȡ��ȿ̤����ơ֤ؤá� �ȡ��ФäƤ�����
���פä��̤�������ܤ���äƤ��롣
�����⤫�⤬���㤯�˾�롣
�ֲ���������Τϡ����ĤϳΤ���Ũ��¦�οʹ֤��ä��Ȥ������Ȥ���������ǽ���Ȥ��Ƥϡ�������ͳ���⤤��
�֤����Ǥ���...�� �����Ȥ����ͻҤ��ڲ��ϸ�����Ȥ���
��ɢ���ڡ���ʬ��Ĺ���ʤ��褦�ʤ��Ȥ�褯���äƤ�...���̤��ȻפäƤ��Τˡ�
��̿�δ������ϡ�ɢ���������Ƥ����Ϥ�����
��̵��������ã��ɢ���ǽ�������뤳�Ȥ��ΤäƤ�����
�֤��ޤʤ��� �����ï�˸����Ƥ��ä����դ��ä��Τ���
���ڲ��ϡ��������뤤����夲�ơ����������Фä���
������ϡ����ä��ޤǤμ���Ū�ʾФ����ǤϤʤ���ï����פ��д���ä���
��...�狼�äƤޤ������ڤ�˾�����Ǥ���͡����äȡ� | | |
PaintBBS Java like a children's Homepage
DiaryCGI [nicky!]
,
|



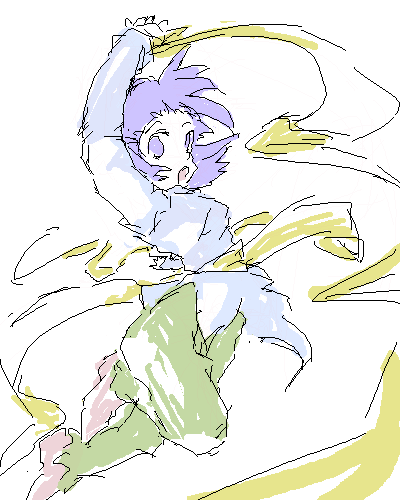



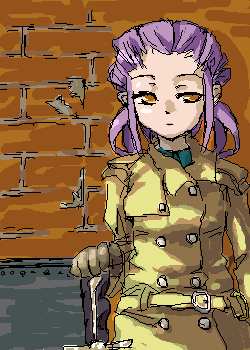
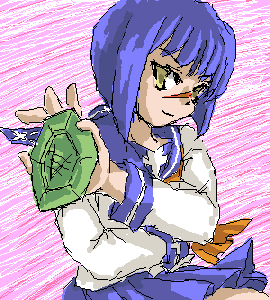

 �ҥ奦�����ΤĤ��ǽޤ�����������Υ֥롼�ʤ⤷����RPG�Υ֥롼Ū�����ˤߤ�������
�ҥ奦�����ΤĤ��ǽޤ�����������Υ֥롼�ʤ⤷����RPG�Υ֥롼Ū�����ˤߤ�������