まず、必須検査としてホルモン検査と抗体検査があります。ホルモン検査は月経周期によって同じ項目でもかなり値に変動があるので月経の3日目から5日目に行うのがいいでしょう。このときは卵胞期といってホルモンの基礎値がもっとも安定して測れます。LH(黄体形成ホルモン)、FSH(卵胞刺激ホルモン)、PRL(乳汁分泌ホルモン)E2(卵胞ホルモン)などを調べます。但しP4(黄体ホルモン)は排卵後に分泌量が増すので体温が高温相になって5日目から8日目に測るのがよいとされています。
抗体検査では抗核抗体や抗精子抗体、抗クラミジア抗体は調べておきたい検査です。時期はいつでも構いません。抗精子抗体陽性の患者さんは体外受精でしか妊娠出来ない場合が多いので早期に調べる必要があります。抗クラミジア抗体検査は過去の感染の既往を調べることになります。すなわち抗体陽性の場合は以前にクラミジアに感染したことがあるということになり、高い確率で腹腔内の癒着が認められるので注意が必要です。
また、生理痛が強い方に対しては子宮内膜症という病気を疑ってCA-125という腫瘍マーカーを調べることがあります。ただ、この検査はあまり特異性の高い検査ではなく子宮内膜症の患者さんで高くなる場合がある、といった程度でしょうか。おまけに卵巣腫瘍や生理中、腹水(お腹の中のお水)が貯まっている場合でも高くなることがありますので少々やっかいです。
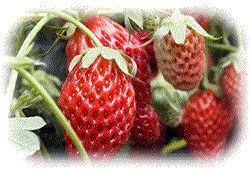 少し専門的ですが中胚葉由来の臓器からは非特異的に分泌されます。特に生理中にお腹がいたくて受診された場合などは高くでる傾向があるのでその日は検査せずに生理が終わってからあらためて来院していただくようにしています。但し、子宮内膜症を正確に診断するためには腹腔鏡という内視鏡検査が必要となります。
少し専門的ですが中胚葉由来の臓器からは非特異的に分泌されます。特に生理中にお腹がいたくて受診された場合などは高くでる傾向があるのでその日は検査せずに生理が終わってからあらためて来院していただくようにしています。但し、子宮内膜症を正確に診断するためには腹腔鏡という内視鏡検査が必要となります。