「俺を殺してくれないか」
漆黒の闇に禍禍しい赤い光りを放ちながら、人の血を塗ったような真っ赤な三日月が
浮かんでいる夜だった。
そんな光の中でも、ロビンには自分に向けられたサンジの顔が苦痛と苦悩に歪んで、
見たこともない程歪んでいるのがはっきりと見る事が出来る。
息をする事さえ、ロビンは忘れ、サンジを見つめ返した。
どんな気持ちでそんな言葉を口にしたのか、血の匂いさえしそうなサンジの声を
聞くだけで痛い程判る。いっそ、死んだ方がどれだけ楽か、と自分の身に置きかえれば
確かにそう思う。
苦しみを感じる事もなく、サンジを殺す事など簡単だ。
それが出来るか、出来無いかはロビンの気持ち一つに掛っているだけの事だ。
「そんな事、出来無いわ」生きていろ、と言う方が酷なのは判っている。
けれど、仲間として大事にしてきた自分がサンジを殺せる筈もなく、また、
サンジを殺したと言う呵責から逃れる為ではもちろんない。
どれだけ苦しかろうと、辛かろうと、サンジは生きていなければならない。
彼らがここへ戻ってくるまでは。
彼らを信じるのよ。そうすれば、きっとなにもかもが終わるわ。
そう言って、ロビンは初めて、サンジと言う人間を知ってから、その体に触れ、
心から慈しんで抱き締めた。
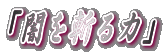 1 2 (第一章 右手の価値)
1 2 (第一章 右手の価値)3 (第2章 呪いの剣)
七星剣と言う聖なる剣があった。
今は粉々に砕け散って、跡形も無い。
本来、聖剣と呼ばれたその剣には、聖なるが故に邪な呪いに汚され、
そして、剣に寄って引き起こされた戦で死に追いやられた者達の怨念を
吸い込み、無数の魂を怨霊に替えた。
1度目はサガと言う剣士にとりつき、そして、その体を以って自らが不業の死を迎えた
怨念の塊である剣の怨霊は、幸福に生きる者全てに嫉妬し、その命を奪うが為に
再び、戦乱を引き起こそうとした。けれども、その目論みはゾロと言う剣士に
阻まれ、拠り所となっていた七星剣はこなごなに砕かれてしまった。
寄る辺のない怨霊はさ迷う。
そして、また、強さをひたすら求める一人の男と出会った。
小国故に、巨大な国に支配され、戦う武器も兵力も無い国の王だった。
自らの強さではなく、強い国になる為に兵力が、つまり、人を殺す為の駒を
多く必要としていた。
人を殺す為になんの躊躇いもなく、そして多少傷付いても、死なない強靭な肉体を持つ、
魔物のような人間がいたなら。例え、それが人間の心を持たない、ただ、人を殺す事しか知らないバケモノでも構わない。そんな者が大勢いれば、すぐにこの国は自由になれるのに。その王はそう願い、怨霊はそこにつけこんだ。
王の剣で斬られた者は死ななくなった。
けれど、その者は剣で斬られた傷が癒えて行くにつれて、その者ではなくなっていく。
自分が何者かを忘れ、大事な者達を忘れ、言葉を忘れ、やがて、人の命の重さを
忘れる。瞳は光芒を失い、肌の色は褪せて、死人の様に姿を変える。
目に人を捉えれば、なんの躊躇いもなく殺す。その体はその為だけに動く様になる。
自我も無く、ただ、人を殺す為だけに生きている、肉体のある亡霊となった。
そうなった彼らを救う術は、首を断ち切るか、あるいは、体に油をかけて焼き尽くさねばならない。剣で斬ろうと、銃で心臓を撃ち抜こうと、一度、王の剣で斬られて、
死人の兵士となった彼らは、殺しても殺しても何度も生きかえるからだ。
だが、その兵は敵国の兵だけではなく、自分達の味方も、武器を持たず、逃げ惑う
自分達の家族さえもなで斬りにし、結果、その国の国力はあっという間に尽き、
滅んだ。死人の兵士達は殺す人間が誰一人いなくなってから、遂には自分達で
命を奪いあった。国を豊かにする為に、家族が幸せに暮す為にと自ら
志願して兵となった者達を待っていたのは、凄惨な末路だった。
父と息子であった者、親友であった者も、もうそんな記憶は欠片も残っていない。
光りを一切宿さない瞳のまま、全身を血まみれにして、自分達が殺した夥しい
屍を踏みちらし、彼らは無感情に目に映る相手を殺した。
生き残った最後の一人は、自分の首を自分で切り落として、
自らの命一つまでをも取りこぼさず奪い尽くした。
虐殺に等しい殺され方をした者、生きながら魂を殺されて怨霊の思うままに
命を奪う人形となった者の恨みを飲みこんで、怨霊の力は膨れ上がる。
豪奢な設えを施された王の剣は、その怨霊を吸い込んで、次の惨劇を待っていた。
鞘に収めれられ、おぞましい「死の兵士」を作り出した伝説の剣として、
噂されたが、戦争後のゴタゴタの最中、その行方を知る者は誰もいない。
まだその刀身を汚した血ぐもりも取れないだろう、わずか、数ヶ月後の事だった。
「これ、見て、すっごい剣よ!?」
麦わらの一味は、たまたま、海上で出くわした海賊船を襲った。
そして、めぼしい金品を物色し、強奪したのだが、その中で航海士のナミが
一振りの剣を、見つけて側にいた考古学者のロビンを興奮した声で呼びつけてそう言った。
「本当ね、見事な細工。宝石も全部、ホンモノね」
「刀身はどう?」とナミから受取り、検分しながら「剣」と聞いて
興味を持ったのか、顔をこちらに向けているゾロにニコリと笑い掛ける。
「戦闘用の剣じゃねえな。どうせ大したモンじゃねえだろ」と興味ありげな
表情をしている割に、横柄な態度でゾロはそう答えた。
「これ・・」ロビンは鞘や、柄をしみじみと眺めて、
「ただの金持ちが趣味の為に作った宝飾品って代物じゃなさそう」
「確かに実用的じゃないけど、独特の文様があるし」と呟くと、
何時の間にかゾロが側まで近付いて来ていた。
「貸せ」
「大したモノじゃないのに?」ぶっきらぼうに言われても、ロビンは嫌な顔もせず、
可笑しそうに柔らかく微笑んで、ゾロにその剣を渡した。
ゾロは鞘からゆっくりと剣を引きぬく。鞘も金属で出来ているので、金属と金属が摺れる、あまり心地良くは無い、小さな「ギャリ・・・」と言う音がした。
そして、目の前に銀色の刃を翳す。
「人斬ってなきゃ、良く切れる包丁くらいの役には立ったかもな」
一瞬だけ、ゾロは異様な気配を感じたような気がした。けれど、初めての
刀を抜く時は、剣士であるなら誰でも一瞬は緊張する。
自分と相性のいい刀と出会ったら、刀の方から剣士に呼び掛けてくる時もある。
その刀の声を剣士は全身全霊で聞き取る為に、これは、と思う得物を抜く時は
意識を集中する。ゾロが一瞬、感じた異様な気配は意識を高め過ぎた為の
錯覚かと思えるほど、ほのかなものだった。
(気の所為か)とゾロはすぐに鞘に戻した。
「使うの、ゾロ?」とナミもゾロに近づいて来た。
表情を見る限り、ゾロにこの剣を持たせるのは嫌らしい。
この海賊船からは奪うつもりだろうが、高価な宝石で豪華に飾られている剣だから、
高く売れるだろうと値踏みしていて、ゾロに使われると売れなくなるから、
ゾロに持たせたくない、と考えているのはミエミエだった。
「使うわけねえだろ、こんなチャラチャラしたヤツ」とゾロは乱暴に
もとの山積になっている宝のところへ投げ返す。
その夜、ゾロは寝つけなかった。
不寝番で、見張り台の上にいて、夜食を運んでくるサンジが来るまでは
何時も起きているのだが、今夜は何時も以上に目が冴えている。
「メシだぜ」とやっと、サンジが見張り台の上に顔を覗かせた。
昼間見た、あのやたらと見事な細工を施された剣の事ばかり考えていて、
何故か、ゾロの心はモヤモヤと陰鬱な空気が詰まっていたのだが、
サンジのいつもと変わらない飄々とした、どことなく、ゾロを小馬鹿にしたような
口調を聞いて、不思議と少しだけ強張っていた心と体の緊張が緩む。
「お前、」ゾロはサンジが持ってきた籠を受取りながら、自分の真正面に座る様、
サンジに示しながら、口を開いた。
「今日の戦利品は?」
「俺か?俺は・・・これだ」とサンジは嬉しそうに自分の腕をシャツをめくって
ゾロに見せた。銀細工の大ぶりの腕輪が細い手首に嵌っている。
「安っぺえ」と今度はゾロがサンジを小馬鹿にしたようにそう言った。
「別に欲しいモノが何もねえから、手間賃がわりに頂いただけだ」と
サンジはそう億劫そうに答えた。本当に答えるのが億劫な訳ではなく、不本意な
戦利品だと思っている本音をゾロに言い当てられるのが悔しいから、
サンジはそんな態度を取っている。サンジと、仲間と言う壁を少し越えた今のゾロなら
見抜く事が出来た。
「お前はどうなんだよ、なんかいい得物でもあったか?」
サンジは話題を変える為に声音も変えて、急にゾロに向き直る。
「俺はねえんだが」とゾロは食べかけていた夜食を一旦、全部飲み込んだ。
「お前、ナミがかっぱらってきた剣、見たか」
「剣?」ゾロの言葉を一度なぞって、
「ああ、派手な宝石がついてる高そうなヤツだな」
ゾロの質問にサンジは期待していた通りの言葉を答える。
「あれがどうかしたのか?」と今度は逆にサンジが聞き返してきた。
あの剣を見てから、ずっと胸に引っ掛かっていた、漠然とした疑問を
ゾロはサンジが質問してくれた事で明確に出来る。
だから、ごく自然にサンジの問いによどみなく答えられた。
「いや・・・あの剣、どう見ても人を斬る為に作ったヤツじゃねえのに」
「なんで血ぐもりがくっきり残ってるのかって気になってな」
「人をたたっ斬る目的で作ったんならもっと頑丈に作るだろうし」
「とてもそうは見えなかった」
ゾロの言葉がそれで最後なのか、どうか、を確認する為か、サンジはしばし、
答えを出すのを待っていた。
ゾロが自分の言いたい事はこれで全部だ、とサンジに目でそう言うと
やっとサンジは煙草の煙を吐き出しながら、
「そんな事が気になるのか?」とまたゾロに問い掛ける。
「次の島に着いたら売っ払っちまう代物だぜ?」
「どんな謂れがあろうと、俺達には関係ねえ」
「それとも、剣士ってのはそんな事まで気になるのか?」
そう言われて、さっきまで胸に澱んでいたいい様のない不安、その所為で
どことなく心臓のあたりの重さが急に消えた。
「そうだな。別に気にする事じゃねえか」
ゾロがそう答えると、サンジは空になった籠を持って立ち上がった。
もう少し、ここにいて欲しい、と思ったけれど、サンジは朝が早い。
昼寝もせず、不寝番の自分の為に誰よりも遅く寝て、誰よりも早く起きるのだから、
無理に引き止めるのは、子供じみた我侭だ。
サンジを大事だと素直に思える今は、言葉には出せなくても、
自分に出来る限りの思い遣りと優しさを少しでも伝えたい。
そう思うから、ゾロは何も言わずに夜食を掻き込んだ。
「あれ、売っぱ払ったら結構な酒が買えるぜ」
「俺は、あの剣を見て、ああ、一杯食料が買えるってくらいしか思わなかった」
そう言ってサンジは笑った。その向こう側には銀色に光る満月が見える。
トップページ 次のページ