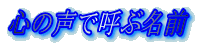
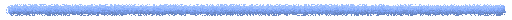
第一章「灰色の海」
第一話「終わりを待つ男」
昨夜からか細い雨がずっと降り続いている。
それなのに、男は、年老いた愛犬と一緒に雨に体が濡れるに任せて波打ち際を歩いていた。
冬が近付いてくる気配を孕んだ雨が、金色がかった白髪を濡らし、頬を伝って流れ落ちる。
年のころは、七十をいくつか超えたくらいだろうか。目には全く生気がない。
生きている意味も見出せず、気力もなく、ただ死ぬ時を待っているだけの目をしていた。
突然、男の足元に寄り添うように歩いていた茶色と白のブチ犬が「ワン!」と
一声高く鳴いて、いきなり走り出す。
「コニー・・・!お前、急に走っちゃいかん!」と男は慌ててその後を追った。
苦しそうにゼエゼエと息を吐き、男は20年以上も生きている愛犬を追い駆け、
海岸の端の磯に辿り着く。
愛犬、コニーは磯についてキャンキャンと何かをその男に知らせるように吠え立てた。
「・・・なんだ、なにかあるのか・・・?」
磯は雨と表面にびっしりと生えはびこった海草の所為で、ひどく滑りやすい。
男は、滑らない様に注意しながら、ゆっくりと足を進め、コニーの声がする場所を
覗き込んだ。
「・・・こりゃあ・・・」と思わず息を飲む。
磯の岩場に、白いシャツを身に纏った、ずぶ濡れの若い男がぐったりと倒れていた。
下半身はまだ海に浸かったままだ。泳いできたのか、流れ着いてきたのかわからない。
血の気の失せた顔、力なく投げ出された腕、その指先は全く血の通った色をしていない。
「・・・そ、そんなバカな・・・」と男は呟き、しばし雨の中呆然と佇む。
凍て付いた様に、男は暫くその若い男を見つめていたが、けたたましく吼える犬の声に
ハっと我に返り、慌てて男を抱き上げた。
その体はくったりと柔かい。
(・・・生きてる・・・!)そう思った途端、無意識に若い男を背負っていた。
※※※
「デンさん、こりゃあ、助からんよ」
「そんなワケはない。まだ若そうだし、きっと体力はある」
一人暮らしの寂れた家に運び込み、男は村の医者を呼び、すぐにその若い男を診て貰った。
だが、診立ては芳しくない。
「衰弱も激しいし、・・・心臓も随分、弱ってるし、熱は高いし・・・」
人の良さそうな40がらみのその医者は、
「手は尽くすけど、」と言いつつも、もう半ば諦めかけている。
「しかし、どこの誰かもわからんうちに死なせたら、この人の親御さんが気の毒だ」と
デン、と言う男は食い下がった。
「息子がこんな風に海で溺れて、誰かに助けられて、そこで医者に見離されていたらと
思うと、・・・堪らないんじゃ」
「あんたの気持ちも分かるが・・・。私としては、デンさんの体の方が心配だよ」
心底気の毒そうな顔をして、医者はベットに横たわっている青年に目を向けた。
その若い男の皮膚は滑らかで白い。
これほどキメ細やかな肌は、若い女でもそうはいない。
きっと、端正な顔と、美しい髪の色、それとその肌の所為で、邪な人間の毒牙に
掛かってしまったのだろう。性的な暴行をかなり長い間、受け続けていた事を
医者は手当ての最中に気付いていた。
(多分、・・・人買いの船から命がけで逃げてきたんだろうな)と思った。
心臓の衰弱はおそらく、その時に使われた媚薬のような薬の副作用だ。
青年の呼吸は弱くて浅い。今にも止まってしまいそうだ。
それに、熱がとても高いのに、顔色は青ざめたままだ。
心臓だけでなく、体中、その薬の所為でボロボロに違いない。
それでも肌の艶や弾力が失われていないのは、もう奇跡としかいいようがない。
「・・・20年前に、海で息子さんが行方不明になったって聞いてるけど、」
「この人は、あんたの息子じゃないだろう。生きていたら、40歳くらいになっている筈だし」
今日初めて診る手の施しようのない青年よりも、長年医者と患者としてだけでなく、
親しい隣人としても見知っているデンの方が医者としては気がかりだった。
それでも、デンは眉間に深い皺を刻み、沈痛な面持ちで
「・・・生まれ変わりかもしれん・・・。息子が生まれ変わって、ワシのところに
帰ってきてくれたのかもしれん、と思ったんじゃ」と独り言の様に呟いた。
※ ※※
医者は、急患が来た、と言う知らせを受けて帰ってしまった。
デンの体には、内臓のあちこちに悪い腫瘍が出来て、もう長くはない。
二年前に長年連れ添った妻も亡くして、それまで二人で営んできたレストランも、
とうとう半年前に体力の限界を感じて閉めてしまった。
一人前の料理人にと期待をかけた一人息子も、修行から帰って来る途中、
海賊に襲われて、二十年も経ったのに、未だに行方が知れない。
そんな寂しい境遇の中、デンがどうにか生きているのは、息子が旅立つ前に拾ってきた愛犬のコニーの面倒を見なければならないと思うからで、他に生きがいなど何もない。
コニーが天寿を全うしてくれたら、食べ物を断ち、ゆっくり死んでいこう。
そう決めていた。
そんな中、デンは海で息子にそっくりな男を助けた。
磯で男を見た時、愕然となったのは、自分の元から旅立って行った息子が
その時の姿のままで急に現れたのかと思ったからだ。
だから、思わず、「そんな、馬鹿な、」と呟いてしまった。
「そんなワケはないだろうが・・・。倅が死んだのが20年前、」
「お前さんが生まれたのもその頃だろうから・・・。生まれ変わりと思っても、
不思議はないじゃろ?」
デンは、意識のないその若い男にゆったりとそう話しかけた。
それから、デンは寝食を忘れて男の看病に没頭した。
聞こえていようと、聞こえていまいと必死に励まし、部屋を温め、
医者から貰った薬を細かく砕き、温い湯で溶いて一さじ、一さじ、唇の端から流し込み、
一時も目を離さずに必死に男の命を繋ぎとめようと努めた。
※ ※※
医者が見離した男は、デンの献身的な看護のおかげでどうにか一命を取り留めた。
「・・・まだ、何も思い出せんか?」
男が起き上がれるようになってから、朝になって顔を合わせる度、
何度デンはそう尋ねただろう。
男は黙って、首を振って眼を伏せる。
「・・・そうか」と答えて、デンは複雑な思いで頷いた。
そんな事をもう何度も、飽きるほど繰り返して来た。
気がつけば、男を磯で見つけてからもう一ヶ月経っている。
今朝も、また同じだった。
デンが尋ね、男が黙って首を振る。
何もわからないままでまた一日が始まる。
向日葵色の髪、くるりと巻いた特徴的なマユゲの青年は、
自分が誰で、どこから来たのか、何もわからなくなっていた。
それどころか、声すら出さない。言葉を出す方法までもを忘れてしまったのか、
デンが話しかけたら、いつも、申し訳なさそうな表情で顔を伏せるだけだ。
「まあ、いいさ。体も心も治るまで気兼ねなくここにいなさい」
そう言ってデンは笑いかけても、青年は微かに、心細げに頷くだけだ。
早く何もかも思い出して、元気に明るい表情を見せて欲しい、と言う気持ちと、
本当に息子の生まれ変わりとして、何もかも空っぽのまま側に置いておきたいと言う
気持ちが心の中で澱む。
デンは、その青年を息子の名「サン」とそのまま呼んだ。
「お前さんは、きっとワシの息子の生まれ変わりだ。髪の色も、眼の色もそっくりだ」
まあ、そのマユゲは似ても似つかないが、とデンは「サン」を安心させようと、
常に温かく優しく接した。
傷ついた息子が自分の元へ帰って来た。
息子を守れるのは、自分だけだ。
日を追うごとに本当にそう思えるようになり、崩れる一方だった体調が少しづつ良くなっていく。
起き上がれるようになり、一緒に食事を取り始めてからしばらくして、
「サン」が、デンが料理を作る様をじっと見ている事に気付いた。
「・・・手伝ってみるか?」と声をかけると、その時、初めてずっと曇ったままだった
「サン」の顔に光が射し、輝いた。
(・・・ほう・・・)
デンは、「サン」の料理をするその手つき、手際のよさに思わず眼を見張る。
特に、包丁捌きと火加減の妙は、本職の料理人、それも一流の腕前と言っていい。
正直、こんな田舎島で細々とレストランを営んでいた自分よりも、ずっと高度で確かな技術を持っている。
それだけではなく、「サン」は水を得た魚のように本当に楽しそうに食材に向き合っていた。
料理をするのが楽しくて嬉しくて仕方ない、と言った風にデンには見えた。
そして、それを見て、また思った。
(やっぱり、これは、サンだ。顔かたちは多少違っても、あの子の生まれ変わりだ・・・)
「・・・自分の名前が言えなくても、料理の仕方は覚えてるなんて、根っからの
料理人だったんじゃろうなあ」と言うと、「サン」は、初めてはにかむような笑顔を見せた。
※ ※※
デンの故郷は、火山の爆発で、大きな地殻の変動があり、海に沈んだ島だ。
その島の歴史も、文化もその時に継承していた者が島から脱出する時に持ち得た分だけが今、どうにか細々と後世に伝えられている。
デンは、その島の文化、特に食に対しての文化を後世に残すようにとの使命を
担った一族の、最後の生き残りだった。
その島独自の野菜、調味料、調理法、調理器具などを後世に伝える為に、
デンの父親は、その島の料理を出すレストランを開いた。
デンはその跡を継ぎ、ゲンの一人息子「サン」もその店と技術を受け継ぐ筈だった。
つまり、「サン」は、料理人になるべくして生まれて来た子だった。
(これは偶然じゃない。こんなに腕のいい料理人がワシのところに流れ着くなんて・・・)
自分の代でその料理が途絶えてしまうと諦めていたデンに、
その生まれ変わりの「サン」は、言葉一つ出さなくても、側にいるだけで、
生き甲斐を与えてくれた。
「ワシが伝承した料理を全部、お前に教えてあげよう」
「お前サンが全部、覚えて・・・。一人で生きていける様になるまで、
ワシがお前サンを守ってやるからな」
そう言うと、「サン」は困惑した様な表情を浮かべた。
だが、きっと元々が心根の優しい青年だったのだろう。
老齢のデンの体も事も、自分が今、デンの生き甲斐になっている事も察して、
逆にデンを労わろうとしているのか、優しく穏やかな眼差しで静かに頷いた。
※ ※※
「サン」の体が完全に回復するのを待ち、デンは閉めていたレストランを再開した。
相変わらず言葉は話せないが、身振り手振りでなんとか意思の疎通は出来る。
それに、店を開けば嫌でも「サン」は人目に晒される。
そうすれば、身元が分かるかもしれない、とも思ったのだ。
「サン」が、息子サンの生まれ変わりであったとしても、今の親は当然、別にいる。
二十年も帰らない息子を案じ続けたデンにとって、その親の気持ちを考えると、
「サン」を手元に置いておきたい、と言う気持ちはあっても、
親に無事を知らせなければと言う気持ちも、抑えられない。
「渦を巻いたマユゲで、金色の髪、二十歳ぐらいの長身で、超一流の腕前を持つ料理人」など、滅多にいるとも思えない。
(・・・身元が分かったとしても、事情を話してもうしばらく面倒を見させてもらえれば、
・ ・・それだけで充分じゃ)
そう思いながら、デンは日を過ごした。
それはとても寒い、横なぐりの細かい雪が吹き付ける夕暮れだった。
「ここにマユゲの渦巻いた、料理人がいるってホント?!」
いらっしゃい、とデンが言う前にその女は店に飛び込んでくるなりそう叫んだ。
オレンジ色の髪に、雪が絡まるように凍り付いている。
とても気の強そうな若いその女は、呆気に取られているデンに気付き、足早に
近づいて興奮気味に、
「オジさん、ここにマユゲの渦巻いた人、いる?その噂を聞いてあたし・・・」と言い募った。
「いるけど、お嬢さん、あんたはあの子の知り合いかい・・・?」
デンは慌てて遮った。(来るべき時が来た、)と急に息子と引き裂かれる、と言う苦しさが
デンの胸にせりあがってくる。
第二話「声」
海賊と海の上で出くわし、麦わらの一味はその海賊と一戦を交えた。
それは、今から半年近く前の話だ。
至近距離での激しい大砲の打ち合いで高く水柱が上がり、その戦闘に興奮した海王類が騒いで、海は嵐でもないのに荒れに荒れた。
ナミはその煽りを食らい、海に投げ出された。
すぐにサンジが船に繋がったロープを持って海に飛び込み、ナミの体にそのロープを
括りつけてくれた。
「早く、ナミさんを引き上げろ、早く!」とサンジは血相を変えて、ロープを手繰るウソップに怒鳴った。その切羽詰った声を、ナミは半年経った今も、片時も忘れられない。
「どうしたの!」とナミはサンジを振り返った。
サンジも腕を伸ばしてロープをしっかりと掴んでいたのをしっかりとナミは覚えている。
けれど、「魚人だ。下に、魚人が・・・!」いる、と言いかけたサンジの姿が何かに引っ張り込まれるようにナミの目の前で当然、海に消えた。
ナミがサンジの姿を見たのは、それが最後だ。
その時にナミがチラリと見た魚人の手の記憶を頼りに、種族を探り、麦わらの一味は、
サンジの行方を捜した。
その魚人の種族がわかり、その中に、海に落ちた人間や宝をその用途に合わせて別の人間や、魚人に売っては稼ぐ輩がいる、と分かるのに三月掛かった。
それから、サンジを浚った魚人を特定し、そいつを締め上げてどこにサンジを叩き売ったかを吐かせるのに、さらに一月掛かった。
「・・・足癖が悪くて手に負えないから、俺達魚人が考えた、人間の体を
タコみたいに柔かくして動けなくする薬を無理矢理飲ませて・・・。それから、
競売にかけた」とその魚人は言った。
「どこに売ったんだ!」と尚も責め立て、この近隣の島々の悪事に全て絡んでいる、と言われている大きな組織がサンジを買ったと分かった。
麻薬、密輸、人身売買、そんな事に手を染めている組織に体の自由を奪われた状態で
買われて行ったのだから、その先は一つしかない。
生きている事が分かって、なんとか助け出す為に彼らの息が掛かっている場所を
手当たり次第に探った。おおっぴらに騒ぎを起こせば、サンジを隠されてしまうかも
知れないし、あるいはサンジを人質にしてどんな厄介な取引を要求してくるか分からない。
あくまで静かに、けれども、噂の一つも聞き逃さずに的確に確実にサンジの行方を追った。
そして、「男娼が客を殺し、その客から盗んだ高価な宝石を盗んで逃げた」と言う噂を
聞いた。その男娼は宝石を盗んで逃げただけではなく、自分が商売道具として扱われた
店を、木っ端微塵に爆破したと言う。
あまりにもその被害は大きく、遺体すら見当たらない従業員や、男娼もいるらしい。
別の噂では、自分を含めて他の男娼や奴隷のように扱われる従業員を逃がす為にわざと
そんな大爆発を起こした、ともナミは聞いた。
(・・・サンジ君だわ。そんな事をするのはサンジ君しかいない)
もうすぐ、サンジを取り戻す事が出来る、と二つの噂を聞いて、ナミは確信した。
それから、サンジがどこへ逃げたかの見当を付けるのにまた時間が掛かった。
そして、海流の方向や、サンジが乗ったかもしれない船の航路を考え、
この島に辿り着いたのだ。
おのおのが港町に散り、サンジの事を尋ねて歩く。
(あたしが海に落ちさえしなければ、サンジ君が魚人に浚われる事はなかった)
自分の所為で、サンジがどんなに辛い目にあっているだろうかとナミは
ずっと自分を責めていた。
何を見ても、世の中が灰色にしか見えないくらいだった。
「ちょっと、聞きたいんだけど・・・。この島で眉毛の巻いた、金髪の若い男の人、
知らない?」港町の端にある、賑やかな酒場の主人にナミはそう尋ねた。
「眉毛の巻いた男?金髪の?ああ、知ってるよ」
「・・・ホントに!」思わず、ナミは歓喜の声を上げる。
「この前まで閉まってたレストランなんだけどね、最近また営業してる」
「そこで働いてるよ」
話を聞いただけなのに、余りに嬉しくて、ナミはその酒場で何も飲み食いしていないにも関わらず、たっぷりとチップを払い、その足で、酒場の主人が教えてくれた
レストランに真っ直ぐに向った。
ルフィ達にも早く知らせたかったが、待ち合わせは夕方だ。
とてもそれまでじっとなどしていられない。
バラバラに散らばった仲間達を探して歩くより、まずは真っ先にサンジのところへ行こう、とナミはすぐに決めた。
(口が利けないって聞いたけど、それぐらい、きっとチョッパーがすぐに治してくれるわ)
走っては息が苦しくて立ち止まり、また走りだす。
雪に足を取られるのがもどかしい。
降りしきる雪の中をナミは、雪を蹴散らしてただ、目指すレストランに向って
走り続ける。
とにかく、一刻も早くサンジの元気な顔が見たかった。
しんしんと降り積もっていく雪の中に、温かそうな光が窓から漏れている。
側に行かなくても、その柔らかな光を見ただけで、ナミはそこにサンジがいる、とはっきりと確信した。
温かな優しい温もりの料理を食べ、人々の心が解れ、笑いさざめく。
その和やかな空気が漏れ出た光の中にさえ溶け込んでいる。
それこそが、サンジの作り出す独特の「空気」で、サンジがそこにいる何よりの証拠だ。
(・・・サンジ君があそこにいる)
そう思うと、嬉し涙が込み上げて、雪に曇る視界がますます曇った。
きっと何も変わらない姿で、いつもの様に楽しく料理を作って働いている姿がナミの
脳裏に浮かぶ。
ナミは体当たりをするように、その店の扉を押し開いた。
誰に何を聞いたらいいかと言う順序が頭から吹っ飛ぶ。
勝手に口から言葉がほとばしった。
「ここにマユゲの渦巻いた、料理人がいるってホント?!」
給仕をしていた小柄な老人が驚いて顔を上げる。
コックスーツを着ているから、この店の主だ、と瞬時にナミは判断した。
早くサンジと会いたい、と気が急いて口調が物凄く早くなる。
「オジさん、ここにマユゲの渦巻いた人、いる?その噂を聞いてあたし・・・」
店の主人はポカンと口を開けて、しばらくボウっとした顔でナミを見上げていた。
※ ※※
「この人がお前サンを知っているそうじゃ」
店にいた客を全部送り出してから主人はやっと、厨房へとナミを案内してくれた。
厨房はきちんと整理され、床も綺麗に磨き上げられてとても清潔で明るい。
けれどそこはナミにとっては自分の領域ではないから、あまり居心地が良い場所ではない。
ナミは粗末な服にエプロンをかけている華奢な背中におずおずと声をかけた。
「サンジ君・・・・」
ナミさん、会いたかったよ!
そう言って、満面の笑顔で擦り寄ってくる、とナミは思った。
サンジは皿を洗う手を止め、ゆっくりと振り返る。
そして、まっすぐに目を逸らす事無く、ナミを見つめた。
ほのかに笑ってはくれたけれども、その表情は、まるでまだ大人になりきれない少年が、警戒心を隠しながら見知らぬ他人をじっと観察するかの様で、どことなく硬く
とても他人行儀だ。
そんなサンジの表情を、今まで見た事がない。
ナミの心を不安が掠めた。
「・・・どうしたの・・・?」
サンジは困惑したのか、助けを求めるように、店の主人を見た。
店の主人は、サンジの意思を汲み取ったらしく、安心させるように小さく何度も目で
頷き返していた。
※ ※※
この子は、料理をすること以外、なんにも覚えていないんだよ。
自分の名前も・・・、どこで生まれて、どこで育って、どうしてここにいるのか、
何もわからないんだよ。
店の主人、デンにそう聞いてナミは愕然とした。
「あたしは、サンジ君の乗ってた船の航海士なの」
「あたしを助ける為にサンジ君は、海に飛び込んで、魚人に浚われて・・・」
ナミとデンはおのおのが知っているサンジの事について話し合った。
しかし、話が進むにつれ、海賊だと言う事が隠せなくなってしまう。
「仲間・・・と言ったが、仲間が7人きりの船って事は・・・」とデンの顔に
僅かに敵意の影が過ぎった。
変に取り繕うよりも、単刀直入に言った方がいい、とナミは判断し、ナミは
「そう。あたし達は、海賊。もちろん、サンジ君も賞金首じゃないけど、
名の通った正真正銘の海賊よ」と真っ正直に答える。
それを聞いて、デンの顔色がさっと青ざめ、すぐに真っ赤になった。
「海賊だと・・・・!そうと分かったら、この子を返すワケにはいかん!」と
椅子が転がるくらいの勢いで、いきなり立ち上がった。店中にデンの声がビリビリと響き渡る。
その剣幕に一瞬、ナミは気圧された。
だが、すぐに気を取り直し、
「サンジ君は、あたし達の仲間なのよ、オジさん!あたし達、サンジ君をずっと探して」と立ち上がったが、デンは耳を貸さない。
「そんな事は知らん!今はもう海賊だった事なんぞ、綺麗に忘れとるんだ!」
「お前らのようなゴクツブシにあの子を渡すわけにはいかん!・・・帰れ!」
(さっきまであんなに温厚なオジさんだったのに・・・)とナミはデンの変貌に
驚きすぎて声も出ない。立ち竦んだナミに向ってデンは拳を振り上げた。
サンジもただならぬデンの様子に顔色を変えて、慌てて立ち上がる。
「帰れ!・・・う!」
デンが拳を振り上げた格好で固まり、「うううう・・・」と呻きながら、よろめいた。
そしてそのまま床に崩れ落ちる。
その体をサンジは床に叩き付けられる前に、抱きとめた。
きっと、サンジも無我夢中だったに違いない。
「オ・・・オヤジさん!オヤジさん!ど・・・どこが痛い!?」
(サンジ君、声が・・・)突然、耳に飛び込んできたサンジの声にナミは驚く。
そして、デンを抱かかえ、床に膝を着いたまま、ナミを見上げた。
「オ・・・オヤジさんが落ち着いたら、」
「きっと、・た、・・訪ねる」
「だから、い、今は」
「か・・・帰って欲しい」
とてもたどたどしい言葉遣いでサンジはナミにそう言った。
(サンジ君、・・・ホントに私がわからないんだ)
今取り戻したとは言え、こんなにもサンジの言葉が拙い。
あまりにも痛々しくて、言葉と記憶を失うほど、サンジは深く傷つき、
辛い想いをしてきたのだと、ナミはまざまざと思い知った。
悔しさと後悔と、悲しさで勝手に涙が目に込み上げて来る。
「・・・ごめんね・・・。サンジ君、・・・・」
そう言葉に出した途端、ナミの目からとうとう、透明な雫が零れ落ちた。
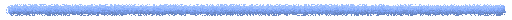
戻る
★