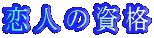ぐっすりと眠れないのは、傷ついた体が痛みで疼く所為ではない。
(…あいつはどうしてる?)たったそれだけの事を、ゾロは未だに誰にも聞けずにいる。
ゾロが何故、満身創痍となったのか、その身に何が起こったのか、知っているのは恐らく、サンジだけだろう。
そして、そのサンジに自分が何をしたかも、ゾロだけが知っている。
あの時の、自分の行動は絶対に間違っていない。もちろん、後悔などしていない。
が、あれ以来、サンジが姿を見せない。
ゾロはそれが気がかりでならない。それなら、(…あいつはどうしている?)と誰かしらに聞けばいいと思うのに、一体、何に気が咎めているのか、それも出来ない。
スリラーバークと呼ばれたこの海域からゾンビが一掃されてからもう三日も経つ。
が、大きなダメージを受けた体はいつもの怪我よりもずっと回復が遅く、ゾロは身動きがままならなかった。
それでも、目が覚めたと知っているなら、何か言って来てもいい頃合だ。
(あんなやり方したんだ。黙ってる訳がねえ…)
ルフィの身代わりに自分の命をクマに差し出そうとしたそのサンジの意識を横合いから強引に奪った時に、腹は括っている。あの時、ゾロは自分の命を諦めたのだ。
それだけの覚悟があったのだから、サンジにどう詰られても責められても、平然と受けて立って見せる。
そう思い、悠然と待ち構えていられたのも、目が覚めてから数時間だけだった。
食事のたびに顔を出すかと思ったのに、サンジは全くゾロの前に顔を出さない。
口にする食事は、明らかにサンジの作った物なのに、それを運んでくるのはチョッパーか、
ナミかロビンで、どんなに寝床の中でじっと大人しく待っていても、サンジは来なかった。
だんだんとゾロの胸の中に不安が滲み出してくる。
(…相当、怒ってやがるだろうな…)と、予想はしているが、沁み出して来た不安が胸の内に広がるにつれ、ゾロは今まで感じた事のない心細さと嫌な胸騒ぎを感じ始めた。
どんなに距離が離れても、どんなに辛い試練に遭っても、サンジが何を信じ、何を思っているのかを揺ぎ無い想いで感じていられたのに、
(…何を考えてやがるんだろう…)と、今この瞬間、サンジの心が見えない。
見透かせていない。
それが、どうしようもなくゾロを心細くさせる。
サンジが何も言わない。サンジの姿が見えない。たったそれだけの単純な、取るに足らない現実。
こんな事は、もちろん初めてではない。
なのに、なぜ、今回に限って、こんなにも不安になるのだろう。
チョッパーやナミが運んでくる食事は、ゾロの体を気遣うような、いつもどおりの細やかなサンジの料理だ。
いつもなら、食事をする相手の体の回復に合わせて調整しているのだから、どんなに大喧嘩をした後でも、療養中の食事を出す時、サンジはその食事を食べている様子を必ず一度は見に来る。
なのに、今回は一度としてゾロの様子を見には来ない。
それに気づいた時、ゾロはハっとした。
(…あいつ、…俺を拒絶してるのか…?)そう思った途端、ますます不安は募った。
ぐっすりと眠れなくなったのは、それ以来だ。いくら目を瞑っても寝付けない。
※ ※※
そうして、四日目の夜半。
雲ひとつない漆黒の空に、細い月が銀色の光を放って浮かんでいる。
モーリアと言う主も、不気味なゾンビ達もいなくなり、シンと静まり返った城の内から、窓越しにその月明かりを見上げ、ゾロは包帯が巻きついた体に上着を羽織る。
思いの他、その月光は明るい。普通の人間には頼りなくか細い光かも知れないが、ゾロには十分すぎる明るさだった。
「…つ…」
動けば、骨が軋み、傷が疼いた。それでも、ゾロは闇色と月光の二つの色しか存在しないような、静寂だけが取り残された城の中を歩き、やがて、外に出た。
寒くもなく、暑くもなく、心地よい夜だ。激闘の末、舞い上がった粉塵もすっかりおさまり、墓場から吹いてくる風も禍々しいとは思えず、いっそ清清しい。
サンジに会えさえすれば、この胸の不安はきっと消える。
言葉を交わせば、嘘の様にこの心細さは消える筈だ。
そう信じて、ゾロは心を研ぎ澄ませ、サンジの気配と息遣いを探して森の中を進む。
森を抜けると、高い城壁が真っ黒な影を地面に落としているのが見えてきた。
歩を進めるごとに、サンジの気配が近くなる。
(…やっぱり、あいつは少しでも海の側にいてえんだな)
いつもと変わらないサンジがそこにいる。不安がる事など、何もなかった。
そんな安堵を覚えて、知らず知らずに凝っていたゾロの心が少しづつ解けた。
城壁をくぐると、そこにサニー号が停泊されたままになっている。
その桟橋の端に、サンジは海の方へと顔を向け、ただ海風に体を晒している様に
立っていた。
古びた、今にも朽ちそうな木の桟橋の上に、細く、真っ黒なサンジの影が伸びる。
闇色と月光の銀色の光しか見えなかったゾロの目に、陽光を受けた様に輝くサンジの金色の髪がやけにまぶしく、鮮やかに見えた。
色のない殺伐とした世界に、唯一、存在する鮮やかな色。
それは、ゾロの世界にとってのサンジの存在そのものだと言ってもいい。
波の揺らぎが起こす微かな潮風が、その髪を優しく撫で梳いていた。
そんな風景を、朝焼けが空を染めるまで、ずっと見つめ続けたい。
ふと、ゾロがそう思った時、サンジが口に咥えていた煙草をゆっくりと指に挟みつつ、振り返った。
小さく、サンジは息を飲む。
(…なんで、お前がここにいる…?)と言いたげに、その表情に困惑が浮かんだ。
けれど、言葉は出ない。
声を失った者の様に、あるいは、言葉を忘れた者の様に、何も言わずに、何気なく振り返った姿勢のまま、ゾロを見つめている。
その沈黙と、心の内を覗けない淡い表情の変化が、またゾロを不安にさせた。
歩けば、ほんの数歩の距離なのに、その距離がかつて感じた事がないほど遠くに感じる。
何か、得体の知れないモノが自分達を隔てようとしている様にも思え、その不可思議な距離感が信じられず、思わずゾロは自分の足元に目を落とした。
(…そんな馬鹿な事がある訳ねえ)とすぐに思い直す。
そして顔を上げ、サンジの姿と現実の距離を確かめる。
その時には、もうサンジの顔に困惑の影はなかった。
振り返った姿勢ではなく、まっすぐにゾロの方へと向き直り、静かにゾロを見据えている。
サンジは、ゾロの目の前に立っている。
一歩、一歩 歩を進めていけば、すぐにでも手が届く場所にいる。
何かを押し殺しているかの様にも見える、静か過ぎるサンジのその眼差しを見つめ返し、今度はゾロが息を飲む。
「…おまえ…」
愕然として、その感情が喉を突き上げて、うめくような声が勝手に出た。
サンジの心がゾロから遠ざかろうとしている。
心の動きは目には見えない。言葉も交わしてもいない。
けれど、ただサンジの眼差しを見ただけなのに、ゾロにははっきりと分かった。
引き潮が、頼りなく漂う海藻を深い海へと浚っていく様に静かに、けれども確かに
サンジは、ゾロから離れて行こうとしている。
何もかも分かり合い、信じ合い、想い合って、心を重ねて来たからこそ直感で分かった。
抉られる様な激しい痛みがゾロの心に深く、グサリと爪を立てる。
その痛みがゾロの喉を塞ぎ、とっさに言葉が出ない。
立ち竦むゾロに、サンジは追い討ちをかける。
「…何も言うなよ」
ようやく耳にサンジの声が届いた。けれど、待ち望んでいた筈のその音は、さらにゾロを突き放す。
「…何か、言いてえ事があるんだろうが…聞く気はねえ」
感情の篭らない、抑揚のない声でサンジはそう言って、ゾロに背を向けた。
いつもの強がりや虚勢ではない。冷静で、感情のブレは全くなかった。
「…お前こそ、…俺に言いてえ事が山ほどある筈だ」
「それを、何も言わなくていいのか…?」
思いがけないサンジの態度にゾロは衝撃を受ける。
そうして、それを跳ね返す様に自分の感情をそのまま言葉にする。
言葉を選ぶ余裕など無くなった。
いや、むしろ、サンジがゾロに心を閉ざそうとしているのなら、余計な言葉を羅列するだけ無駄だ。
(…思い切り全部、腹のうちを曝け出さなきゃ、話にならねえな…。この様子じゃ、変な意地張ってる場合じゃねえ、)取り返しのつかない事になりそうな予感すらして、
ゾロは改めて腹を決める。
「…言いてエ事あるのに口をつぐんで何も言わねえなんて、てめえらしくねえ。いつもみてえ言いたい事言えよ」
口に衝いて出た言葉は、いつもどおりに自然に煽るような口調になった。
「…言いてえ事なんか…なんにもねえよ」
「嘘つけ」
あくまで頑なにゾロを拒もうとするサンジに対して、ゾロは体だけでなく心ごと歩み寄る。
目を逸らさずに、まして背中など向けずに、しっかりと自分に向き合って欲しい。
そうすれば、きっとサンジはあの時のゾロの行動を理解し、分かってくれるに違いない。
そう思うのに、サンジはゾロに背を向けたまま、そしてゾロは意気地なくその肩に手を伸ばす事も出来ずにいる。
早く、ここから立ち去ってくれ。お前とは話したくない。
サンジの背中が、そんな風に気強く、けれどとても辛そうにゾロを拒絶しているからだ。
「お前、…俺が何を言いたいのか、おおよそ、分かってんだろ?だったら、俺はお前に何も言う事は無エ」
「…俺が言いてえ事なんかねえ…って言ったのは、そう言う意味だ」
そのゾロの感覚を裏付ける様に、サンジは声を絞り出す様にそう言った。
(…こりゃ、相当ヤべえぞ…)
その声を聞いて、ゾロは自分が思っていた以上に深刻な状態になっている事にやっと気付いた。
サンジの誇りを傷つけた事は分かりすぎるぐらい分かっている。
だが、それに対しての言い訳はない。
謝罪などする気は全くないし、ゾロにはゾロの言い分がある。
「…あの時の事、怒ってんだろうが…俺は、謝らねえぞ。間違った事はしてねえ」
「ああ。別に謝って欲しい訳じゃねえ」
ゾロの言葉に、サンジが頷き、やっと振り向いた。
星明りを映した水面の青白く不規則な波の反射が、複雑な感情を必死に押し隠そうとする、悲しげに歪んだ笑顔をいっそう美しく見せる。
「…あの時、ああして俺を庇った事は間違ってない、お前がそう思うなら、…もう、それでいいさ。一生、勝手にそう思ってりゃいい」
「俺は、お前に庇われて死なずに済んだ。お前にとっちゃ、ただそれだけの事だからな」
そう辛らつな言葉をぶつけられている訳でもないのに、ゾロは咄嗟に言葉が返せない。
詰られ、責められる事は覚悟していた。
想像していた以上に自分の心が乱れている事にますます動揺する。
実際に心から愛しいと思い、命がけで守ろうとした相手に拒絶される事が、こんなにも辛い事だとは思いもしなかった。
女々しいかも知れない。縋りつく様な眼差しでサンジを見つめている事も自覚している。
それでも、ゾロは自分の心を全て曝け出す。
それ以外に、サンジの心を引き寄せる方法を何も思いつかなかった。
「…てめえが俺に何も言いたくねえって言うなら、何も言わなくていい」
「けどな、俺にだって言い分がある。それぐらい、言わせろ…!」
「聞くだけ無駄だ」
ゾロの言葉を聞き終わる前に、サンジは即座にきっぱりとそう言い切る。
その言葉だけは、今夜交わした僅かな言葉の中でも、一番はっきりと、明瞭だった。
だが、もうゾロは動揺しない。
伝えたい感情は胸のうちに一気に込み上げて、もう感情が走り出すのを止められない。
「俺だって、死ぬ時は一緒に死ねる、俺が死ぬ時はお前も道連れに出来る、いや、してやるって
ずっと思ってた」
「俺が死んだ後、てめえが誰かに惚れて、俺を忘れて生きていくのかと思ったら、そんな事許せる訳ねえって思ってた」
「本気で惚れてるなら、生きるのも死ぬのも一緒がいい。それが本当だってずっと思い込んでた」
「けど、それは、…違う」
そこまで言って、ゾロの声が詰まった。
オーズと戦った時の光景がまざまざとゾロの脳裏に浮かぶ。
そのゾロの表情を見て、サンジの脳裏にも同じ光景が浮かんだのか、サンジがまっすぐにゾロの方を見た。
「…お前が、オーズにひっ捕まって、死ぬかも知れねえって思った時…」
「あの時、俺は生まれて初めて、怖エって感覚を知った」
「お前が死ぬ事、俺の目の前でお前が死ぬ事が、…俺にとって、どれだけ恐怖だったか…!」
「今まで生きて来て、俺は何かを怖エと思った事は一回も無エ」
「その俺が、…本気で怖エと思ったんだ」
「オーズをじゃねえ。お前を失う事が、怖エと思ったんだ…。正気を失うくらいに、だ…!」
「だから、俺は…お前を傷つけるって分かってても、…道連れには出来なかった」
お前を庇ったのは、自己満足の為じゃない。お前を心から、何よりも大切に想ったからだ。
そのゾロの想いを込めた不器用な言葉をサンジは黙って、目を伏せ、最後まで聞いていた。
桟橋に寄せる穏やかな波音が耳に優しく、長い沈黙の時間が流れる。
ゾロの言葉を聞き、サンジも色々な感情が胸のうちで渦巻いたのだろう。
時間にすれば、ほんの数分、2分もなかったかも知れないが、ゾロにはとても長い時間に思えた。
そうして、やっとサンジが口を開く。
「…それを聞いて、俺が感激するとでも思ったか…?」
「俺を見くびるのも、いい加減にしやがれ…!」
「お前が、そんなだから、そんな甘エ事言うから、」
「だから、余計に許せねえって事が…、なんで、分からねえんだ…!」
怒りともどかしさ、悲しみ、そんなたくさんの感情を湛えた海色の瞳は、まっすぐにゾロを見据える。が、それは一瞬で、サンジはゾロの横を足早にすり抜けた。
「…サンジ…!」
思わず、取りすがるようにサンジの名を呼んだ。だが、サンジは振り向かない。
サンジの心が、急速に自分から離れていく。
それを感じるのに、それを引き止める術も無く、ゾロはただ佇み、その背中を追う事が出来なかった。
つづく