
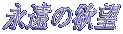
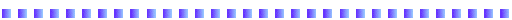
第一章 「漂着」
「第一話」「香華」
「…しかし、なんで俺はお前なんかとこんな事やってんのかね…」
そう言って、サンジは腹ばいになったまま、口元に微かな笑みを浮かべて煙草に手を伸ばした。
***
麦わらの一味を乗せた船は、嵐に揉まれて、波に流され、
ログホースが示す航路を外れてしまった。
食料が尽きる前にこの島に辿り着けたのは、偶然だけれど、とても幸運な事だ。
気候は春か、秋の様で少し湿気が多く、分厚い雲が空一面を覆って天候は決して良くはないが、波は荒れていない。航海には支障はないだろうが、おそらく数日はこんな鬱陶しい天候が続きそうだ。
それに、この島はログから外れている。
つまり、グランドラインでもあまり名の知れていない島で、ロビンすらも
「来た事も見た事もないわ」と言う。
そんな未知の島に辿り着いて、ただ、水と食料の補給だけに立ち寄るのは勿体無い。
「何も無さそうよ。なんだか辛気臭い島だし」
「そうだよな、なんだか…島のあちこちに墓がありそうな陰気な空気を俺も感じるぞ」
華やいだ雰囲気が微塵もない小さな島の様子を遠目から見て、ナミは不服そうな顔をし、
ウソップはどことなく荘厳な森を見て、いつもの様に怯えて見せた。
たが、ルフィは初めての、しかもどこか秘密の場所めいた雰囲気の島に目を輝かせ、
「陰気臭く見えるのはきっと天気だって!森があちこちあって楽しそうだし、晴れたら、絶対楽しいって!」と上陸して冒険する、と決めてしまう。
(ルフィがそう決めたんなら、もう何を言っても無駄だな)
サンジは口の端に煙草をくわえ、残った食材の量を確認しながらルフィとナミ達のやり取りを側で聞いていてそう思った。
「もう日が暮れるぜ。夜中に冒険するのか?」と口を挟んだけれど、ルフィはまだ碇を下ろしたばかりだと言うのに、今すぐにでも「冒険」に行きたいらしい。
けれど、この島に辿り着くまでに、航路を外れるほどの嵐と戦ってきた。
ナミやウソップ、チョッパーの顔を見ると、少し疲れているように見える。
(ちょっと、まとまった睡眠が欲しい頃だろうな…)、と思い、サンジは
「どうせ冒険するなら、色々と準備を整えて、皆で行った方がいいだろ」
「明日の朝にするなら、残った食材を使って弁当作ってやるよ」とルフィを止めた。
そして、久しぶりに麦わらの一味は穏やかな夜を過ごす事になった。
***
素肌で触れ合って、まだ、その温もりを肌に感じる時間が心地よい。
甘い熱で体が溶けて、一つになった直後には、心までが蕩けて一つになれた様に
満ち足りた気持ちになれる。
「…こういうの、…随分、久しぶりじゃねえか?」
ゾロが呟いている声をサンジは背中越しに聞いて、聞こえない振りをする。
(…見透かされたみてえだ)今、ゾロと心が重なっている。
今感じているもの、心地よいと思うもの、幸せだと思う事、その全てがきっと同じだ。
そう思うと急に少し照れ臭くなる。
ゾロに対して罵詈雑言ならいくらでも思い浮かぶのに、こんな時に限って、
どんな言葉を話せばいいのかわからなくなる。
サンジは何も言わずに、口を閉じ、ゾロの言葉を確認するかの様に、目も閉じた。
体の中の熱を持て余して、性急に求める行為ではなく、今、感じている様な
柔かな満足感に浸る時間を持てたのは、確かにゾロの言うとおり、「久しぶり」の事だった。
衣服を身に着けてしまうと、折角肌を包み込んでくれるようなその温みが冷めてしまう。
ランプだけを灯した薄暗い格納庫の中、それが惜しくて、二人ともまだ素っ裸で上掛け一枚を体に掛けた格好のままでいる。
「…しかし、なんで俺はお前なんかとこんな事やってんのかね…」
そう言って、サンジはゆっくりとゾロの腕を解いて、腹ばいになった。
何が可笑しいと言うわけでもないのに、勝手に微かな笑みが口元に浮かぶ。
それを見られるのも、なんだか気恥ずかしくて、サンジはゾロから顔を逸らし、
そっと煙草に手を伸ばした。
「俺とヤるのが気持ちイイからだろ?」ゾロは悪びれずにそう言う。
顔を見なくても、どんな顔をしているのかサンジにはわかる。
きっと、とても嬉しそうにニヤニヤと笑っているに違いない。
「…ふん」その高慢ちきな物の言い方が可笑しいけれども憎らしくて、サンジは鼻を鳴らして笑った。
「そうだなア、」と敢えて、ゾロの言葉に頷いて見せ、すぐに底意地の悪い口調で、
「気持ちよくヤりてえ、って欲求を埋めるのに、たまたま丁度いいヤツが側にいたってだけどな」と皮肉を言った。
「…へっ…他のヤツで試す度胸もねえ癖に」
そう言ってゾロはまたサンジの体をまさぐり、摺り寄ってくる。
(…面倒なだけだ、そんな相手を探すのが…)と言い返す唇をゾロに塞がれ、
サンジはせっかく指に挟んだ煙草に火を着けもせずにポトリと床に落とした。
***
翌日。
冒険をする、と言って麦わらの一味はその島の森に入った。
だが、空島の樹海や、リトルガーデンの密林を体験して来た自分達が「冒険する」には
余りにものどかで、静かな場所だと言う事にすぐに気付き、途中で、「誰が今晩のオカズになるモノをたくさん捕ってくれるか」の競争になった。
そうなると、ロビンとナミはさっさと船に帰ってしまう。
結局残ったのは、男連中だけになってしまった。
「競争」、しかも食材調達の競争だ。
(…絶対、誰にも負けられねえ。特に、)ゾロにだけは負けたくない。
そう思ってサンジは森の中を獣の気配を探してザクザクと進んだ。
けれど、なかなか獣に出くわすどころか、気配さえ感じない。
当て所なく、森を突き進んでいると、ぽっかりと空から森に穴を開けたように、
目の前に野原が開けた。
人の手によって、樹が伐採され、そこだけを何かの目的のために切り開いた、どうやら
この野原はそんな場所の様だ。端から端まで歩いても、50歩もないだろう。
そんな狭い場所だけれど、サンジは思わず急に明るくなった視界に目を細めて、
空を見上げる。
木の枝と葉で切り取られたような灰色の空を見て、(…空を独り占め出来る場所だな)と
サンジは思った。
そして、足元には、白い花びらをつけた、茎の細い花が咲き乱れている。
(これは…)サンジは少し身を屈めて、じっとその花を眺め、
それから一本、手折ってみた。
(これの赤いのは見た事ある…。白いのもあるのか…)
(しかも、それがこんなにたくさん咲いてるなんて…)
ゾロの生まれ育った島では、その花は秋に野辺の道に群れて咲くのだと聞いた事がある。
グランドラインでも、サンジはその花を何度か見た事がある。
ゾロはその花の事を「彼岸花」と読んでいた。
それは炎のような紅色に、金色のような花弁の、どこか悲壮な姿をした花だった。
けれど、サンジの目の前に咲き乱れている花は、その炎の花と同じ形をしているのに、
鮮やかな緑の下草の上に咲く姿はまるで白衣を纏い、一身に祈る聖女の様に清楚で儚げだ。
その野原をぐるりと囲む背の低い木には、桃色や、黄色、赤などの色鮮やかな小さな花が細い枝がしなって地面に垂れるほど咲き競っている。
その鮮やかさが却って、白い彼岸花の美しさを際立たせていた。
「ん?」
カサカサ…と小さく風に下草が揺れた。
その風の中に、サンジは人の気配を感じ取る。
周りを見渡し、遠くを見通して、サンジはその気配の主を探した。
野原を突っ切っていったその先に、一人の少女らしき背中が見える。
そのたわわに咲く花を取ろうと、少女が一人、手を伸ばしている。
背中まで届く長い髪を一つに括り、背筋をピンと伸ばしきり、手も精一杯伸ばせるだけ
伸ばしている。
年の頃は、かつて知り合った少女、アデルと同じか、それよりもう少し幼いかも知れない。
あとほんの少し背伸びをすれば届きそうなのに、そのあとほんの少し、が届きそうにない。その懸命な姿がいじらしくて、サンジは少女に近付いた。
「…どの花がご希望ですか、お嬢さん?」
サンジは少女にそう声をかける。
ビク!と少女の肩が震え、恐る恐るサンジのほうへと顔を向けた。
こんな人気のない場所で見も知らない男に声を掛けられたら、少女でなくても、
普通、驚く。まして、幼い少女なら、怯えられて当たり前だ。
だが、サンジには例え少女であっても、女性に警戒心を抱かせない絶対的な自信がある。
笑顔と声音、物腰、言葉遣い。それらを優しく柔かく、そしてその女性を心から好きだと思うと、自ずと女性はサンジへの警戒心を解いてくれる。
そんな風にサンジは思っていた。
が。
少女は表情を強張らせて、大きな目を見開き、サンジを見上げる。
悲鳴を上げることもせず、逃げもしない。
恐ろしすぎて、声も出せない、身動きも出来ない、と言った様子で体も硬直してしまって、ガタガタ震えているだけだ。
その様子を見て、サンジの方が面食らった。
(なんだか、殺人鬼を目の前にして竦みあがっているみてえだ)と思うくらいの
異様な怯え方に、サンジは思わず苦笑する。
「…困ったなア、そんなに悪い事をするヤツに見える?」
そう言って、サンジは腕を伸ばし、桃色の花を一輪摘まんで、少女に差し出した。
「この色でいい?」と尋ねると、少女はコクン、と小さく頷く。
「他の花も摘んであげようか?」そう尋ねると、少女は同じ色の花を指差した。
***
言葉を知らないのか、怯えて声を出せないのか。
それとも、話せないのか。
サンジが花を渡した少女は、何を話しかけてもただ頷くか、首を振るだけで、一切声を出さない。長い睫毛、大きな黒い瞳、桃色の頬、とても可憐な顔立ちをしているのに、
その表情も殆ど動かない。
少女は、自分の背が届く高さに咲く花は自分で摘む。
届かない花を見ては、サンジを見上げるので、サンジは少女が指と目で指す花を摘んでは、渡した。
「綺麗な花束が出来たね。誰にあげるの?」
そう尋ねても、少女はやっぱり少女は何も答えない。
黙って、サンジに背を向け、急に小走りに走り出す。
その動きは戯れていた気まぐれな子猫が走り出したかのように軽やかだ。
寡黙で、無表情な態度とはかけ離れた、その快活な走り方にサンジは少し唖然とする。
本当は、活発で明るい少女なのではないか。
ふと、サンジは少女の駆けて行くその背中と足の運びを見て、そう思った。
曇り空が僅かに切れて、晴れ間が覗く。その雲の切れ間から細い細い太陽の光がこの野原に差し込んで、少女の髪を柔かく照らす。
それを追いかけもせず、見送っていると、忘れ物をしたかのように、少女はサンジを振り返る。
何か言いたげな目をして、じっと佇み、サンジをただ見ている。
「え?」
どうしていいのか分からずに、サンジがそう首を傾げると、また背を向けて数歩、走った。
それからまた振り返ってサンジを見る。
まるでついて来て、と言っているように思えて、サンジは少女の耳まで届く様に、少し大きな声で「…どこに行くんだい?」と聞いてみた。
だが、何も返事をしない。じい…とサンジを見ているだけだ。
「付いていっていいのかい?」と、もう一度尋ねると、少女は頷いて、サンジのところへ
走って戻ってきた。
そして、サンジの袖を掴むと、グイグイと引っ張り、歩き出す。
***
野原から、また森の中へと続く細い道に入り、数分歩く。
すると、前方の木々の間から、煌くような光が見えてきた。
その光に向ってさらに進むと、突然、森が途切れた。目の前には、湧き水らしい泉がある。
さして大きくはなく、ボートでも浮かべたら、ものの五分と漕がずに、端から端まで行けるだろう。
「へえ…こんなところにこんな綺麗な真水があるなんて…」
サンジはその泉に近付き、水底を覗き込む。透き通って、泳いでいる魚の姿が見え、清浄な水の中に古木がそのままの姿で沈んでいた。
手を浸すと、とても冷たい。湧き出す水が作る水流が立てる小さな小さな波が、
サンジの手をすすいだ。
その泉は、周囲をぐるりと森の木々に囲まれている。まるで聖地として守られている様だ。
目の前の美しい景色に見とれ、サンジが眺めていると、袖をツン、と少女に引っ張られた。
「ああ、ごめん、あんまり綺麗な水だったから」と言い訳しながら、サンジは少女の顔を見下ろした。少女の表情が和んできた様で、(ちょっとは心を開いてくれたかな、)と嬉しくなる。サンジは袖を引っ張られるままに歩いた。
「ここ?」
少女は急に立ち止まって地面を指差す。思わずサンジはそう聞き返してしまった。
足元の地面には花が咲き乱れている。
よく見れば、サンジと少女が摘んだ、木の上で咲く花が地面にみっしりと生えている。
その中に埋もれる様にして、女の姿を模った小さな石の彫刻と、それよりも少し小振りな、同じ形の彫刻がもう一つ、ポツンと置かれていた。
「これは…?」サンジの言葉に答えず、少女は手に握っていた花束をそっと地面に置き、墓標らしき彫刻の前に膝を折ってしゃがむ。
少女の寂しげな横顔を見てサンジは(母親と、姉さんか、妹の墓か…)と思った。
「この花、ここでも咲くんだね」
何気なくサンジがそう言うと、少女はまた黙って首を振る。
「え?そうやって、ここに置くだけ?」
不思議に思ってそう尋ねると、少女はコクン、と頷いた。
「昨日も一昨日も…その前もずっと、こうやって置いただけかい?」
「どれも、全然枯れてないね…」
たくさんの香華が時を止められたかのように、不思議と色褪せないまま、手向けられている。
少女はまた、サンジの袖を掴んで泉の際を歩き、茂みの一角までサンジを引っ張ってきた。
その茂みには、真っ赤に熟した野いちごが見事に実っている。
「うわあ、こりゃすごい!美味そうな野いちごだね!」
野いちごのあまりの瑞々しさにサンジは思わず声をあげた。
少女は一つ、摘み取ってサンジの掌に乗せた。
「花を摘む手伝いをしたから、お礼をくれるって事?」と尋ねると、少女は頷く。
「そっか。ありがと」サンジは礼を言い、すぐにその野いちごを口に含んだ。
口の中に、甘酸っぱい、さわやかな味と香りが広がる。
「こりゃ、美味いね1」お世辞ではなく、本心からそう言うと、少女は初めて
嬉しそうにニッコリと笑った。
それが、サンジとヒナコが出会い、心を許しあった最初の出来事だった。
第二話「隠れ島」
「真水もあるし、人が住めるのに十分な広さだし、気候もそう厳しくも無さそうだけど」
「どうして、この島には小さな村が一つあるだけなの?」
ログホースの示す航路から外れていると言っても、人が住めるのであれば、それなりに発展してもいい筈だ、とナミは不思議がった。
「美味しいものを食べたい、綺麗なものを身に着けたい、立派な家に住みたいって欲は
誰にでもあるものでしょ?」
「なのに、この島、食べ物も、着る物も何もかもが自給自足じゃない」
「まるで外から入ってくるものを拒んでるみたい。どうして?」
サンジとヒナコが仲良くなった事をきっかけに、麦わらの一味はその一家と…
と言っても、ヒナコには父親しかいないのだが、その父親、イサオとも親しくなった。
そして、その夜、ヒナコの家に招かれ、賑やかに食卓を囲んでいる。
その最中、ナミはイサオにそう尋ねた。
「…私、あなたの顔を見た事があるわ」
イサオが答える前に、ロビンが探る様な目でイサオの顔を見た。
「もしかしたら、…昔、賞金稼ぎだった、剣士さんにも見覚えがあるかも知れない」
それから、ちらりとゾロの方に死線を投げる。
「俺?知らねえぞ、このオッサンの顔は」
ゾロは、急に話題を振られて、迷惑そうな顔をする。
「確か、…船長さんを超えた、2億4千万ベリーが掛かった賞金首よ」
「「「ええ!?」」」
ナミとウソップ、チョッパーが驚いていきなり椅子から立ち上がり、壁際まで一気にうしろずさった。
「ど、どんな大海賊だよ、その金額は!」とウソップは怯えて怒鳴るが、
「へえ、…じゃあ、オッサン、実は相当強いのか?」ゾロは平然と薄ら笑いを浮かべている。
(…そんな風には見えねえけど、そうなのか?)サンジは目だけでゾロに尋ねたが、
ゾロは、首を僅かに振り、刀を抜く必要はない、とサンジだけに利き手をブラブラと振って見せた。
「海賊なんかじゃありませんよ」とイサオは苦笑し、
「海賊じゃなくっても…世界政府は、自分達の敵だ、と言うだけで賞金首にし、犯罪者に仕立て上げてしまうんです」イサオはそう言って、口元に苦笑を残したまま、
少し悲しげに目を伏せ、サンジが持ってきた酒の入ったコップに口を付け、ズズ…と啜った。
「…この世に生まれて、生きているだけで、私達の種族は悪魔と呼ばれる」
「私達は、普通に生きて、普通に子供を育て、普通に年老いて死んでいく事を望んでいる、ただの人間だというのに、それをあいつらは許してくれない…」
そのイサオの言葉を聞いて、ロビンの眼差しが急に変わった。
自分の身の上と、イサオの身の上があまりにも似ている。
その事に、心を動かされたのかもしれない。
「…わけを聞かせて頂けるかしら。私も、あなたに聞いて欲しい事がある…」
その真剣なロビンの口調に、イサオはしばらく黙り込む。
話すべきか、はぐらかすべきか、それを迷っている。そんな顔付きでロビンを見、
それから、何気なく、麦わらの一味全員の顔を探り見た。
「おじさん、実はロビンもね…」
その不安げなイサオの様子を見て、ナミがロビンの身の上をイサオに話して聞かせる。
オハラの事、ポーネグリフの事、古代兵器の事、自分達が今、どんな状況で世界政府に追われているか…。
イサオに話そうが秘密にしようが、これからの航海になんの支障もない。
それに、珍しくロビンがイサオに心を開きかけているのを見て、ナミは口添えをする気になったのだろう。
「ここで会ったのも何かの縁じゃねえか、オッサン」
「なんにも力になれねえかも知れないけどよ、自分達の事を友達だって思ってくれるヤツが世界のどこかにいるって言うだけでも、楽しくねえか?」
ルフィの言葉にイサオは「…確かにそうだな」と笑って、口を開いた。
***
能力者、と言われる者には、実は二種類ある。
一つは、「悪魔の実」を食べる事によって、能力者になった者。
もう一つは、生まれながらに「能力」を持っている者。
私達の種族は、「生まれながらに能力を持つ者」だ。
その能力は、普通の人間と交配しても、優性遺伝して次代の子に受け継がれていく。
どんな能力か、と言えば様々だ。
例えば、私は、行った事のある場所ならどこにだって瞬時にいける。
妻は、手を使わずとも、石を砕ける程の力を出せる能力を持っていたし、双子の娘、
ヒナコとチカゲは、二人とも「時を止める」能力を持っている。
ある者は、素手で刃を振り回すように、何でも切り裂く事が出来たし、
風を操り、空を自由に飛ぶ事が出来る者もいた。
私の兄は…いや、兄の話はいい。
そんな力を持っている私達を、戦の道具に使おうと、世界政府の奴等は、
私達の種族一人残らず捕まえ、大きな要塞に閉じ込めた。
その中では、我々は言葉には尽せないほどの酷い扱いを受けたよ。
人体実験…と言うのかな。
とても人間が人間に対してするような仕打ちじゃない。
好きあってもいない男と女を交尾させて無理矢理子供を生ませたり、毎日血を抜かれたり、
治癒能力のある者の能力を試す為にわざわざ別の能力者に瀕死の重傷を負わせたり…。
我々の種族の女は短命でね。30年生きれば、長生きした方だ。
それなのに、そんな中で暮らして、長生きなんか出来る筈がない。
たくさんの母親や、娘達がその要塞の中で死んでいったよ。
どうして、そんな力があるのに、逃げ出さなかったのかって?
自分の娘や、兄弟を人質に取られていたら、見捨てて逃げるわけにはいかないよ。
それに、私達には、絶対に破ってはいけない掟がある。
私達は、自分の能力で絶対に人を殺めてはいけない。
人を殺せば、その骸から瘴気が出て、それを吸い込めば、私達の体は、生きながらに腐ってしまう。
血を浴びれば、その血の穢れで能力を失い、気が狂ってしまう。
人を殺めたその罪の呪いが、先祖にも子孫にも及んで永遠に苦しまなければならなくなる。
自分だけがその罰を受けるならともかく、自分が生まれる為に命を繋いでくれた先祖にまでそんな累が及ぶのは、あまりにも罪深い事だ。そんな身勝手な事は決して許されない。
…そんなの迷信だと思うかね?そうかも知れない。でも、誰がそれを実証出来る?
もしも、それが事実だとしたら、無残な死に方をしなければならない。
悶死する事が迷信で全く事実でなかったとしても、先祖の魂を穢した事、未来に生まれてくる子孫に及ぶ影響を誰がどうやって見極める?
…誰にも、私達の信仰をただの迷信だと実証できないんだよ。
本来、人が持つべきではない力を持って、我々は生まれてしまった。
もしも、我々が何者かと戦えば、世界が滅んでしまうかもしれない。
我々の先祖は、そんな愚行を引き起こさない為に、この教えを「掟」として自らに課した。子孫である我々と、我々が生きる世界を守る為に、その「掟」を種族の血と魂に刻み込んで来た。私はそう考えている。
***
(なるほど、…それであの墓の周りの花は、咲いたままだったのか…)
イサオの話を聞いて、サンジは膝の上にちょこんと腰を降ろしているヒナコを見た。
サンジにだけは心を開いている様に見えるけれど、相変わらず全く喋らない。
船から持ってきたサンジの料理の本を字など読めもしないのに、熱心に見ている。
「…それが、どうしてこの島に?」
「海賊に貰ったんだよ」
ゾロの質問にイサオはそう答えた。
「確かにこの島は、海賊が根城にするにはちょうどいい島だけど…」とナミが首を捻りつつ、イサオに話の先をせがむ。
イサオの話は続く。
***
一年…いや、もう二年は経つかな。
私達が閉じ込められていた要塞に、海賊が戦いを仕掛けてきたんだよ。
とても激しい戦いで…。でも、そのドサクサに紛れて、私達は逃げ出そうとしたんだ。
その時、海軍と戦っていた、…結果的に私達を助けてくれた海賊が、この島への永久指針と船を一隻くれた。
そして、忘れもしない。私達にとって恩人の、その海賊のお頭はこう言ったんだ。
「もしも、神様があんた達を生かしていい、と言うなら、この島まで生きて辿り着ける筈だ」
「そこで生き抜く事が出来たら、…いつか、きっといい事があるさ」
そのお頭は、髪が真っ赤で、片腕で…。それから、目に大きな傷跡が合って…
***
「シャンクスだ!」
そこまで聞いて、ルフィは目を輝かせ、大声を上げた。
「じゃあ、この島はシャンクスのモノだったんだ!凄エ!やっぱり、シャンクスは凄エ!」
「でもよぉ、…おっさん。奥さんと、その子の双子だって言う子は…」
ウソップがそう言うと、イサオは静かに首を横に振った。
「…二人とも、もういない。見ての通り、今は父一人、子一人だよ」
「じゃあ、二人とも、世界政府に殺されたのか?」「…ウソップ、」
イサオの口が急に重くなった様に見え、サンジは(それ以上踏み込むな、)とウソップを止めた。
「私の賞金額を聞いて、トナカイの船医さんと長鼻の狙撃手さん達は驚いていたが、
強さで賞金額が決まる訳じゃないよ」
急に話題をかけたイサオの言葉にロビンが深く頷いている。
「生き残った私達の首にそれぞれ多額の賞金が掛けられているのは、私達が海賊以上に危険な存在だと思われているからだ」
「もし、特別な能力を持つ子供をたくさん作って、攻撃的に育てているとしたら、世界政府にとって、大きな脅威となるからね」
その言葉を聞いて、サンジは「ヒナコちゃんにも、賞金が?」と尋ねた。
イサオは、「そうだ」と頷く。
「まだ、7歳の子がたった6千万ベリーで世界中から狙われなければならないんだよ」
「生まれながらに特別な能力を持っている、ただそれだけの事で…!」
「…この子は、要塞の中で生まれた。だから、要塞の中とこの島の事しか知らない」
「そして、僅か30年ほど生きて…死んでいく」
「可哀想だと思うが…私は、この島の中で健やかに育ってくれるように、ただ見守ってやる事しか出来ないんだ」
そのイサオの沈痛な言葉に、返す言葉もなく、誰も何も言えなかった。
***
その次の夜。
昨日まで海は凪いでいたのに、朝から波が高く、船は出せなかった。
夜になると、波は一際高くなり、日暮れ前に降り出した雨の勢いも時を追って増していく。
「なんだか、二日も厄介になっちまって悪イな、イサオのおっさん」
口ではそう言いながら、ルフィはいつもどおり好き勝手に寛いでいる。
「なに、構わないよ。こんなあばら家で良ければいくらでも羽根を伸ばしてくれ」と言う
気さくなイサオに、ウソップも「オッサン、家の修理とかあればしてやるよ」とすっかり心を許している。
「…こちらこそ、粗末なものしかないのに、美味い食事まで作ってもらって申し訳ないねえ」
「うちのコックさんは、超一流の腕よ。材料が粗末でも、一流の料理に仕上げてくれるわ」とロビンの機嫌もいい。
「さあ、お待たせ、隠れ島名物のディナーが出来たぞ!」
サンジは自分が作った料理を取り分け、イサオの家の粗末な食卓に運ぶ。
和やかで賑やかな食事の時間が始まり、何事のなければ、その夜も酒を飲み遅くまで
楽しく過ごせる筈だった。
第三話「殺意の皿」
「美味そうだな、これ!何の肉だ?」
サンジが大きな皿に盛り付けて運んできた肉料理を見て、ルフィが目を輝かせた。
「俺が獲った豚だ」「豚?豚なんか、森にいたの?」
得意げなゾロにナミが驚いてそう尋ねた。
「この島をくれた海賊が、もともと家畜として飼ってたらしい」
「でも、私達が来た時にはもう野生化していてね。今じゃ、森の中で勝手に育って勝手に太って、いい味になってるよ」
皿を運ぶサンジの手伝いをしながら、イサオがナミの疑問に答える。
「馬も見たぜ」「馬?野生のか?」ゾロの言葉に、今度はサンジが反応する。
「馬だって食えるんだぜ。捕まえてこればよかったのに」
サンジにそう言われて、ゾロは「ああ、ウソップもそんな事言ってたが…」と答えて
森の中で馬を見たイサオの様子が妙だった事を急に思い出した。
何故かそれが心に引っかかり、ゾロはその時の事を思い返してみる。
***
「食料調達しなきゃな。狩り勝負の続き、するか?」
サンジのその言葉で、朝食を取った後男連中は森へ行って、猟をする事になった。
「あんたは道に迷いやすいでしょ。イサオさんと一緒に行きなさいよ。それからウソップも。ゾロと一緒なら怖くないんじゃない?」とナミが効率のいい組み合わせを決め、
ゾロはイサオとウソップと共に森で獲物を狩る事になった。
「俺達だけで狩りをしてたら全然獣なんかいなかったぜ」
「大丈夫、餌場があるからそこに行けば必ずいる」
(この森じゃ、でかいトカゲとかサイなんかはいねえだろうな)と思いながら、
ゾロはウソップとイサオの後ろを付いて歩く。
「ウサギみたいなのを一匹二匹捕まえてもルフィに丸呑みされるだけだからなあ」
ウソップのそんな溜息交じりの言葉にゾロは後ろから
「ウサギ?そんなしょぼい獲物じゃ、コックの組に負けるじゃねえか」
「一発大物を仕留めて、ギャフンを言わせなきゃ勝った事にゃならねえんだ」
「そう言うつもりでしっかり獲物を探せ」と檄を飛ばした。
「…し…」
イサオが急に二人の動きと声を制した。
「…なんかいるのか?」思わず身を伏せたウソップがそう尋ねると、イサオは頷き、
「…餌場はこのすぐ近くだ。ここで待ってて…」、とだけ言い、次の瞬間にはもう姿がない。
「え!?」「お?!」思わず、ゾロとウソップは同時に声を上げる。
掻き消えた、と言うよりも、もともと人間などそこに最初から居なかった。
そんな風に思えるくらいの早業だ。
「…消えたぜ、オッサン」ウソップは唖然として、イサオが立っていた地面をまじまじと眺めている。
「話には聞いたが…こりゃ、確かに人間業じゃねえ」ゾロも流石に驚いた。
「音ひとつ立てないで、消えて、またいきなり現れるわけだろ?」
「猟銃持ったままでも移動出来るのか。神出鬼没の殺し屋になれるぜ、あのオッサン」
ウソップがそう言い、「あのオッサンは人なんか殺せねえよ」とゾロが答えた時、
イサオが立っていたあたりの風景が揺れた。
そこに陽炎が立ち昇ったかのように目に見える風景が歪む。
「!」それに気が付き、そして一度瞬きをした後、もうイサオはゾロとウソップの目の前に立っていた。
「今、ちょうど餌を食べる為に野生の豚が群れてますよ。行きましょう」とにこやかに、背中越しの森を親指を立てて指差す。
「なんだ、獲って来なかったのか?側まで行ったのに、見てきただけ?」
ウソップが拍子抜けをしたような声でそう言うと、イサオは「能力を使って殺生してはいけない"掟"だから…、」と答え、下草を掻き分け、歩き出した。
ゾロはなるべく大きな体の豚を選んで狩った。
豚、と言っても野生化しているのでかなり凶暴だったが、それでも、所詮は豚だ。
鼻っ面を思い切り殴ればそれで簡単に仕留められる。
「もういいだろ。サンジ達も何か捕まえてくるだろうし」
三頭殴って倒すと、ウソップがそう言ってゾロを止めた。
「まだ担げるぜ。たった三匹ぽっちじゃ、一度の食事で全部食っちまうぞ」と言い返す。
その時、森の下草がガサガサ…と大きな音を立てた。
豚よりももっと大きな獣の気配だ。
ゾロも、ウソップも、イサオもその気配を感じる方へと顔を向けた。
「…馬だ」ウソップがそう呟く。
鬱蒼とした森の木々の間に真っ黒な馬が佇んで、じっと三人を見詰めている。
いや、観察している。そんな風にも見えた。
その馬が、ゆっくりと近付いて来る。
喉が怯えるようにゴクン、と鳴る音を聞いて、ふとゾロはイサオの横顔に目をやった。
(…なんだ?)
まるで悪魔が幽霊を見ている様な、そんな目でイサオはその黒い馬を見ていた。
寒くもないのに震え、暑くもないのに、額に脂汗が浮いている。
「…少し、ここを動かずに…。この先にもう一箇所、豚の餌場があるので…見て来る」
蚊の泣くような声でそう言うと、またイサオの姿が音もなく消えた。
それと同時に、馬も踵を返し、森の奥へと歩いていく。
まるで、イサオ以外に用はない、と言っている様だ。
「…あの黒い馬、なんだか怖エな」ウソップのそんな小心な言葉を聞いても、何故かゾロは笑う気になれない。
あの黒い馬が怖い、とウソップが感じるのも無理はない気がする。
闇のように黒い、と言うだけでなく、野生の動物にしてはどこか禍々しい。
(確かに、…バケモノじみた雰囲気の馬だ)と、ゾロも思った。
それから、半時間ほど経ってもイサオは戻ってこない。
「遅いな…」「…なにかあったのか?まさか、馬に蹴られたとか」
心配になって二人がジリジリし始める頃、やっとイサオは二人の前に現れた。
「いやあ、遅くなってすまなかった」
「能力を二回も連続で使うと疲れるって言う事をすっかり忘れていたよ」
「豚の餌場まで着いたら、頭が痛くて動けなくなってしまってね」
そう言うイサオの口調は明瞭で、表情も冴えている。姿を消す前と、あまり変わりはない。
けれど、イサオの顔色はどこか蒼ざめていて、張りのある声を出そうと空元気を装っているようにゾロには見えた。
「もう平気なのか?」と気遣えば、「大丈夫、大丈夫。休んできたから…」と元気そうな声で言う。
「馬は捕らないのか?そんなに疲れるんなら、わざわざ豚を捕りに行かなくても、
目の前にあんなにでっかい馬がいたんだから、あいつを狙えばよかったのに…」
帰り道すがら、ウソップがイサオにそう言った。
「馬…?」イサオは豚を担いだまま、ウソップの言葉に怪訝そうな顔で振り返る。
「馬だよ、あの黒い馬。目の前にいたのに」
ウソップの言葉を聞いて、イサオはほんの数秒、表情を強張らせた。
だが、急に愛想笑いのような笑顔を浮かべ、唐突に思い出したかの様に、「ああ、あの、さっきの黒い馬か!」と答えている。
その目まぐるしい表情の変化に、ゾロはイサオが表情を強張らせたのは、(…気のせいか…)と思った。
「馬は前に食べたけど、捌くのが大変だし、あんまり美味くなかったからね」
「もう、食べない事にしたんだよ」
「捌くのはサンジだぜ?それに、馬肉だってあいつなら美味く料理してくれるのに」
そうウソップが言っても、イサオは曖昧に笑って、
「…あ、まあ、…馬より豚の方がずっと美味いから、…」と言葉を濁した。
***
そして、夜。
作った料理を次々と食卓一杯に並べるが、それがあっという間になくなっていく。
その様子を見ていたイサオがサンジに声をかけた。
「料理が多すぎて、皿が足りないようだね」
「洗いながら使うから構わねえよ、」と答えたのに、イサオはサンジのその言葉を聞きもせずに、「ヒナコ、裏の納屋へ行って皿を取って来なさい」と言った。
裏の納屋、と言っても家の中から灯りを持って外へ出なければならない。
雨が降り出した上、もう夜になっていて外は真っ暗だ。
ヒナコは困った様にサンジを見上げる。
「いいよ、一緒に取りに行こう」とサンジはヒナコの手をとり、台所から外へ出る。
サンジが外へ出たのを見届けてから、イサオは目を鋭く光らせて、一人一人に料理が取り分けた皿を眺める。
物音を立てないように用心し、ポケットからそっと小さな瓶を取り出した。
その瓶の口を素早く開けて、ポトリ、ポトリ、…と二滴、一つの皿にその雫を垂らす。
「…許してくれ…。これで、もう許してくれ…!」
誰かにする切願するような声でそう呟き、イサオはギュ、と目を閉じた。
大きく一つ、ため息をつき、それから決心がついたかのように目を開ける。
「おい、コック!料理はもうないのか?」
台所に入ってきたゾロにそう声を掛けられ、イサオは慌てて振り向いた。
「まだまだあるみたいだ、すぐ、持っていくよ!」と明るく返事を返す。
その手がわずかに震えていたけれど、納屋からヒナコが戻って来た時にはもう止まっている。
何食わぬ顔をし、毒の雫が混ざった皿をヒナコに手渡した。
麦わらの一味が談笑する声に消されて、イサオがヒナコに囁いた声は誰にも聞こえていない。
「…これが1番美味しく出来たそうだよ…。剣士のお兄さんに持っていっておあげ」
その言葉にヒナコは素直に頷き、ゾロの前に持っていく。
もしも、イサオ自身が皿を持っていたら、ゾロは敏感に殺意を感じ取っていただろう。
だが、運んできたのは何も知らないヒナコだ。
だから、ゾロは何も警戒せず、殺意の皿の料理を口に運び、そして飲み込んだ。
(続きは、オフ本にて♪) 戻る ★