|
MAMA
俺は鉄男と傘というアンバランスさに含み笑いを漏らした。
バカにしたのではない。
鉄錆びとヤニのにおいしか纏わないその身体が、その日だけ雨の匂いがしたのだ。
広い背中にまつわるそれは、地下にこもった負の臭気を打ち消して、不健康に曇った彼の体臭をほのかに漂わせた。とうに忘れていたがそれは人間くさかった。
無機物はこんなに温かいものを生み出せない。
限界まで吸い尽くされた体力を更に奪う敷き詰める雫が、青色の輪に突然遮られたとき俺は目を瞠った。もはや気力だけで発条を回していた自分には、その仕草さえ辛かったのだけど。
「鉄男・・・」
青色の空を広げた男の名を掠れた声で呟いた。全身濡れているのに唇は青く変色してかさかさだ。青の傘を隆起した肩にもたせて、三井の唇に鋭い視線をやる鉄男は、何を思ったのか乾いた唇を同じもので触れ合わせた。ガキの俺には興味も無いのか舌の遊戯はやりもしない。それはただ、その部分に体温を通わすだけの行為だった。
「俺のために・・・似合わないことを」
傘も、口付けも。あまりに温かくて嫌になる。
優しくされるのはあの陽だまりの体育館にいたとき以来で、忘れていた涙が視界をぼやけさせるのに羞恥した。
「まだ体内にも水分が残っていたか」
「何とか、生きていける位には・・・」
弱弱しく笑って、鉄男の前に俺は右の拳を掲げた。青黒く変色した手の甲と連なる指には、血痕が筋のように何本も走っている。乱暴な使い方に折れても良かったのに、もともと鍛えてあったそれはダメージを表層のみでとどめた。
その結果が足元に転がっている。浅い息で、泥の水溜りに沈む長身の男。
「やったようじゃねぇか・・・生きてるぜ。お前は生きてる」
「おう・・・生きてる」
水と血と泥と痣と涙でぐちゃぐちゃになった顔をくしゃくしゃにしながら俺は鉄男の言った言葉を繰り返した。この拳で、勝利を掴み取った。殴られた痛さも殴った痛さもそのまま糧になる。鉄男に手首を取られ立ち上がって、改めて実感した。
「まだ生きてる・・・どこでだって生きてやるさ」
伸びた髪をかきあげて、上空を見据えた。らせん状に雨が降りそそぐ。
目を閉じれば雨のにおい、そして隣に立つ鉄男のにおいしかしない。
「ぼっちゃん傘はいらねぇのかよ。お前のために持ってきたんだぜ」
「いらねぇ。んなモンもってくるならお前を寄越せよ」
「クッ、もっとちゃあんと選びな三井。俺はお前を守らないが傘は守ってくれんだぜ?」
「嘘ばっかり。卑怯者」
にやりと笑うくせのある口元は、ぞっとするほど成熟した大人の仕草で、三井の子供の身体を震えさせた。
「今だけさ。俺の気まぐれが過ぎるまで」
鉄男は青色の傘を閉じて丸めると、その先を俺の胸元に突きつけた。
「それはいつまでだよ」
「さぁ」
「やっぱり・・・卑怯者」
三井は眉を寄せ唇を尖らせた。唇の端に残った裂傷が引きつるような痛覚をひきつける。
「傘はいらねぇよ。鉄男もとっとと捨てちまえよ。どうせ差してたって濡れるトコは濡れるし、人間だって水で出来てんだ。この世は水ばっかなんだ」
だから鉄男の体臭は雨の匂いがするのだろうか。いいながら三井はじくじくと血を垂れ流す自分の手の甲を見遣った。薄い皮膚に血管が脈打つ。
鉄男が鼻で笑う。
「だから濡れてもいいってか?冗談じゃねぇよ。みっともねぇ。ただ雨に濡れてる奴は愚かもんさ。自分の温度を奪われていることにすらきづかねぇ」
鉄男は唇だけで嘲笑しながら、俺の視界から傷だらけの手を奪った。鉄男のごつい手のぞっとするほどの熱さに思わず腰が引ける。
「・・・な。死にかけてんのにも気づかねぇ」
「お・・・俺の手死んぢまうのか?」
切ったはずの世界に対する未練が断片を覗かせる。混乱する思考から力ずくでそれを排除して縋る目で鉄男を見た。
「知らねぇよ」
鉄男の言葉はそっけない。何時だって中途半端に構うだけで確信に触れてくれない。
何とか頭の回転を廻らして、一本づつ指を動かし、まだ大丈夫なことを確認する。比較的軽症な左手で右手を包み込むように支えると、少しづつ熱と痛覚が戻ってくるのを感じた。
「どうよ」
「・・・大丈夫だ」
「そうか」
表面だけの会話で、意志の疎通を図る。
それでも彼が発する雨の匂いと纏う熱い空気は俺を安堵させた。
そしてその雨が蓄積されて創られたような、絶えず変わらない海のような彼の内面。
目標もなく、しがらみもないその自由な空気に憧れた。
「もっと強くなって俺に手間ぁかけさせんな」
「鉄男が勝手にでばってくんじゃん。じきに傘も鉄男もいらなくなるさ」
「へっ、言いやがるな」
ほんの、軽口のはずだった。2人とも笑っていたのだから。
「でもバイクには乗せてくれよ。帰るところは一緒だろ?」
鉄男は笑いながら首だけで路地の向こうを促す。雨の幕に覆われた黒光りする車体は、この静かな世界で圧倒的な存在感を誇示していた。
シルバーの配管が幾重にも連なるその上の大きなシートにかけることが出来るのは、鉄男と俺だけだ。低いエンジン音を響かせて、今は荒れ狂う海を横切り帰路につく。
いつもどうりに鉄男の後ろにまたがり、プラスして今日は縋るように広い背中に頬を擦りよせた。
「雨の匂いがする・・・」
「さんざ濡れたからな。もっと濡れるぜ」
「いい。もう温けぇし・・・」
触れる頬のそばから。
消え入りそうなほどに。
そして風が過ぎ去った後のこの場所には、俺のノした男と流した血と、青色の傘だけが放置される。
重厚な存在の匂いはもうここにはない。
最早どこにもない。
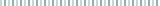 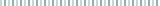
どうも私の中で鉄三は騎士と姫です。ストイックかつ精神的エロティックな(意味不明)

|